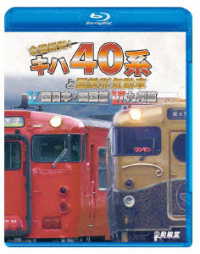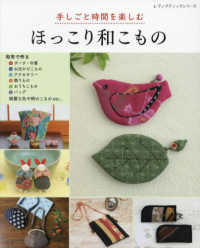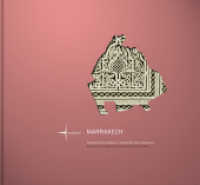内容説明
世界有数の火山列島という国土の成り立ちから、大地震はじめ大天災にしばしば見舞われてきた日本。そうした大災害が、どのように歴史を動かしてきたのか。また、先人達はいかにして復興を成し遂げたのか。天災(地震・津波・噴火)という新視点から日本史を捉え直した意欲作。
本書では、日本史を動かした主要災害として、天長出羽地震、鎌倉地震、天正地震、慶長伏見地震、寛文高田地震、宝永富士山大噴火、天明浅間山大噴火、島原大変、善光寺地震、安政江戸地震、磐梯山大噴火、濃尾地震、明治三陸大津波、関東大震災などを取り上げている。そして、これらの被害そのものより、災害後、当時の為政者(トップ)や人々がいかに考え行動して、復興の道を歩んだかを分かりやすい語り口で解説している。
なかには、天災という切り口から歴史を捉え直すことにより、従来の通説とは違った歴史解釈が示されている点もあり興味深い。たとえば、豊臣家を弱体化するために徳川が行わせたといわれる寺社造営なども、慶長伏見地震の復興という視点から捉え直すことにより、違った側面を浮かび上がらせている。そのほか、江戸幕府による復興税の不正利用、復興政策のまずから起きた一揆、地震の二次被害を防いだ名君、世界的科学者・野口英世誕生のきっかけとなった大噴火――といった意外な実話がふんだんに紹介されている。
また、たび重なる大津波にもかかわらず進まなかった三陸の住居の高所化、関東大震災後の政争により縮小された復興計画……など、現在の日本が直面する、東日本大震災からの復興という課題に対しても大きな示唆を与える内容になっている。
目次
天災の古代史―災害を天の警鐘とみなした古代王朝
1293年 永仁鎌倉地震―復興された武士の都
1585年 天正地震―天下人秀吉の恐怖体験
1596年慶長伏見地震―創出された災害復興への王道
1665年 寛文高田地震―天災が生んだ名宰相
1707年 宝永富士山大噴火―欺瞞に満ちた復興策
1783年 天明浅間山大噴火―田沼政権を崩壊へと導いた天災
1792年 島原大変―格差社会を拡大させた大津波
1847年 善光寺地震―二次被害を防いだ真田の智謀
1855年 安政江戸地震―幕末動乱を加速させた直下型地震
1888年 磐梯山噴火―日本初の義援金と災害報道
1891年 濃尾地震―地震学を発展へと導いた都市災害
1896年 明治三陸大津波―生かされなかった過去の教訓
1923年 関東大震災―幻の東京再生計画
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あや
日和見菌
茶田