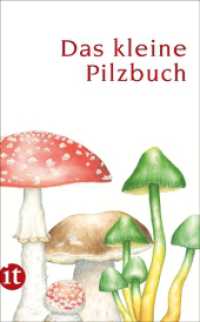- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「なぜ人を殺してはいけないのか」「なぜ民主主義はうまくいかないのか」―現代の社会の抱えるさまざまな難問について、京大生に問いかけ、語り合う。若い学生たちの意外な本音から、戦後日本、さらには現代文明の混迷が浮かび上がってくる。旧来の思想―戦後民主主義や功利主義、リベラリズム、リバタリアニズムでは解決しきれない問題をいかに考えるべきか。アポリアの深層にあるニヒリズムという病を見据え、それを乗り越えるべく、日本思想のもつ可能性を再考する。
目次
第1講 現代文明の病―ニヒリズムとは何か
第2講 なぜ人を殺してはいけないのか―自由と規範をめぐる討議1
第3講 沈みゆくボートで誰が犠牲になるべきか―自由と規範をめぐる討議2
第4講 民主党政権はなぜ失敗したのか―民主主義をめぐる討議1
第5講 政治家の嘘は許されるか―民主主義をめぐる討議2
第6講 尖閣諸島は自衛できるか―「国を守ること」をめぐる討議
第7講 主権者とは誰か―憲法をめぐる討議
第8講 ニヒリズムを乗り越える―日本思想のもつ可能性
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
道楽モン
32
「ハーバード白熱教室」ならぬ「京都大学白熱教室」。全8回の講義を書籍化。2011年当時の政治状況(民主党政権時)を踏まえて、ニヒリズムや新自由主義などを各回のテーマとして展開。討論ではなく、問題提起して受講生に考えさせ、それぞれの回答を裏付ける思考が、歴史的にどう発達してきたのかを解説する形式(当然、佐伯先生の予習に誘導される)。読みやすいが、答えは無い。受講生は徹底して自己の思索を促される。学問の基本的な姿勢を学ぶには最適だろうが、まさに一般教養課程なので、ここから先は各自で調べて読んで考えるが必須だ。2024/08/30
masabi
13
グローバル化が進み、西洋発のニヒリズムも世界に蔓延っている。ニヒリズムとは、絶対の価値を見出だせないこと、無を信奉することである。日本も例外なくニヒリズムに覆われている。そして、その処方箋は日本思想にある、とするのが筆者の主張である。興味深かったのはニヒリズムを巡る言説と民主主義の2つ。民主主義は民意というありもしないものに基礎づけられているので、ニヒリズムを患っているけれども、他の政治制度よりは害悪が少ない。民主主義の要素と非民主主義的要素を組み合わせる必要がある。2016/03/03
こばやし
10
難破船の話。誰を犠牲者にするか?リバタリアニズム、リベラリズム、功利主義、ポストモダニズム… 結局は功利主義かつポストモダニズムであり、今の自分もボードから落とされた一人のうえに生きていて、世代を越えたくじ引きを引いたにすぎない。こんな考え方をしたことはなかった。この本は様々な問題を著者の経験や読んだ本を踏まえてわかりやすく解説してくれているため、ある意味では池上彰さんの知らないと恥を~シリーズなどを読んだあとにこれを読み、少しずつ公共哲学や政治・経済理論が血肉化していることを感じた。佐伯啓思さんの講義を2015/12/24
姉勤
9
知らず知らず陥っているニヒリズム的な感情。マスコミの論調は全てこうだ。煽情された世論も、それに従っても反発揶揄しても、結局ニヒリズムに辿り着く。我欲の放棄以外ニヒリズムの排除は無理だとおもう。それに少しでも近づけるための論議、各章とも答えを提示せず考えさせる内容となっている。ニヒリズムが避けられないとしたら最悪の選択をしないように感情の制御を学んでいくしか無い。2012/05/09
takizawa
9
サンデル白熱教室方式のディスカッション型講義をまとめたもの。現代政治哲学ではニヒリスティックな状況を越えられない,特に日本の病理的現象が顕著ということが色んな議論を通して明らかになるがこれらは西田哲学オチへの壮大な前フリなんだなぁ。尖閣問題や政権交代などの話題が一昔前のものになる前にご一読を。2011/08/08