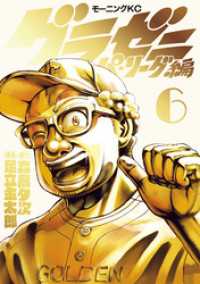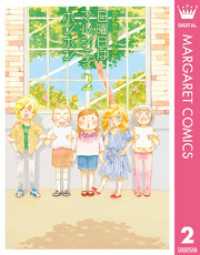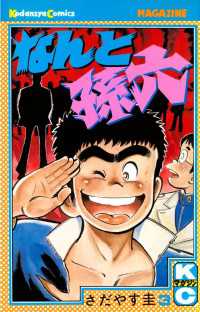内容説明
北の町に暮らす人々を描く悲運の作家の遺作
「海炭市叙景」は、90年に自死を遂げた作家、佐藤泰志(1949-90)の遺作となった短編連作です。海に囲まれた北の町、「海炭市」(佐藤の故郷である函館市がモデルです)に暮らすさまざまな人々の日常を淡々と描き、落ち着いた筆致の底から、「普通の人々」の悲しみと喜び、絶望と希望があざやかに浮かび上がってきます。この作品が執筆された当時はいわゆる「バブル」時代でしたが、地方都市の経済的逼迫はすでに始まっていました。20年の歳月を経て、佐藤泰志が描いたこの作品内の状況は、よりリアルに私たちに迫ってくると言えます。
函館市民たちが主導した映画(熊切和嘉監督・加瀬亮、谷村美月、小林薫、南果歩などが出演)の公開は2010年12月。映画化をきっかけに、心ある読者に愛されてきた幻の名作が、ついに電子書籍となって登場!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
216
青函連絡船と函館を題材にしたBSのドキュメンタリー番組で、この作家を初めて知り無性に読みたくなった。佐藤泰志(さとう・やすし)は高校生から作家として注目を集め、芥川賞に5回ノミネートされるも獲れぬまま、41歳で自死。本作は函館山を舞台に、叙情溢れる筆致でつづった連作短編集だった。「わたしは、この街がただの瓦礫のように感じたのだ」。死後、全て絶版となった作品群が再評価され、本作は「市民映画」として映像化され蘇った、記念碑的小説だった!2025/07/28
遥かなる想い
177
駅の本屋で、さりげなく紹介されていた本。筆者佐藤康志は何度も芥川賞候補作品を書きながら受賞できず、1990年突然の自殺を遂げた作家だそうである。この本の「海炭市」は筆者の育った函館をモチーフに、そこで暮らす多くの人たちを克明に描いている。読んでいてひどく懐かしい気がしたのは、その文体なのか、その叙景なのか…普通の人たちの18の人生を描く その筆力には非凡なものを感じるのだが…2011/05/15
はるを@お試しアイコン実施中
138
🌟🌟🌟🌟☆。いつかガッツリ向き合いたかった作家のひとり。「無冠の帝王」と言ったら天国から怒られるだろうか。海炭市で生きる様々な人々の生きザマを描いた二部構成全18編の人間讃歌。どいつもこいつも愚直で頑固で不器用で生き方が下手クソでバカばっかりで俺はたぶん登場人物の誰とも友達になれないと思うけれど何故か全員愛しくてなってくる。親近感が湧いてくる。抱きしめたくなってくる。「まだ若い廃墟」「裂けた爪」「夜の中の夜」「週末」「裸足」「まっとうな男」「夢みる力」「しずかな若者」が特に良かった。2022/01/10
新地学@児童書病発動中
127
これは傑作。函館らしき街を舞台に普通の人々の喜び、哀しみ、怒りを描いていく内容。一つの街を丸ごと描こうとする作者の意志が好きだ。華やかに生きている人たちではなく、どん詰まりで懸命に生きている人たちを丁寧に描いていくところに作者の人間的な優しさを感じる。都会ではなく、地方で生きている人間は、ここに出てくる登場人物たちと同じやるせなさや憤りを感じているだろう。飲酒運転で警察に捕まって、警官に手を出す男の話「まっとうな男」の「ただ働いてきた、それだけの人生だ」と言う独白は悲しくも、切ない。 2016/08/28
まーくん
89
先日放送のNHKBS「新日本風土記 函館の光…」に触発されて。函館に生まれた著者佐藤泰志は自分と同年代。自分は函館には住んだことはないが、何かと縁あり、仕事でも度々訪れたこともある。実在の地名を用いると差し障りがあるためか、海炭市という架空の街の名で綴られるが、海峡に位置し正面に砂州で繋がる400m弱の山があり山麓から頂上へロープウエイが通じてる人口35万の都市。路面電車が走る街と言えば…。ただ炭鉱が隣接してるということだけを除いて。故郷の地誌的記憶を舞台に、80年代末のこの地方都市に住む様々な人々の⇒ 2025/03/31