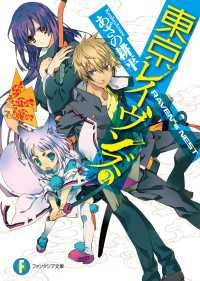- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
テレビ視聴率の低下、新聞部数の激減、出版の不調……、未曽有の危機の原因はどこにあるのか? 「贈与と返礼」の人類学的地平からメディアの社会的存在意義を探り、危機の本質を見極める。内田樹が贈る、マニュアルのない未来を生き抜くすべての人に必要な「知」のレッスン。神戸女学院大学の人気講義を書籍化。【光文社新書】
目次
第1講 キャリアは他人のためのもの<br/>第2講 マスメディアの嘘と演技<br/>第3講 メディアと「クレイマー」<br/>第4講 「正義」の暴走<br/>第5講 メディアと「変えないほうがよいもの」<br/>第6講 読者はどこにいるのか<br/>第7講 贈与経済と読書<br/>第8講 わけのわからない未来へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
200
神戸女学院大学での講義に基づいたものだが、ここでも、筆者は学生たちに鮮やかな知のパラダイムシフトを示して見せる。タイトルはメディア論だが、内容的には教育論から社会のしくみにまで及ぶ。これを読んでいると、筆者の内田樹はあたかも屈原の「衆人皆酔我独醒」のごとくだ。例えば、冒頭のキャリア教育論にしても、世を挙げて「キャリアだ。適性だ」と騒いでいる中で、そんなものは結婚みたいなもので、後から要請されて身に付くものだから必要ないのだと喝破する。たしかに彼の言うように、子どももいないのに父性に燃える男は不気味だ。 2013/06/13
KAZOO
122
この筆者については好きな人と嫌いな人がはっきり分かれているような印象を受けます。私はあまり感じないのですが、この本を読むとメディアがかなりクレイマー化して、一つの事件をかなり各報道局で競って特集をしたりするのを見ると感じることがあります。ニュースしか見ないのですがすべてが同じような報道を行っています。ですので視聴率などが落ちていくのも当たり前ではないかと思われます。また読者について書かれているのを読むと、最近図書館戦争という映画を見たのが思い出され、この中の出来事は近未来あるような気がしています。2015/10/26
seki
95
テレビ、新聞、出版界などメディア全般の凋落を筆者が批判的に論じる一冊。概ね筆者の意見に賛同。ただマスコミの無責任さは今に始まったことでないと思う。先の大戦で、戦前戦中は日米の国力の差を知り得ながら、軍国主義と一緒になって国民に戦意を煽り、敗戦となると自らの責任には目を背けて、被害者のように振る舞っていなかったか。国民に誤った情報を伝えても、謝罪がないのはなぜか。筆者はメディアの不調は国民の知性の不調につながっているという。日本人はメディア情報からもっと自由になった方がいい。2019/12/01
マーム
79
本書の主題からはやや外れるかもしれませんが、書棚は僕たちの「理想我」である、という行にわが意を得たりと思いました。書棚に「読みたい本」ばかりでなく「いずれ読まねばならぬ本」も並べるのは、「いずれ読まねばならぬ本」を読みこなせるリテラシーを備えた、「十分に知性的・情緒的に成熟を果たした自分」にいつかはなりたいという欲望が私たちにあるからであり、それらの本が書棚に鎮座しているのを折りに触れて目にすることによって自らの成長を促すというのが内田先生の主張かなと理解。ということで今日も私は「買い置き」を続けます!?2011/09/17
みのゆかパパ@ぼちぼち読んでます
57
ネットの普及により、その存在が脅かされているメディアと出版産業をめぐる問題を考察した一冊。メディアについては、ネットの出現といった外的要因にではなく、その報道の質という内的なものに凋落の原因があるという指摘は、はからずも福島原発事故を通じて実証されたことでもあり、大いに納得できる。ただ、それをクリアしたとしても紙媒体のメディアに未来があるかについてまでは言及されず、そこに携わる一人としてはもどかしさもあったが、読者を消費者としてだけ見る出版産業のあり方への警鐘を含め、うなずかされることの多い一冊だった。2012/11/10