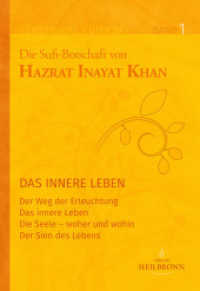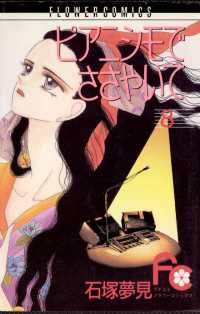- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
豊前中津奥平藩の下級士族の末子が「窮屈な小さい箱」をヒョイト飛び出し、洋学を志して長崎、大阪、江戸へ、欧米へ……。幕末・維新の大変化の時代を「自由自在に運動」し、慶應義塾を創設、大いに「西洋文明の空気」を吹き込んで日本の思想的近代化に貢献した福沢諭吉。その痛快無類の人生を存分に語り尽くした自伝文学の最高傑作。(講談社学術文庫)
目次
凡 例
初版序(石河幹明)
幼少の時
長崎遊学
大阪修業
緒方の塾風
大阪を去って江戸に行く
始めてアメリカに渡る
ヨーロッパ各国に行く
攘夷論
再度米国行
王政維新
暗殺の心配
雑 記
一身一家経済の由来
品行家風
老余の半生
校 注 土橋俊一
解 題 土橋俊一
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
46
『「さようさ、まず日本一の大金持ちになって思うさま金を使うてみようと思います」』P23福沢諭吉が子供の頃に放った言葉。強烈。でも、福沢諭吉が大金持ちになりたかったのって、内村鑑三がいう『遺物』をこの日本に置いていきたかったがためだと思います。究極のリアリストたる諭吉がお金に重きを置かないという選択肢はないし、ましてや下級武士。お金に頼らなければ日本を変えることは出来ないということを薄々感じていたのでしょう。世間に溶け込んでいるようで世間からはみ出している福沢流の生き方には学ぶべきものがあります。2023/07/21
newman
11
「人の上に人を作らず・・・」と言っていながら、幼稚舎に入れれば、大学までエスカレーター、と思って読まなかったが、面白く読みました。彼がお酒が大好きな人だったこと。咸臨丸に乗ったのは当然に選ばれた人だったのかと思っていたが、伝手を頼って乗れるようになったこと。大阪の適塾で勉強し塾頭も勤めていたが、血を見るのもダメだったこと。明治4年3月に慶應義塾は三田に引っ越したが元は島原藩の屋敷だったこと。借金をしたことがなかったこと。吉原を知らなかったことなどを知りました。この本は明治時代のベストセラーだったそうです。2022/05/18
takam
9
鎖国からの開国、幕末の動乱を過ごし、日本の近代化を推進した福沢諭吉の自伝である。幼少期の話から、書生として大阪の適塾で蘭学を学び、渡米や西洋訪問、そして慶應義塾の創設や彼の考えが描かれている。福沢諭吉はもともと平等の考え方を幼い頃から持っており、学問のすゝめの著明な冒頭の文章はその思想から来ているのだろう。Competencyを「競争」と訳し、武士に「穏やかじゃない」と言われたストーリーも収録されている。福沢諭吉は仏のような存在かと思いきや、偏見が強い点もあったり、一筋縄ではいかない性格のようだ。2019/01/09
シモネッタ
6
ユーモアも交え、生き生きとした語り口。目の前で喋っているが如く。面白い!2017/11/25
nicokiyo
5
また読み直してみたいと感じました。読む時々で得るものも感じるものも違ってくるのではないかと思います。2019/03/03