- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
音楽の聴き方は、誰に言われるまでもなく全く自由だ。しかし、誰かからの影響や何らかの傾向なしに聴くこともまた不可能である。それならば、自分はどんな聴き方をしているのかについて自覚的になってみようというのが、本書の狙いである。聴き方の「型」を知り、自分の感じたことを言葉にしてみるだけで、どれほど世界が広がって見えることか。規則なき規則を考えるためにはどうすればよいかの道筋を示す。
目次
第1章 音楽と共鳴するとき-「内なる図書館」を作る(音楽の生理的次元
相性のメカニズム ほか)
第2章 音楽を語る言葉を探す-神学修辞から「わざ言語」へ(「鳴り響く沈黙」とドイツ・ロマン派の音楽観
神の代理人としての音楽批評 ほか)
第3章 音楽を読む-言語としての音楽(「音楽の正しい朗読法」-一八世紀の演奏美学
音楽/言語の分節規則 ほか)
第4章 音楽はポータブルか?-複文化の中で音楽を聴く(再生技術史としての音楽史
演奏家を信じない作曲家たち ほか)
第5章 アマチュアの権利-してみなければ分からな
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
386
音楽の「聴き方」というよりは「語り方」を語った本。そもそも著者によれば、音楽を語ることは、すなわち聴くことでもあるのだが。引用も含めて随所に卓見。構成も語り方も上手い。なるほどと思ったのはハンスリックの「(音楽美学は)我々を圧倒する感情の描写に終始している」との言。また、第2次大戦末期、フルトヴェングラーによる第9のコンサートが聴衆に圧倒的な感動を与えたことの両義性と、近代音楽(演奏を含めた)の終焉を語る辺りは圧巻。他にも音楽を語る際の「わざ言語」など有効な指摘に溢れる。2019/06/28
やっさん
118
★★★★☆ 一貫して〝音楽の営為は演奏・享受・批評の三観点から成る〟というスタンスで語られている。僕は、演奏者でも愛好家でも指導者でもあるから、三つの観点がいずれかに傾倒しないような努力が常に必要だ。2017/11/16
ジョンノレン
48
著者2冊目。素朴に聴く段階から、語る楽しみに導く道案内の書。とはいえ内容には中級から上級レベルも。多様な切り口で、その構造と内実が展開図の様に開示され、目から鱗ポイント多数。初耳の挿話も多くそちらも存分に楽しめる。最後に音楽鑑賞等に関わる数多くの注意事項が示されるが多過ぎて散漫。結局人生同様自ら対峙して、引き受けて取り込む事に収斂かな。2023/10/20
魚京童!
28
とにかく聴いて、勉強して…。2014/02/07
maito/まいと
26
「音楽の好みは感性だ。それを伝え合う努力の“洗練”を怠ってはならない」「音楽を聴くとは、未知なる他者を知ろうとする営みである」“音楽”を読書や他の趣味に置き換えられる提言が山ほど入ってる名本!元々はクラシックを理解するための、音楽と人間との関係についての歴史が多くを占めている本。その中で、今より体全体を使って音楽を聴き、理解しようとしてきた先代の行動から、僕たちは学ばないといけないのだろう。感覚が合う人だけで固まっては知る楽しさは得られない。理解しようとする、わかり合うという姿勢の尊さを改めて知る1冊だ。2020/06/30
-

- 電子書籍
- 異世界のすみっこで快適ものづくり生活3…
-
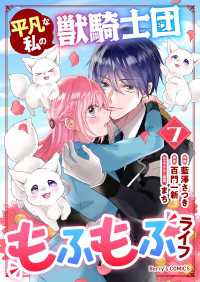
- 電子書籍
- 平凡な私の獣騎士団もふもふライフ7巻 …
-
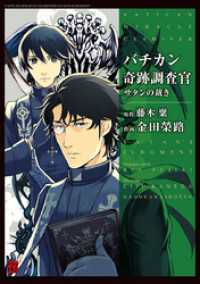
- 電子書籍
- バチカン奇跡調査官 サタンの裁き カド…
-
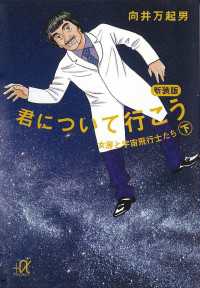
- 電子書籍
- 新装版 君について行こう(下) 女房と…
-

- 電子書籍
- 嘘と愛の間で 秘密の扉が開くとき I …




