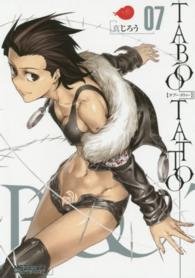- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
古代バビロニアで粘土板に二次方程式の解法が刻まれてから四千年、多くの人々の情熱と天才、努力と葛藤によって、人類は壮大な数学の世界を見出した。通約不可能性、円周率、微積分、非ユークリッド幾何、集合論-それぞれの発見やパラダイムシフトは、数学史全体の中でどのような意味を持ち、どのような発展をもたらしたのか。歴史の大きなうねりを一望しつつ、和算の成果や19世紀以降の展開についても充実させた数学史決定版。
目次
第1章 数学の芽
第2章 数学の始まり
第3章 西洋数学らしさ
第4章 古代から中世へ
第5章 カメに追いつくとき
第6章 計算する魂
第7章 曲がった彫刻
第8章 見えない対称性
第9章 形に対する悦び
第10章 感性の統合
第11章 フェルマーの最終定理
第12章 空間と構造
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
106
古代における数学の起源から始まり、現代数学史のところまでを非常にわかりやすく解説してくれています。あまり数式などを使用していない分、文章での解説が多いのでページ数も多くなっています。数学嫌いの人もこのような本から入るといいのではないでしょうか。2015/11/28
WATA
65
古代から現代までの数学の発展の歴史を、「見ること」と「計算すること」を統合しようとする創意工夫の軌跡として捉えた本。数学の発展の裏側にある思想面を重視した内容になっている。読みやすく書かれているが、内容をきちんとつかむには多少の数学知識が必要。「見ること」と「計算すること」の発展の歴史を重視したために内容は幾何学と代数学に偏っている。確率論や情報数学の話がほとんどないのはやや不満だが、新書1冊に収めるには仕方のないことかもしれない。その点以外は良くできており、数学好きなら読んで損の無い1冊だと思う。2014/09/09
翔亀
44
【真理鉱山7数学篇6】なかなか読ませる数学史。ほとんど数式を使わずに数学がどう発展してきたかを判った気にさせる手腕は大したものだと思う。古代(ユークリッド幾何学)から近代(微積分)までの数学はよく語られるが、本書は東洋数学や日本の和算が西洋に決して劣ることなく世界最高水準だったことをπの算出や行列式の水準の高さなどの例証により主張しているのが特徴の一つだろう。また、古代ギリシャ人がユークリッド幾何学のようなあれほどの論理技法を生み出したのは、「死ぬほどヒマだったから」(p77)というなど軽妙な語り口の↓2021/03/07
やまやま
16
ギリシャ的な意味での証明の特徴は、ミクロレベルでは極めて簡単な論理の流れからできているが、それ自体が鮮やかなわけではなく、議論全体から得られる印象が「見事」なのだ、という感覚でミロのビーナスを見てください、というのが本書の帰納的な紹介になるだろうか。東洋数学は「計算」に主力を置くが、これはギリシャ人が計算が得意でなかったから、という可能性について、計算より幾何だと言われれば何となくそうかな、とも思ってしまいます。最後にトポスの紹介で、現代の空間の視点では、点の概念が不可欠ではなくなったと述べる。2020/06/21
nbhd
15
後半で急激に難易度が増すのでチンプンカンプンになったけど、おおいに得るものがあった数学本。それは、そういえば人生で「無限」とか「極限」とかいうものを、抽象的に頭で掴んだのは”数学から”でなかったか、ということ。小学校で「平行線は”宇宙”まで延長しても決して交わらない」と習って、遠い宇宙に思いをはせた気がするし、当たり前だけどヒトは√2とかπとか0.333…とかで「無限」をしぜんと受容している。「アキレスと亀」的な「極限」もしかり。このバカでかい無限の世界を手中におさめようとしたのが数学なのだなと思った次第2016/01/31
-

- 電子書籍
- 同居人はケダモノでした!?(3) Bl…
-

- 電子書籍
- 10億円で夫、捨てます。第2話 Car…
-
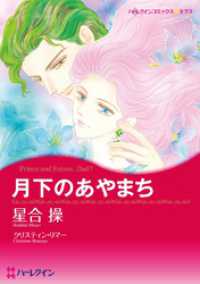
- 電子書籍
- 月下のあやまち〈バイキングの花嫁たちⅡ…
-

- 電子書籍
- 国家試験受験のためのよくわかる憲法