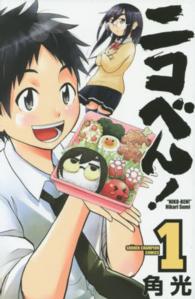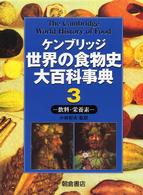内容説明
日本の近代は焼け野原となって幕を閉じた。しかし、敗戦も一つの達成であった――。第一次大戦の戦勝から大東亜戦争の敗戦までの約三十年間、日本は何を成し遂げたのか。五大国として列強と肩を並べた日本は、帝国主義の終焉と相次ぐ大不況に方向性を見失う。国家が迷走するなか、主導権を握った軍部は、次第に最強国アメリカとの対立を深めていく。たった二冊で黒船から敗戦までの九十年がわかる特別講義の完結編。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スシローよりはま寿司が好きな寺
42
福田和也の日本近代史下巻。関東大震災から敗戦まで。日本近代史お馴染みの、あれよあれよと悲惨になる展開だが仕方ない。海軍善玉論は無く、陸軍を昭和のデモクラシーを担った政治集団だと説く。言われるとそんな気もする。史上評判の良い米内光政を「最大の戦犯として糾弾されるべき人物」山本五十六を「(勤務経験が長かった米国の事を)実際は全く理解していなかった」「無責任」と評する。人物評がチラッと出る瞬間がやはり面白い。著者が不意に立ち上がるのだ。あとがき『「敗戦」は悪くない結末だった』はちょっと感動的である。2015/10/29
fseigojp
15
日比谷焼き討ちは徴兵され死んだものたちの抗議であり、第一次大戦で総力戦が必至となり普通選挙制が実施された 統制派軍部・革新官僚・重工業産業界の独走が満州国建国へ。。。アメリカの機嫌を取る気が全然ないのが魔訶不思議。。。。そのあたりはドイツも一緒なんだが2015/08/01
小鈴
10
新書二冊にして日本近代史の完成度が高い良書。あとがきの202ページ以降の著者のメッセージは、これを書くために近代史をまとめたとさえいえ、胸に響く。「大正期に生きる意味や人生の理想を求めた世代が〜国体の明徴を求め〜精神主義的、理想主義的な方向に引っ張っていってしまう。〜天皇機関説批判とは、すぐれて昭和的なデモクラシーに他ならなかった」「自分らしさという発想は、実は国体とたいして変わらないのではないかと危惧しています。それは、日本人が現実感覚を失っていく兆候に他ならないから。」歴史の教訓を生かしたい。2009/07/12
inokori
7
新書2冊で日本の近代史を概観できるという点ではなかなかお得.特に上巻は,歴史学者の新しい研究成果からの引用も多く,手堅い感を受ける.はっきり言ってしまえば,上巻は加藤陽子氏の著作を中心に手を広げていくことでもっと深い理解が得られるかもしれない.一方,日露戦争後から大東亜戦争を扱う下巻は,これまでリベラルと評されてきた海軍提督陣(米内光政や山本五十六等)への世評への懐疑が呈せられているのが類書と違うかも.著者に期待されそうな思想史的要素に禁欲的なのが,歴史書として成功した要因かも.2010/09/12
新父帰る
6
2009年6月刊。上巻に続いて下巻も面白かった。明治維新以降、5大国の仲間入りを果たしは日本は近代を歩み始めた。日清・日露戦争後、第一次大戦を経て、日本に総力戦への構えがないことに築く。満州事変から盧溝橋事件で日中戦争に突入して、終着点の見えない戦争が続くが、太平洋戦争も真珠湾攻撃以降の戦略が見えず、陸軍海軍もバラバラ、戦争指導者も終着点を描けず、天皇の聖断で終戦を迎えた。著者は山本五十六の無責任を厳しく指摘。逆説的に日本は敗戦して良かったと言っている。戦後復興は戦時中の技術の研鑽が大いに役立ったと言う。2025/08/11
-
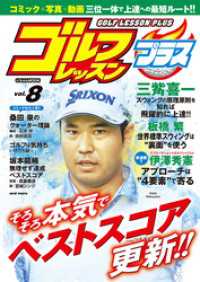
- 電子書籍
- ゴルフレッスンプラス vol.8
-
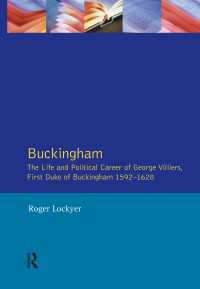
- 洋書電子書籍
- Buckingham : The Li…