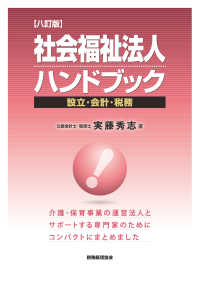- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
時間を、時計のような区切られた点の集まりではなく意識の内的持続の中に見る。19世紀実証主義哲学を批判し、人間の意識と科学の因果律の違いを説いた、ノーベル賞哲学者の代表作。(原題「意識に直接与えられているものについての試論」)
目次
第1章 心理的諸状態の強さについて(強さをもつものと外延的なもの 深い感情 ほか)
第2章 意識の諸状態の多数性について―持続の観念(数的多数性と空間 空間と等質性 ほか)
第3章 意識の諸状態の有機化について―自由(物理的決定論 心理的決定論 ほか)
結論(常識へ戻ること カントのあやまり)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
9
時間を外側から眺めようとすると空間と混同され、質的なものが「距離」や「長さ」と言った量的なものに移し替えられ、「自由」なき決定論が生まれる。しかし、時間とは量的「延長」ではなく、あらゆる要素の溶け合った「持続」であるとベルクソンは訴える。おそらくライプニッツやカントを念頭においた、哲学批判の哲学書。咀嚼できてない部分多数だが、この具体的な抽象性に漱石が「美しい」と言ったのも頷ける。中原中也と自身の経験を繋げて「言葉への疑い」を抽出する加藤典洋の解説が巧い。ポールとピエール、『ファイトクラブ』かと思った。2021/02/27
SQT
5
延長を持つもの(空間で捉えられるもの)=量=社会的な自我↔︎延長を持たないもの=質=深い自我、的な話。これを混同してしまうことが決定論を許している、と。というのは行為を原因→結果のような線で表すことが、延長を持たない(分割を許さない)、2度と同じようには反復され得ない行為を、空間を使って捉えてしまうことになっているから。人間の行為は決してこのような形では捉えられないと。ただ言語とか、意味を局在化してしまうようなものに囲まれているわれわれはそこから離れるのは難しいよね…と。まぁまぁ難しかった。2017/01/07
Bevel
4
難しかった。「還元不可能な質を量で説明するのはよくない」という批判を超えて、「なぜ実際に、質を量で説明してしまうのか、その可能性の条件は何か」つまり、「量と質はどこで関係するのか」という問いが重要だと思う。ただ、相変わらずそれがどこなのかうまく想像できなかった。外的原因は線を構成し、線と内的原因のペアは内包量という第三の対象を構成しうる。外的原因の一部にだけ成り立つ、稠密性について気になった。2012/11/13
菜桜
1
昔読んだけど、若かったのであまり、、、というか、ほとんど意味を理解出来ず(;^∀^) もう一度読み返してみたいなぁ。
rymuka
1
楽譜全般にそうなのですが,特に北欧の作曲家の楽譜を眺めると,ベルクソンの時間論を思い出します。>> http://rymuka.blog136.fc2.com/blog-entry-14.html >> http://rymuka.blog136.fc2.com/blog-entry-54.html2015/11/21
-
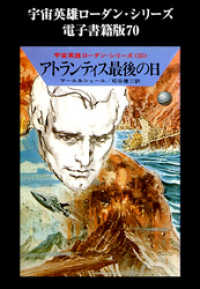
- 電子書籍
- 宇宙英雄ローダン・シリーズ 電子書籍版…
-
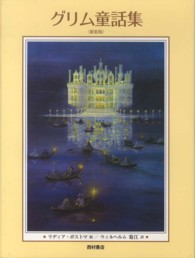
- 和書
- グリム童話集 (新装版)