内容説明
師千利休は何故太閤様より死を賜り、一言の申し開きもせず従容と死に赴いたのか? 弟子の本覚坊は、師の縁の人々を尋ね語らい、又冷え枯れた磧の道を行く師に夢の中でまみえる。本覚坊の手記の形で利休自刃の謎に迫り、狭い茶室で命を突きつけあう乱世の侘茶に、死をも貫徹する芸術精神を描く。文化勲章はじめ現世の名誉を得た晩年にあって、なお已み難い作家精神の耀きを示した名作。日本文学大賞受賞作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
199
著者74才の作。本覚坊の手記の一片一片が血の通った師利休の姿と周りの群像を形作る。特に印象的なのは、かつて本覚坊が、師と兄弟子らしき人の対座する茶席の隣室に控えていた折に、「〝無〟では何もなくならないが〝死〟ではなくなる」という声を聞いた話だ。本覚坊の目には、〝死〟の軸を掛けた二畳の暗がりにいる兄弟子が、《火炎に上半身を照らし出されている他面多臂の明王のように見えた》と。ここでの〝死〟は、〝無〟の静寂を突き抜ける〝生〟の反語ではないか。〝死〟に面した茶室で〝生〟の意味を問うことこそ、作品の意図でもあろう。2024/04/21
優希
112
単行本で読みましたが、こちらで登録。利休の晩年の孤独な精神が伝わってくるようでした。利休は何故死ぬべきであったのかということを考えさせられます。不特定の人物と本覚坊の語りの入れ子構造で利休の身近な人物の証言や記述物から語られることで死にゆく利休の心理や覚悟が伝わってくるようでした。何故利休は死ななければならなかったのかという史実に迫っているわけではありませんが、その死への想いが目に見えるようです。2017/01/14
NY
18
秀吉が千利休に自死を命じた理由は早くから具体的に推測されてきた一方、なぜ利休が命を静かに受け入れたのか、なぜ詫びなかったのか、人々は理解に苦しみ長いこと煩悶してきたようだ。その謎に対する「井上流」の答えが、秀吉と利休の魂が対面する最後の場面で明かされる。秀吉の庇護を受ければ受けるほど、自己を損なってきた利休。生殺与奪を一手に握る権力者から死を賜ることは、自己を取り戻すためには避けられない運命だったのだ。利休の畳み掛けるような決別の言葉にただうろたえる秀吉。男女の別れのようでもあり、妙に腑に落ちた。2019/02/09
Takashi Takeuchi
17
利休の弟子である本覚坊が古田織部、織田有楽斎、東陽坊、江雪斎など師と所縁ある人々と語らうことで利休の死の真相、利休の茶の真髄に迫ろうとするが、全ては靄の中、結局答えは明かされないまま。その答えは読者に委ねられる。本覚坊の手記形式をとることで、静謐ながらも亡き師への想いの深さが伝わってくる。随分昔に観た熊井啓による映画化作品『千利休 本覚坊遺文』もこの小説の持つ雰囲気を上手く映像化した佳作だった。2022/12/16
PAO
14
「“無”ではなくならん。“死”ではなくなる」…『利休にたずねよ』を読んだので私の利休観を決定づけた本書を再読しました。本書の密度と重量感は他と比べようもなく井上靖の描く現と幻、枯淡と豊潤という矛盾が醸し出す虚構に昔読んだ時よりも更に翻弄され、ずっと首筋に冷たい刃を当てられる様な稀有な読書体験を味わえたことに感謝します。聖とか俗とかいう些細な分別を遥かに置き去りにして“無”を凌駕する“死”に向き合って殉じた利休、宗二、織部といった茶人たちの姿を描くことで作者自身の死への覚悟を示すまさに「遺文」たる作品です。2025/07/26
-
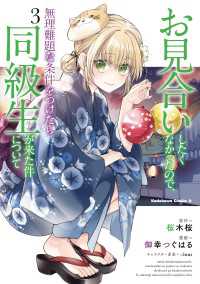
- 電子書籍
- お見合いしたくなかったので、無理難題な…
-
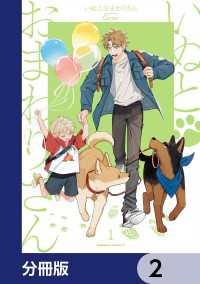
- 電子書籍
- いぬとおまわりさん【分冊版】 2 角川…
-

- 電子書籍
- 生贄姫の毒は勇者の愛に溶かされて 5話…
-

- 電子書籍
- 弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭…
-

- 電子書籍
- 少女は復讐のために【タテヨミ】第59話…




