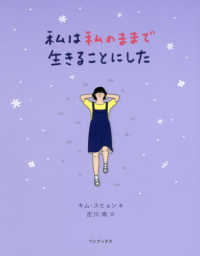- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(健康/ダイエット)
内容説明
本書は、世界のソニーを育てた伝説の経営者が、精魂込めて語った新時代の子育て論。
1971年に刊行されて以来、多くのお父さんお母さんに読み継がれてきました。
「幼児は叱るよりほめたほうがよい」
「体を動かす子ほど知能の発達も早くなる」
「整理されすぎた部屋は子どもの成長を妨げる」
など、長年の幼児教育研究で報告された興味深いエピソードと、
それをもとに行われる提言は、うなずけるものがいっぱいです。
これから子育てをはじめる方々に、ぜひ読んでいただければと思います。
※本書は1999年に小社より刊行された同名の文庫を、新装版として出版するものです。
【目次より】
○幼児教育は天才をつくるためのものではない
○抱き癖は、おおいにつけるべきである
○お金や暇がなくても子どもの教育はできる
○人を信じられる人間が21世紀の日本をつくる
目次
1章 幼児の可能性は三歳までに決まってしまう(幼稚園に入ってからでは、もう遅い どの子も〇歳からの育て方ひとつで能力を伸ばしていける 幼児教育は天才をつくるためのものではない ほか)
2章 幼児の能力を最大限に伸ばす育て方・環境づくり(幼児の能力は遺伝よりも教育・環境が優先する 学者の子だから学者に適しているとはかぎらない 人間の赤ん坊でも獣の中で育てば獣になる ほか)
3章 ほんとうの幼児教育は母親にしかできない(ビジョンをもたない母親に子どもの教育はできない 女性にとって育児ほどたいせつな仕事はない 幼児教育は母親教育から始まる ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kaelu Haruki
12
「0歳~3歳までの間に脳の重量は大人の80%にまで成長し、脳の配線の大部分が形成される。この期間に多くの刺激を与えて、脳のハードウェア(情報処理能力)の性能を良くしなければならない。」大いに子育ての参考にしている書。3度目くらいの再読。僕も胎教から絵本の読み聞かせなど子供に関わるようにしてきたが、サボらないようにもう一度気合を入れ直そうと思う。2015/05/15
Eriko M
9
出産を間近に控え、育児の予習として。20年前に刊行された物の新装版。時代の違いを感じるのは今より女性の社会進出が一般的ではなかったため、育児や教育は母親の仕事、女性の一番の仕事は出産して子供を立派に育てること!と主張している点。 それ以外は今でも新鮮だし、有効でありそう。 とりあえず押し付けではなく、いろいろ経験させてあげたいな。出産前に読んでいてよかったです。 ★★★★★2020/01/28
isao_key
7
盛田昭夫と共に、ソニーを創業した井深大は、技術者、経営者の面だけではなく、早くから幼児教育やボーイスカウト、障がい者自立支援など社会貢献事業に尽力されていた。とりわけ幼児教育についての関心が強く、本書は1971年に出版されている。井深の元となる考え方には、スズキメソードを開発した鈴木鎮一先生の思いが深く影響している。それは、才能は生まれつきのものではなく、どの子どもでも育て方によって同じように伸びる可能性があり、より早い時期に教えることが大切だということ。古い本ではあるが、基本的な内容は現在でも通じる。2017/09/15
小鈴
7
1971年発行の新装版。ソニー創業者である著者が幼児教育の必要性を説いたこの本はベストセラーになった。当時において、赤ちゃんは言葉も理屈も通用しないと見られていたが、三才までの積極的な働きかけがその後の能力や才能に大きな影響を与える、という。もちろんここで言われている教育は受験のための能力開発などではない。今読むとたいして目新しさを感じないが、今に至る育児の本やネットの情報(特に赤ちゃんの能力開発)はこれを孫引きしてるんだろうなぁと思った。2013/08/14
Nanami
6
1970年発行。ソニー創始者による育児本、という珍しさにひかれて。3歳までに脳の80%が作られる、三つ子の魂百まで、というのは現在ではよくきくけれど、当時はきっと画期的だったのだろうなと思う。早期教育は天才を作る為ではない。3歳までに脳のつながりをたくさん育て、ハードとなる部分をしっかり作ること。3歳以降はソフトとなる部分を育て、広がるように。これといって目新しいことはなかったけれど(40年前だし当たり前といえば当たり前)折に触れて読み返してみようと思う。2016/10/30