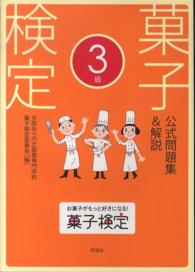内容説明
「蛍の光」「「埴生の宿」から見える明治史。明治という近代化の時代、西洋を受容しあらたな「日本」を模索するなかで、なぜ「歌」が必要だったのか。日本語の「文法」と「唱歌」をめぐる知られざる歴史。(講談社選書メチエ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
7
日本における音楽教育のさきがけ、井沢修二が吃音矯正も手がけていたという事実の提示が、本書の主題を予告している。すなわち、唱歌と国文法という明治期に確立された形式が、国家体制の浸透させるための規律の装置であったということ。唱歌にも国語にも、「体に記憶させる」という機能が強調されてたということ。国文法の覚え方を延々と歌に乗せた唱歌が存在したように、両者は交差している。この交差は、今の(国家から離れたように見える)文学や音楽にどのように作用しているか。そのあたりのことに関心がある。2021/12/03
hika
2
日常的な「言葉」を「国語」にしていくといくことの日本的実践の一幕。文法の確立との関連そして、国学者と近大の教育という観点からも興味深いところが多々。2015/08/13
またゆき
2
明治の国語教育には文法が必要であり、暗記装置としての唱歌もまた国語教育に必要であったって話。 文法唱歌や堺水道唱歌なんてすごい唱歌の話や、明治には「いろは歌」ではなく、文法的な「あいうえお」が求められていたって話が印象的2012/07/31
ほたぴょん
1
言われないと気づかないもので、明治時代に学校教育というものができ、そこで西洋に倣って音楽を教えることになるまで、日本では音楽教育というものはほぼ存在しなかった。そのことを教えられた。そうして生まれた唱歌が、一面では道徳、文法教育の側面を持たされたというのは、現代の国語教育はその一面、道徳教育に堕しているという石原千秋先生の指摘を思い起こさせて興味深い。「昨日の敵は今日の友」という言い回しは、佐佐木信綱が作詞した「水師堂の会見」という唱歌が初出。乃木希典とステッセルの旅順の会見を歌ったものだとか。以上備忘。2022/05/12
かもはし
1
五線譜に描いた夢展でちょっと興味がわいて読んでみた2013/12/04