- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
発達障害にまつわる誤解と偏見を解く! 言葉が幼い、落ち着きがない、授業についていけない。そだちの遅れがみられる子のなかで、治療や養護が必要かどうかを、どう見分けるか。ケーススタディをもとに第一人者が教える。
目次
第1章 発達障害は治るのか
第2章 「生まれつき」か「環境」か
第3章 精神遅滞と境界知能
第4章 自閉症という文化
第5章 アスペルガー問題
第6章 ADHDと学習障害
第7章 子ども虐待という発達障害
第8章 発達障害の早期療育
第9章 どのクラスで学ぶか―特別支援教育を考える
第10章 薬は必要か
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てち
71
発達障害について個々の事例や、主な症状について詳しく書かれている。読んでみると意外と誤解していた点があり、ためになった。2020/05/05
tamami
48
刊行当初(2007年)に一度目を通した記録はあるのだが、記憶はない。というわけで積読本を再読。現在も多くの支持があるらしく、版を重ねている。筆者のような門外漢にとっても、発達障害に関する大変バランスの取れた参考書ではないかと思う。本書には、著者が関わった子どもに関する幾つもの事例が記されているが、そのどれもが、一時的な診断の記録ではなく、対象の子どもに関わって以来、何年もの時によると何十年もの記録の積み重ねを経ての記述となっている。これってすごいことだと思う。書棚に杉山本がもう一冊みつかった。次はそれだ。2022/03/29
ころりんぱ
47
発達障害という言葉も昔に比べたら認知度も高まり、学校などの対応も良くなって来たんじゃないかと思っていたけれど、現実はどうなのかな?と。学校だと極端に学習障害が認められない場合、通常クラスでとなっている現状。内容のほとんどわからない授業に50分×5時間とか座ってなければいけないのは、自分が全くわからない言語で行われている会議に出て同じだけ座って聞いてなきゃいけないという場合を考えてみて欲しいと書いてあって、そりゃキツイよと思った。子どもの状態に合わせた支援体制が整うことを願う。2014/05/17
ゆう。
38
臨床現場で長く発達障害の子どもたちを見てきた著者が、発達障害に対する誤解や偏見を示し、どのように支援していくことが大切なのかを述べた内容です。帯には「治る子と治らない子」とありましたが、著者は「治る」という概念で発達障害を捉えていないと思いました。発達障害に対する正しい知識のもとに子どもの実態や思いにしっかりと応えた介入をすることの大切さを述べていると思います。それが十分になされない場合に社会への適応障害が生じてくるということなのだと思いました。学ぶことの多い一冊でした。2018/08/31
きいろ
31
早期発見、療育の重要性がよくわかる。自閉症スペクトラムについて、ある講演会で 紺色に近い深い青から青 水色 透明に近い青まで連続した色に例えて説明があって、健常でも自閉症的特徴を持った人は多いのね。と感じたのだけれど(個人個人のこだわりどころとか)逆に考えれば、発達障碍を持っていても個人の一個性として社会が受け入れることさえできれば当事者の生き辛さは軽減されるのではないかな。受け入れる側の知識不足で差別されたり、不当な叱られ体験を重ねて二次障碍に陥る人が減りますように。2016/06/05
-

- 電子書籍
- 宮廷をクビになった植物魔導師はスローラ…
-
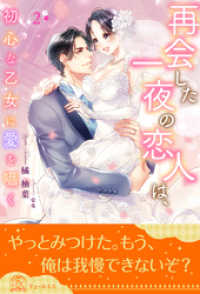
- 電子書籍
- 再会した一夜の恋人は、初心な乙女に愛を…
-
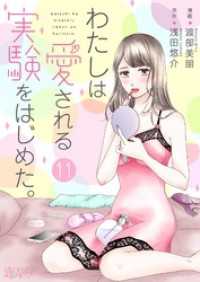
- 電子書籍
- わたしは愛される実験をはじめた。 11…
-
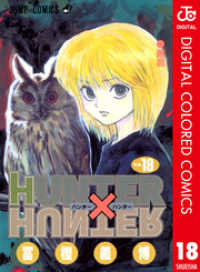
- 電子書籍
- HUNTER×HUNTER カラー版 …





