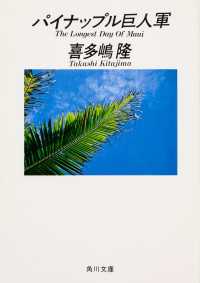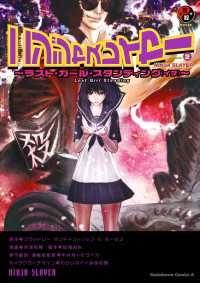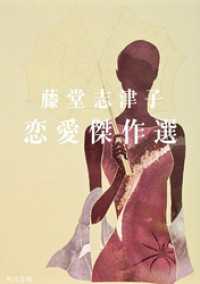内容説明
「ひきこもり」研究の第一人者である著者が、ラカン、コフート、クライン、ビオンの精神分析理論をわかりやすく紹介し、ひきこもる人の精神病理を読み解くとともに、家族の具体的な対応法について解説。ひきこもりとニートの違いなど、「ひきこもり」の現在が解き明かされる。 ――以下、本文“はじめに”より『なぜ「治る」のか?』という、ちょっと奇妙なタイトルには、いろいろな意味が込められています、その一つは、「必ずしも病気とはいえないひきこもりを治療するとはどういうことか?」という問いかけです。そう、ひきこもりは、それだけでは病気ではありません。だからこそ、社会参加に際しては、さまざまな支援や対策が有効であり得ます。しかし、ひきこもりは治療によって「治る」こともある。ならばその過程は、精神医学的に、というよりは精神分析的に、どう理解することができるのか。…」
目次
第1章 「ひきこもり」の考え方―対人関係があればニート、なければひきこもり
第2章 ラカンとひきこもり―なぜ他者とのかかわりが必要なのか
第3章 コフート理論とひきこもり―人間は一生をかけて成熟する
第4章 クライン、ビオンとひきこもり―攻撃すると攻撃が、良い対応をすると良い反応が返ってくる
第5章 家族の対応方針―安心してひきこもれる環境を作ることから
第6章 ひきこもりの個人精神療法―「治る」ということは、「自由」になるということ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
袖崎いたる
15
著者の依拠する人として中井久夫とラカンとは知っていたけれど神田橋條治も押えられていたとは知らなかった。齋藤環という人はひきこもりにホームベースとしての家を整備してあげようと頑張っている。ともすると怠慢なアウトローとして認知されがちなひきこもりという存在に臨床の経験と分析家としての洞察から、彼らを一個の人間として理解するためのセーフティネット的なフレームの構築を試みる。ぼくとしてはラカンとコフートの繋ぎが勉強になった。それと名前は出してないけど内海聡的な反投薬への批判もあった。シラケの重要性は肝に銘じたい。2017/03/27
ひろか
6
Kindleにて読了。ラカン、コフート、クライン、ビオンといった精神分析家の理論を援用しながら、ひきこもりの心理の解明していく。2014/07/06
花梅
5
作中に紹介されている精神分析の理論をちゃんと理解できたわけではないが、ひきこもりに向き合う著者の淡々とした姿勢には好感を持った。人の心なんて、正論とか善悪なんてフィルターを通して見たのでは、理解なんて全然出来ないと思う。既存の価値観をとりあえず横に置いておいて問題と向き合わないと、そもそも相手に心を開いてもらうことすら難しい。2017/04/20
Yukicks
5
心を病む原因は他者だが、その心を回復するのに必要なのも他者だということ。2012/03/08
マユ~。
4
現場の治療者がどんなことを考えているのか?が良く解った。2016/09/08