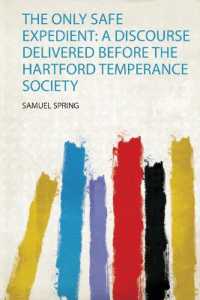- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「とにもかくにも人は、もののあはれを知る、これ肝要なり……」。本居宣長七十二年の生涯は、終始、古典文学味読のうちに、波瀾万丈の思想劇となって完結した。伊勢松坂に温和な常識人として身を処し、古典作者との対話に人生の意味と道の学問を究めた宣長の人と思想は、時代をこえてわれわれを深い感動の世界につつみこむ。著者がその晩年、全精力を傾注して書きついだ畢生の大業。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
65
2014.01.14(01/01)(つづき)小林秀雄著。 01/14 (p082) 中江が生まれたのは秀吉の死後10年である。 藤樹は近江の貧農の家に生まれ、独学し、独創し、ついに一村民として終わりながら、誰もが是認する近江聖人としての実名を得た。 これは学問の世界にあっては、前代未聞の話であった。 秀吉は、手紙に、「てんか」と署名した。 2014/01/14
i-miya
56
2014.03.01(02/01)(つづき)小林秀雄著。 02/28 (P083) 藤樹の父。 年譜、六年、先生=十三歳。 「この年、夏、五月、大いに雨が降り、五穀は実らない。百姓は、飢饉に及ばんとす。これより風早(=飛び地、大洲藩、吉長は奉行)は、この地を去ろうとする住民、多かった。 2014/03/01
i-miya
41
2013.06.28(つづき)小林秀雄著。 2013.06.27 七. 上田秋成が契沖晩年の地、円珠庵を訪れた。 契沖の一遺文を写した。 「せうとなるものの、みまかるけるに」とあり、兄、如水の挽歌から始まっている。 そのうち、の一首に、「いまさらに、すみぞめ衣、袖ぬれて、うき世の事に、なかむとやする」ともう一首、「ともし火の、のちのほのおを、わが身にて、消ゆとも人を、いまでか見む」 元禄十一年、契沖の死の三年前のこと。 兄所水は、晩年の法号。 2013/06/28
i-miya
40
2013.12.01(12/01)(つづき)小林秀雄著。 11/29 (p080) 戦国時代のこの下剋上、という言葉。 下の者が、上の者に克つ。 この簡明な言い方がその内容を隠す嫌いがある。 『大言海』に、「此の語、でもくらしいトデモ解スベシ」とある。 乱暴な解だととる向きも多かろう。 「戦国」とか、「下剋上」とか、いう言葉、否定的に響く字面の裏には健全な意味があるのだ。 歴史の上で、実名が虚名を制すという動き、これはきわめて自然なことである。 2013/12/01
i-miya
39
2013.03.23(つづき)小林秀雄著。 2013.03.23 七. 上田秋成-契沖が隠棲した円珠庵を訪う。 契沖の一遺文を写す。 「せうとなるものの みまかりけるに」 兄、如水の挽歌である。 「いまさらに 墨染めごろも 袖ぬれて うき世の事も なかむとやする」 もう一つ、「ともし火の のちのほのほを 我が身にて きゆとも人を いつまでか見む」 元禄十一年、契沖が死ぬ三年前。 「如水」は晩年の称号。 播州松平家に仕官する下川瀬兵衛元氏という下級武士。 2013/03/23