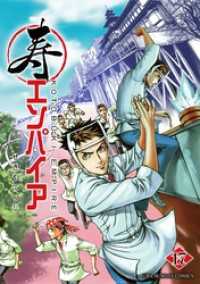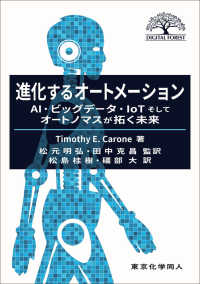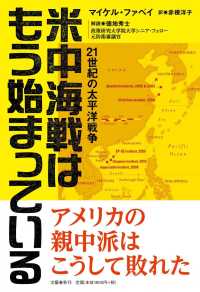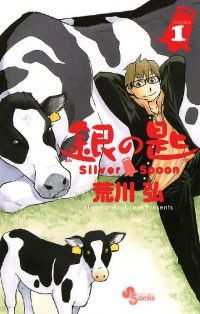内容説明
ほんとうに、日本語はそんなにむつかしいのでしょうか。乱れているのでしょうか。そうだとすれば、そのむつかしい日本語を正しく、巧みに使いこなすにはどうすればいいのか。かつては「豊葦原瑞穂国(とよあしはらみずほのくに)」であり、今や世界に冠たる「グルメ大国」であるこの国にふさわしく、「食」の言葉のあれこれから日本語を考えてみたいと思います。
目次
まえがき
第一章 「米」をめぐる言葉の不思議
「ご飯」と「ライス」はどう違う?
海産物がなくても「山海の珍味」
パン食なのに朝飯と言うわけは?
山盛りご飯の由緒
「ご馳走」とは駆けまわること
死語になった「紅箸」
「箸と茶碗」より大切なもの
ご飯を入れるのに、なぜ茶碗?
第二章 日本語は世界の変わり者
言葉の婦人専用車
「女房詞」と「文字言葉」
男は「食う」女は「食べる」
「食べる」の意外な語源
緑色の蚕豆がなぜ「青物」?
ブラックティーが「紅茶」のわけ
難波の葦は伊勢の浜荻
チンチンとは黒鯛のこと
方言
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いずみ
0
背表紙の目次にはうなぎ文やらら抜き言葉やら書いてあったけど、それらについてを延々語るわけではなく、その辺の説明はあくまでさらっと分かりやすく。それよりも食べ物にまつわる色々な語・慣用句等の話が多めで読みやすい。2010/08/06
志村真幸
0
著者は新聞記者からエッセイやテレビ業界で活躍した人物。 本書は、食べること/食べものにまつわる日本語を、いろいろな角度から見直してみようとしたもの。川魚は「山海の珍味」にふくめていいのか、「ら抜き言葉」がいつからあるのか、みずみずしい野菜を「青物」と呼ぶ理由、食べものの登場する諺などなど。 軽く読めて勉強になる一冊だ。 ただし、裏取りは甘くて、憶測も多く、完全に信用すると危ないかも。また、ひとりよがりな箇所が目に付く。もう80歳を過ぎての著作というから、仕方ないか……。 2023/08/25