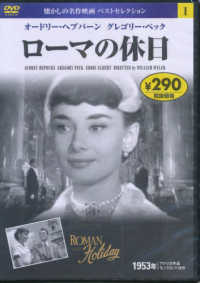- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
人は合理的である、とする伝統経済学の理論は本当か。現実の人の行動はもっと複雑ではないか。重要な提言と詳細な検証により新たな領域を築く行動経済学を、基礎から解説する。
目次
第1章 経済学と心理学の復縁―行動経済学の誕生
第2章 人は限定合理的に行動する―合理的決定の難しさ
第3章 ヒューリスティクスとバイアス―「直感」のはたらき
第4章 プロスペクト理論(1)理論―リスクのもとでの判断
第5章 プロスペクト理論(2)応用―「持っているもの」へのこだわり
第6章 フレーミング効果と選好の形成―選好はうつろいやすい
第7章 近視眼的な心―時間選好
第8章 他者を顧みる心―社会的選好
第9章 理性と感情のダンス―行動経済学最前線
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
108
10年以上の前の本ですがこの本は行動経済学とは何たるものかをわかりやすくまたよく分析されています。先日読んだ「やさしい経済学」版のさまざま学者が書かれたものよりもはるかにいい本です。この分野の経済学は非常に範囲が広くて意思決定論や交渉学、あるいは経済心理学などの分野までが入るのではないかと思われます。とくに6章の「フレーミング効果と選好の形成」は私にとっては啓発されるものでした。2018/02/17
きいち
37
経済は感情で動いているけど、動かしている人は決して非合理ではない。情報収集や比較衡量にも工数がかかるのだから、むしろとりあえず目の子算してそこから修整していく方が行動する者としては合理的。だから感情経済学じゃなく「行動経済学」なんだな。◇かなり広い範囲を丁寧に抑える理想的な教科書。ここから掘っていける。◇特に今興味を持ったのは「(一般的)信頼」との関係。これも有効なヒューリスティックの一つ。バイアスもあるし。◇経済人的合理性は一つだけど、行動経済学の合理性にはいくつものレイヤーがある。商売人向きで面白い。2018/09/02
さばずし2487398
36
入門として読んだが途中かなり読み飛ばし(汗)感情によって、その時と場合の余りに多くのパターンで人間がいかに合理的に判断してないか、という事はよく分かった。 理論的に考えれば別の答えに行く筈が、置かれた状況や先入観などによってそうなってないというヒューリズム。これは昨今のコロナやその後の対処一つを見ても正に当てはまる事で、 他国の状況や数字、選択のリスクを理屈的に考えればおかしいと思う事も不必要に煽られた瞬間から不安と思考停止に陥り同調圧力という集団心理を生み出す。今こそこういう学問は重要なのでは。2022/11/13
加納恭史
32
軽く行動経済学の外観を復習出来そうと思ったが、なかなか深い最近の動向もあり、驚く。ダニエル・カーネマンの行動経済学を復習出来るのだが、認知心理学と経済学の繋がりの背景まで語られているのに感動した。アダム・スミスやケインズも頻繁に出て来るし、カーネマンとセイラーを並記して行動経済学を語るとは、著者の洞察力は相当なものだ。感情を行動経済学に取り込んでいることも凄い。この本は2006年発行だが、十分2020年以降でも手引きとして通用する。これで他の文献も十分に再検討でき、内容は「愛と怒りの行動経済学」と同様。2022/03/07
Thinking_sketch_book
32
★★★★☆ 利益のためなら友人を裏切れないように、人は利益を追求するために完全に合理的な決断をし、行動するのではない。決断する上では感情や環境も影響する。会社のシステムやプロジェクトでも同じことが言える。新しいシステムを検討すると、どうしても完全に合理的な方法を選択しがちだが、それでは上手くいかない。それは感情がともなわないからだと思う。一方で感情が伴っているシステムやプロジェクトは上手くいく。行動経済学をもう少し深く読んでみたいと思う。2014/08/09