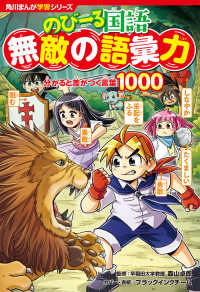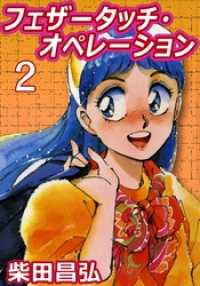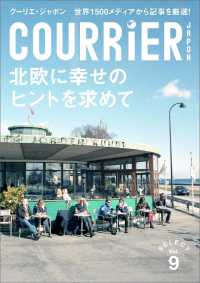- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
過去の暗闇に隠れている出来事を発掘しその意味を考えることから歴史探究は始まる。本書は、岩船地蔵と刻まれた一体のお地蔵様の発見から始まる、歴史探索のプロセスを開示したものである。関東甲信・静岡の各地に散らばる地蔵を捜索し、関連の文字資料を発掘する過程で、江戸中期の享保四年(一七一九年)に、下野国の岩舟を出発点にして地蔵が村から村へ送られ、地蔵が通った各地の村に「岩船地蔵」が建立されたことが明らかになる。なぜこのような流行仏が出現したのか。何気ない路傍の地蔵から、歴史と民俗の織り成す豊かな水脈へと読者をいざなう
目次
1章 岩船地蔵の発見
2章 流行神仏と江戸時代
3章 文字の中に探る
4章 岩船地蔵を追う
5章 下野国岩船地蔵
6章 関東の岩船地蔵
7章 信州から甲州、そして駿河へ
8章 非難される地蔵・取り締まられる地蔵
9章 流行神仏の時代
10章 その後の岩船地蔵
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バニラ風味
22
道端にある地蔵によだれかけがかかっていたり、近くに千羽鶴が吊ってあったりするのを見て、地蔵は子育てや、水子供養のものが多いのだろうと思ってました。この本では、著者が岩船地蔵を見つけたことから始まり。岩船地蔵とは何なのか、いつ頃建立されたのか、その目的や、信仰の一つとしての広がりを追いながら、その時代の背景などを調査した結果をまとめています。天候不順などや災害があった時、神に祈ったり、拝んだことがあったように、地蔵を奉り、崇める宗教も多々あったよう。この記録は、過去の歴史の一部分であっても、大きな遺産です。2016/09/25
takeapple
12
民俗学者福田アジオが、文献史学と民俗学の手法で、享保4年に西関東で流行し、村送りされていった岩舟地蔵の謎を解こうとした本。この手法を使えば、アマチュアでも筋が通った新しい歴史に迫れる。内容も方法も素晴らしい。文献史学と民俗学の描く歴史像が一致するのではなく、文献史学が享保4年という点に迫るもので、民俗学が、その後の長い時間に迫るものということも明らかだ。2019/05/25
silk
3
関東に多くある岩船地蔵とは何か。実際の地蔵や文献史料を検討して、これまで知られていなかった岩船地蔵を歴史の中に位置づける。船の向きによる分類、そしてその分布・刻まれた日付に基づく伝播ルートの想定というのは、日付はないが考古学でも行われている手法だ。これから各地の石仏を見るのが楽しくなった一冊。2014/03/22
邑尾端子
2
「歴史探索の手法」というタイトルだけ見ると、調査研究とはこうあるべき!みたいな方法論を述べた内容を想像してしまいますが、本書は全くそういったものではなく、筆者の岩船地蔵との出会い(研究対象の発見)から調査、考察とそして本書の執筆に至るまでの一連の流れを淡々と述べた「実践記録」のような内容になっています。教科書を読むような堅苦しさはなく、筆者と一緒に謎解きしていくような感覚で歴史探索の流れをつかむことができ、個人的にはとても読みやすかったです。2012/05/19
Kazuhisa Hirao
2
享保4年から5年に掛けて関東西部一帯に熱狂的に流行った岩船地蔵についての探索結果を淡々と書いているだけの本ではあるのですが、書題にあるよう、岩船地蔵の研究成果を通じて歴史探索の手法について実践的に語っている(といって教科書的で無いのがよい)曰く継続は力、曰く研究は一人ではできない。2012/01/11