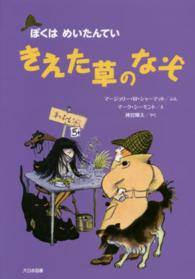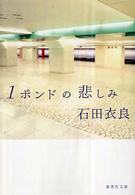- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
ずんずん調査のホリイ博士が80年代と対峙。クリスマス・ファシズムの勃興、回転ベッドの衰退、浮遊する月9ドラマ、宮崎勤事件、バブル絶頂期の「一杯のかけそば」騒動……あの時なにが葬られたのか? (講談社現代新書)
目次
第1章 1989年の一杯のかけそば
第2章 1983年のクリスマス
第3章 1987年のディズニーランド
第4章 1989年のサブカルチャー
第5章 1991年のラブストーリー
第6章 1999年のノストラダムス
終章 2010年の大いなる黄昏あるいは2015年の倭国の大乱
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
156
リアルタイムで過ごしたわけではないが80年代、70年代、90年代の世相をうまく言い表してるように思う。 しかし総じて昔は今から見るとのどかなイメージ。2025/03/24
ホークス
40
1980〜90年代に若者がエネルギーを失っていく過程、その環境的要因を主にサブカル方面から振り返った本。著者が自分の3歳上、しかも冴えない男の子目線なので、問題意識より懐かしさが先に立った。文章も軽くて分かりやすい。70年代はすぐそこに貧乏があり、80年代は貧乏人が「余裕ある生活」を体験しようとがむしゃらに努力した時代。生活が向上すると向上分はどんどん産業化されていく。それは当然の成り行きだが、後戻りできないのも事実。当時の自分は、パワハラ社会を生き延びるのに必死で楽しくはなかった。パワハラ社会は今も同じ2018/12/13
やすらぎ
33
感想を書かずに手放すことにしました✨2020/09/06
confusion_regret_temptation
29
2006年の書。スマホ前であり、習近平前の時代に書かれた本。とは言え、それ以前の時代を振り返っている内容なので、当時を生きてきたおっさんにとっては然程違和感も無く趣旨も理解できる。殆どが著者の主観によるが、そもそも資本主義ってそういうものだよね、と思ってしまうのは、2022年という今に読んだからなのだろうか。2022/11/27
モルツ
21
80年代から90年代の若者文化の変容から、今の若者を覆う閉塞感を紐解く一冊。ベビーブーマーたちが謳歌した若者像はすでになく、社会のシステムの中で 若者は消費する主体として、搾取されるようになった。大人が若者のつもりのまま年をとっていき、その下の若者の居場所がない。/ 社会形成に参加していない今の若者が、活躍する場はない、という指摘は確かに的を射ている。社会システムのなかで割を食う若者ができることは少ない。その現れが、緩やかな社会の拒否(投票に行かない、ネットの右傾化など)ではないかな、と思った2013/01/23
-
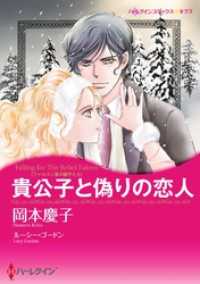
- 電子書籍
- 貴公子と偽りの恋人〈ファルコン家の獅子…