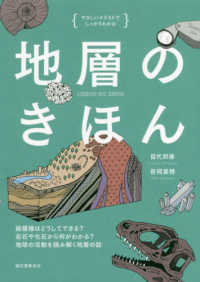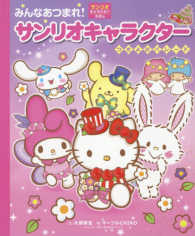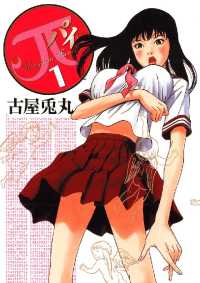内容説明
唯一の被爆国でありながら、「豊かさ」への渇望ゆえに核の力を借りる選択をした日本。核の傘の下で平和憲法を制定する「ねじれ」からはじまったその戦後。推進/反対どちらにも寄らずに、原子力に関わったさまざまな人物や、社会の価値観を可視化する文化的現象を追った「各」論の集積が、混迷する戦後日本の姿を浮き上がらせる!
目次
はじめに―一九四六年のひなたぼっこ(ただし原子力的日光の中での)
一九五四年論 水爆映画としてのゴジラ―中曾根康弘と原子力の黎明期
一九五七年論 ウラン爺の伝説―科学と反科学の間で揺らぐ「信頼」
一九六五年論 鉄腕アトムとオッペンハイマー―自分と自分でないものが出会う
一九七〇年論 大阪万博―未来が輝かしかった頃
一九七四年論 電源三法交付金―過疎と過密と原発と
一九八〇年論 清水幾太郎の「転向」―講和、安保、核武装
一九八六年論 高木仁三郎―科学の論理と運動の論理
一九九九年論 JCO臨界事故―原子力的日光の及ばぬ先の孤独な死
二〇〇二年論 ノイマンから遠く離れて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キミ兄
0
電力3法は、原発事故賠償額を抑えるために人口稠密地区への原発建設を禁止していた。感情的にならず淡々と事実を描写。普通のジャーナリストなら、これだけネタがあれば新書10冊は書いている。☆☆☆☆☆。2011/08/01
臓物ちゃん
0
大阪万博でそんな裏が・・・ショッキング。2012/07/10
kokada_jnet
0
武田徹という人をそれほど評価していなかったのだが、これは良書。2011/05/23
とらやん
0
これは1954年から2002年までの核開発について、 中立的な立場で、幅広く考察したものです。 そのニュートラルな姿勢は貴重で、 原発を語る上で、 絶対外してはいけない一冊だと思います。 ぜひお読み下さい。 それにしても今回の災害を、 著者はどういう思いで見ているのだろか。2011/05/11
白義
0
核と戦後史の関係を、アトムやゴジラといったサブカルから法、思想史まで含めて多面的に問いかけた本。時系列は飛び飛びだけどどの章も本質的なものを含んでいて考えさせられる。単純な賛成でも反対でもない、静かな洞察と思考を行うために今必要な一冊。近々増補版が出るのでそちらを読むのがいいだろう。武田徹の共同体三部作、最後の一冊でもある2011/05/01