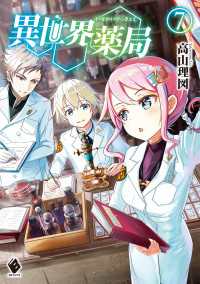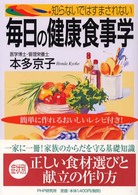内容説明
一九二〇年代、退嬰的な世紀末芸術の後に明るく花開いた美術様式、アール・デコ。ジャズ、ダンス、ファッション――祝祭的で都会的な美が欧州を席巻する。
目次
1 アール・デコの歴史とスタイル(一九二〇年代のアール・デコ;アール・デコの二つの神話 ほか)
2 アール・デコの女性たち(ソフィスティケーテッド・レディ;ポスターの中のモダン・ガール ほか)
3 アール・デコの都市(“イン・スタイル”の時代;パリ(エコール・ド・パリの時代;マン・レイのパリ、ナンシー・キュナードのパリ) ほか)
4 アール・デコの生活(ジャズ・エイジの自動車;スポーツ―ラグビーはジェントルマンズ・スポーツ ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coco.
14
1920年代に流行した装飾様式〈アール・デコ〉解説本。白黒写真だが実物例付きで想像を掻き立てられる。アール・ヌーヴォーは、大戦後に傷ついた人々の気持ちを和らげていく自然寄りで優美なもの。アール・デコには、富裕層の支援で豪華に、女性の社会進出から、彼女たちが憧れるよう女性の為に作られたものが多い。それゆえ百年後も女性から支持され、再ブームもあり得るのだと合点がいった。経済事情・対象者/支援者の存在・職業位置(制作者本人の意識も含む)を押さえることで同時代の映画を観る時、音楽を聴く時、受け取る器も広げられる。2014/02/18
isao_key
7
作者はアール・デコを単に美術、装飾、工芸品として捉えるのではなく、一つの時代のムーブメントとして広告、映画、ジャズ、車、小説などを含めて紹介している。世紀末に起こったアール・ヌーヴォーは日常生活に使われるものを芸術化したい、という運動であったが、エリートのものであった。アール・デコは、記号化、複製化という1920年代都市の状況を背景とした大衆文化による複製芸術であるとする。また「装飾」には美の観念が入っているが「デザイン」は計画、構想することであり、物を作る上で必ずしも美のみを目指している訳でないという。2014/07/22
i-miya
5
2006.05.19 2005.04.25 1920台 1939生まれ 早稲田大学 世紀末のアール・ヌーボー → 一部エリート、前衛的 1918-1932 アール・デコ → 大衆的、複製的 美術館の外 美術公論社 アルフォンス・ミュシャ エミール・ガレ P316 アール・デコ 1918 信号機 ゴーストップ 銀座尾張町交差点 P032 ポール・ポワレ コルセットから女性を解放 1911 女性用ズボン 1911 デザイン学校 マルチーヌ 1914 第一次世界大戦 2006/05/22
コニコ@共楽
3
ぼんやりと思っていた「アール・デコ」のイメージが具体的なデザインや、特定の時代背景があって一気に世界に拡がった。とても納得のいく本だった。第一次世界大戦から第二次世界大戦までの20世紀前半、特に1920年代の時代の空気に近代を非常に感じられた。また、海野さんの本を読んでみたくなった。2015/03/14
shou
3
デザインだけでなく大衆の生活スタイルとしてのアール・デコ全般について。イサドラ・ダンカンなど当時をそのスタイルで生きた人々の話も。アール・ヌーボーとは異なる精神がようやく理解できた感じがする。2014/01/27