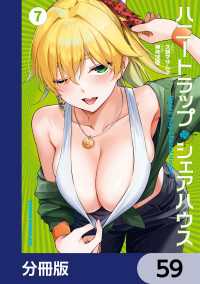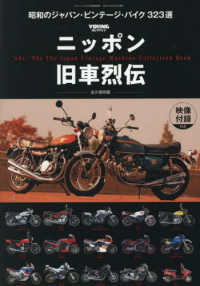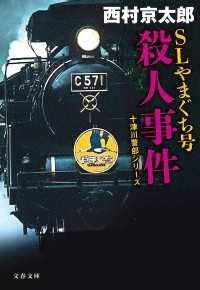- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
城郭や寺社を訪れるとき、まず目に入るのは屋根である。遠くからでもキラキラと光って目立つ屋根は、権威や崇高ささえ感じさせる。このような日本の屋根はどのようにして発達してきたのだろうか。葺材の重さに耐え、雨漏りと戦いながら、職人たちの創意と工夫によって素材や構造を進化させ、独自の美を生みだしてきた。国宝等の修復を数多く手がけてきた檜皮葺職人が、自らの経験をふまえて語る屋根の通史。
目次
序章 屋根のフォークロア
第1章 大陸への憧憬
第2章 貴族文化と屋根
第3章 和様美の定着
第4章 戦国時代の職人たち
第5章 江戸の屋根文化
第6章 合理化、画一化の時代
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ととろ
0
日本史にせよ世界史にせよ、歴史を辿る際には何か一つ、軸があると理解がスムーズになります。本書の場合は日本の屋根を軸に、縄文時代から現代に至るまでの屋根の歴史を辿ります。そして日本の屋根文化を育てたのは神社建築と寺院建築。となれば、神社仏閣の建築史も同時に辿ることになります。筆者の立てた仮説もなかなか的を射ていて、史実を別の角度から視ることができました。2010/10/10
Riko
0
図書館で借りた2010/07/02
わ!
0
屋根は本当はそんなに簡単なものじゃない。形は「切妻(きりつま)」なのか、「寄棟(よせむね)」なのか、はたまた「入母屋(いりもや)」なのか。葺は、「茅葺(かやぶき)」なのか、「檜皮葺(ひかわぶき)」なのか「杮葺(こけらぶき)」なのか、それとも今では一番多い「瓦葺(かわらぶき)」なのか?そのそれぞれに風景があり、機能があり、意味がある。実は屋根とは、そこに住む人からすれば、風除け雨除けのアイテムでしかないかもしれないが、建物を見て、町を見る人からすれば、とても重要な風景なのだ。2014/08/05