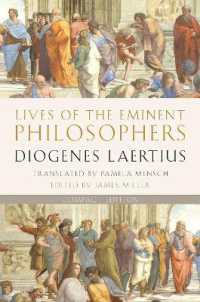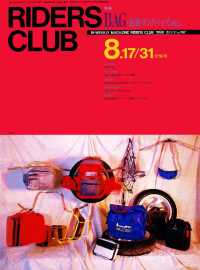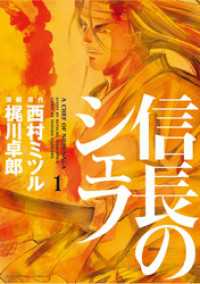内容説明
その時、沖合から不気味な大轟音が鳴り響いた――「ヨダだ!」大海嘯ともヨダとも呼ばれる大津波は、明治29年、昭和8年、昭和35年の3度にわたって三陸沿岸を襲った。平成23年、東日本大震災で東北を襲った巨大津波は「未曾有」ではなかったのだ。津波の前兆、海面から50メートルの高さまで上り家々をなぎ倒す海水、家族を亡くした嘆き、地方自治体の必死の闘い…生き延びた人々の貴重なインタビューや子どもたちの作文が伝える、忘れてはいけない歴史の真実。
目次
1 明治二十九年の津波(前兆;被害;挿話 ほか)
2 昭和八年の津波(津波・海嘯・よだ;波高;前兆 ほか)
3 チリ地震津波(のっこ、のっことやって来た;予知;津波との戦い)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
547
残された資料と、インタビューを基盤としつつ、津波の様子には作家的想像力を加えたセミ・ドキュメンタリー。直接に取材の対象となったのは1896年、1933年、1960年の3度の津波だが、この地域は歴史記録にも何度もの津波の記録がある。まず三陸沖はプレートのズレから、何十年かに一度は必ず海底地震が起こる。その結果津波が押し寄せるのだが、リアス式海岸の地形は津波の高さを一層増幅させるようだ。それでもそこに住まねばならない以上、万全の対策が必要だろう。この地に原発を造ったのは、過去の経験を全く顧みないものだ。2016/03/10
やすらぎ
292
昭和45年に上梓された本書。吉村昭さん43歳のときである。一切脚色せず、事実を聞き集めて伝承する。だからこそ読者は、厳しい現実と向き合うことができる。明治29年、昭和8年、35年、語り継がれた体験談が数多く載っている。改めて認識することは、安全だろうと思いこまず、深夜であっても一刻も早く、少しでも高台に駆け上がること。ありふれた感想になってしまうが、真に大事なこと。文末、住民の意識は高まり今後も被害は減るだろうと期待を記す。著者は2006年逝去され2011年を迎えてしまったのか。やるせない気持ちになった。2024/01/18
さんつきくん
213
「津波は時世が変わってもなくならない、必ず今後も襲ってくる。しかし、今の人達は色々な方法で警戒しているから、死ぬ人はめったにないと思う」。この言葉は明治29年三陸地震、昭和8年三陸地震、昭和35年チリ地震の3つの津波を乗り越えた岩手県田野畑の男性の言葉である。ノンフィクション作家吉村昭さんが三陸地方をこまめ歩いて取材し、記した一冊。女川に生まれ育ったけど3.11前でも体験談として話題になったのはチリ地震津波くらい。1896年と1933年の津波経験者の体験談は貴重だと思う。2013/02/24
Nobu A
193
吉村昭著書4冊目。70年刊行後、04年に文庫化。2年以上前に購入。先日から南海トラフ地震や神奈川震源の地震発生が背中を押してくれた。まえがきが秀逸。専門家ではなく一旅行者として災害の恐ろしさを余すところなく伝えている。さすが国民的作家。東日本大震災から10年以上経つが、やはり忘れてはいけない。驚いたのは災害は常に過酷だと思っていたが、明治29年の三陸海岸大津波の二次災害は今とは雲泥の差。今のように自衛隊が即時に救出に来たりするわけではない。峻厳な自然に放り出され、飢えと悪天候に何日も耐えなければならない。2024/08/10
いつでも母さん
193
「災害は忘れたころにやって来る・・」災害があった後必ず耳にする言葉。何度も辛い教訓から人間は学ぶ。が、それでもまた災害は起こる。明治29年と昭和8年の大津波に襲われた三陸を取材し、記録した吉村昭の本作を今3月11日を前に読了した。10mの大防潮堤を越えて津波に襲われた田老町を、映像で見た私たち。そこで暮らして来た住民の思いは千々に乱れるだろう。第10刷が2011年4月・・吉村作家が亡くなったのはそれより前の2006年。どんなことを思っただろうと思いを馳せた。2022/03/08