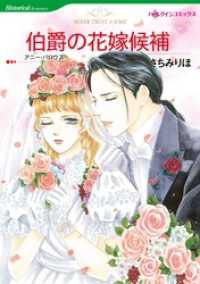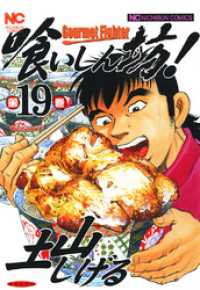内容説明
努力しているのに、いっこうに上達しない。それどころか、かえって技量が低下していると感じられる。このような時、人はスランプを自覚する。単なる疲労なのか、それともマンネリで飽きが生じたのか。<才能の壁>があなたに重くのしかかる。本書は、認知心理学、記憶心理学などに基づき、スランプの構造を解き明かす。スポーツから語学習得まで、あらゆる技能を磨くヒントが<スキーマ>や<コード化>という能力にあることを解明。さらに、その技能を繰り返し使うために必要な、アイコニックメモリ(感覚記憶)、ワーキングメモリ(作動記憶)などの構造を説明する。それらの理論から独自のスランプ克服法を提案する。「ひな型トレーニング」「下位技能の訓練」「理論書を読む」等々。スランプを抜け出た時、自分の人生の小さな奇跡として記憶される。その記憶が後々、人としての成長と余裕を形作るのである、と著者はいう。焦りと諦めを超え、一流をめざすための指南書。
目次
序章 努力が報われないときの考え方
第1章 スランプの八つの外的要因―種類と仕組み
第2章 スランプと無気力の関係
第3章 技能はいかに記憶されるか―上達のプロセスとスランプ
第4章 スランプの内的要因―記憶と認知のトラブル
第5章 下位技能(基礎技能)をチェックする―スランプ克服の方法論1
第6章 ひな型トレーニング―スランプ克服の方法論2
第7章 自我関与(やる気)を高める法則―スランプ克服の方法論3
第8章 理論書を読む―スランプ克服の方法論4
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
山田K
3
感覚でしか捕えられなかったものを、言語化することの重要性。認知スキーマを<評価スキーマ>と<技量スキーマ>に分割する。それによって自分の技能から派生する認知上の制約を受けずに、すぐれた他者の技量を正確に認識し鑑賞することができる。鑑賞の豊かさを享受できる。達人の技量に対する評価スキーマの認識が自分にとって技能化可能、つまり技能スキーマの進歩を与えてくれるといった経験を積む。他者の作品を深い気持ちで見る。なぜこのような発想が可能なのだろう、と考えながら見ているうちにスキーマの差に気付く。とりあえず、覚書。2017/07/02
クジラ
1
岡本浩一氏の考えをより定着させるために2冊連続で読んでみた。ここまでまとめてしまっては、文意が違ってきてしまうのかもしれないが、基本を徹底して、そして丁寧に学ぶことの大切さを改めて感じた。2018/05/04
KTakahashi
0
なるほど2015/08/04
hidehi
0
『上達の法則』の上級編。学習自体はもう軌道に乗った人が対処しなければならないのは確かにスランプだけだ。そのスランプに対応するためには、なぜそういう状態に陥るかを知らないといけない。そしてそれは学習というものの構造により深くかかわってくる。単なるスランプへの対応法ではなく、学習というものにより深い理解を促す好著。 世の中、学習をするには、学習を軌道に乗せるには、という本はけっこうあるが、ある程度の状態になってからさらにスキルを上げるのは難しい。意外と悩んでいる人はいるのではないだろうか。ぜひ再刊すべし。2022/08/20
マーケ・セールス研究家
0
タイトルに惹かれて読んでみたが、ハッキリ言って難しかった。教科書かと思った。本のタイトルを「認知心理学・スキーマのホニャララ」にしたほうが良いと思う。理論と方法の繋がりが今いち良く分からない。かなり難しいので知識をつけてもう一度挑戦したい。2019/08/27