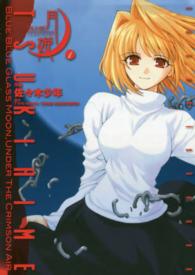- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
歴史は何のために学ばなければならないのか?
そもそも、社会や個人の役に立つのだろうか?
年号ばかり羅列する歴史教科書への疑念。
一方で相対主義や構造主義は、“歴史学の使命は終わった”とばかりに批判を浴びせる。
しかし歴史学には、コミュニケーション改善のツールや、常識を覆す魅力的な「知の技法」が隠されていたのだ!歴史小説と歴史書のちがいや従軍慰安婦論争などを例に、日常に根ざした存在意義を模索する。
歴史家たちの仕事場を覗き「使える教養」の可能性を探る、素人のための歴史学入門講座。
目次
序章 悩める歴史学(「パパ、歴史は何の役に立つの」 シーン1・ある高校の教室で ほか)
第1章 史実を明らかにできるか(歴史書と歴史小説 「大きな物語」は消滅したか ほか)
第2章 歴史学は社会の役に立つか(従軍慰安婦論争と歴史学 歴史学の社会的な有用性)
第3章 歴史家は何をしているか(高校世界史の教科書を読みなおす 日本の歴史学の戦後史 ほか)
終章 歴史学の枠組みを考える(「物語と記憶」という枠組み 「通常科学」とは何か ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
48
ホワイト『メタ・ヒストリー』のような大著ではない本ということで読んでみました。知識ゼロで読めるので、メタヒストリーに関心が無くても、知的なことに関心があるが難しい本はイヤというひとにお勧めです。歳を取って来ると、否応なく自分は歴史的な主体だということと、周囲のものの価値もまた歴史的な網の目によって構成されていることが分かってきます。そのような実感が無い人も、歴史学は科学とコモン・センスの組み合わせだというのが著者の主張を読みながら考えていく経験が、次のちょっと難しい本を読み切る力を与えてくれると思います。2021/11/02
崩紫サロメ
37
再読。歴史学とは何か、平易な語り口でありながら、2004年時点での歴史学をとりまく諸問題を一通り網羅しているように思う。即ち、構造主義的な考え方からの言語論的転回(→歴史を明らかにすることができるのか)、歴史書と歴史小説の違い、歴史は社会の役に立つのか(立つべきなのか)、終盤で少し触れただけになったが「記憶」の問題。歴史家に必要な資質は「疑い、ためらい、行ったり来たりすること」という当たり前のことを改めて考えさせられる。2021/03/30
金吾
22
歴史は事実はわかっても真実にはなかなか到達出来ないと考えていますので、興味深く読みました。一次資料といえど意図があるのでやはり難しいのだろうと思います。2024/01/29
ステビア
22
仕事のため8年ぶりに再読。遅塚先生と全く同じこと言ってるなぁと。2021/09/26
coolflat
22
歴史小説では最終的な判断を著者の実感に基づかせる事が認められている。だから歴史小説では筆者である小説家は想像の翼を広げられる。これが歴史小説のメリット。その一方幾ら史料や先行研究を利用し叙述のみならず分析を加えているとしても記述の信憑性に疑いが残ってしまう。これが歴史小説の限界。これに対し歴史書はあくまでも史料や先行研究の中でそれを根拠に考察を進める。そして根拠がない場合は「わからない」と述べるか、或いは「これはあくまでも仮説である」と断らなければならない。これは歴史書の限界でもあり基本的な特徴でもある。2017/05/27
-
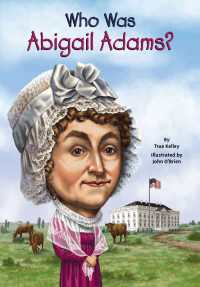
- 洋書電子書籍
- Who Was Abigail Ada…