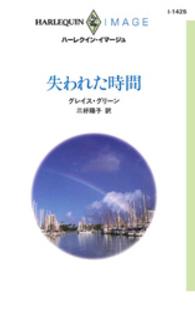内容説明
海は柔らかい交通路である。それは自在な交通を許し、人と人を結び、文化同志を融合させる。本書では全国の中世海村・海民の姿が、綿密な現地調査と文献から浮き彫りにされてゆく。中国大陸・朝鮮半島・日本列島をまたにかけた「倭寇世界人」を生み出した海のダイナミズムを探り、東アジアに開かれた列島社会の新鮮な姿を描き出す、網野史学の論集。(講談社学術文庫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
のれん
9
中世史の革命的存在による小論集。というより対談に近いものもあり、研究内容のおさらいというべき。 網野史観という言葉も知らないまま読むと、混乱するので入門書としてはオススメはできない。 が、それを知れば、本書の日本中世の常識は真に面白い。 中世は地域の産業化が村単位で生まれた時代であり、地域社会の最古の祖先と言って良い。 そこには農民だ武士だという区別も曖昧に人は銭を得るため生きていた。 我々が想像する以上にカオスな共同体が各社会には必ずあった。それは人類社会という枠組みにも繋がっていく面白さがあるだろう。2020/07/05
可兒
4
いわゆる「網野史観」というやつを再確認しようと手に取った。講演録だからか、予想外に読みやすい文章ですらすら読めてしまった。また海民論をよみなおしてみようか2010/04/01
なつきネコ@成長した化け猫 久びさの成長
3
遣唐使の難破の話は言われてみれば、重要な矛盾だな。司馬さんの話の中にも日本の航海技術は低いなんて堂々と書いてたから信じてた。しかし、天照大神を東国では嘘をつく神様と言われて起請文に上げられてないのも驚いた。さらに一の谷遺跡ほどの重要な遺跡が破壊しているとは残念だ。昔の墓があるから縁起が悪いではなく、聖なる場所なのが昔の日本人の感性なのか。2014/04/16
ぼっせぃー
2
『海は、非常に柔らかい自然、交通路です。たとえそこで人が何千万回漁労をし、何千万回そこを渡ろうと、海それ自体には、少なくとも表面にはなに一つ足跡は残らない。』『それだけにわれわれは、これほどの広い海を果たして人が渡ったんだろうかと、どうしても考えがちになり、海の交通路としての役割に対し、消極的な見方に陥りがちになるのはやむをえないところもあるのではないかと思うのです』『しかし本来、海と切り離しがたい生活をしていたはずの日本人が、どうしてこのよ うに海の役割を軽視するようになったのかは、決して単に海の自然2025/04/22
いちはじめ
2
農業中心の史観に一貫して異議を唱えた網野善彦だが、本書も中世海村・海民を力強く論じている。2003/05/13