内容説明
かつて、これほどまでに読者をよくわからない時空に置き去りにするエッセイがあっただろうか。「パレード。」「ぶらぶらする」「発酵と腐敗」「商店街往復」「小走りの人」「動くとおなかが痛い」「牛もいれば馬もいる」「微妙なすきまができている」「カレーと、インド遅れた」など、脱力感みなぎる71篇。面白さを伝えるのが困難な本だが、大変笑えて、おかしい奇書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ・ラメーテ
42
PC関係のエッセイは、今読むと懐かしい感じがする。後半の書評がおもしろくて、宮沢章夫的でありながらちゃんと書評でもあって、今まで興味も無かった本がちょっと気になった。2016/08/14
メタボン
38
☆☆☆★ 相変わらずの脱力エッセイ。読んでいて「何だかなあ」という気分になること請け合い。この気分が面白くて宮沢章夫を読んでしまうんです。しりあがり寿の「エレキな春」の解説が収録。あのマンガが出てきたとき、すごく衝撃を受けたことを思い出した。2019/10/28
春
31
だらだら読んでにやにやするエッセイ。 一番面白かったのは『カタカナの方法』。「デラックス」「スタミナ」「パレード」何でもない言葉を掘り下げまくるのだけど、理解できる感覚もあって笑ってしまう。「パレード」という言葉の持つ「あきれた感じ」は「パ」を発音する時の口を半開きにする姿にあったのか、、。そういえば大学生になった途端、これまでプリントと読んでいたものを皆がレジュメと言うようになって、なんだか「レジュメ」という響の格好よさに口にするたびに照れていたなあ。 表題の『茫然とする技術』は「ぶらぶらする」は→2019/05/04
Tui
30
宮沢さんの面白さといえば、ものの喩えや連想の妙技に尽きると思う。たとえば「事象A」について、もしBなら、さらにはCだったら、いや待てまさかDなんてことはないだろうな、と畳み掛けるパターン。しつこくないギリギリまで発展させるのが持ち味だが、何冊か読むうちに、この展開が一段階しつこく思えてきてしまうのは困った事態だ。ところで後半は本についてのエッセイで、こちらの方が楽しい。『「こんなときじゃなけりゃ読めない」の、「こんなとき」は読書家の憧れである』というくだりに大いに納得。「こんなとき」か、何読みたいかな。2016/05/24
烟々羅
23
1,2章では、東海林さだおの食事エセイの題材を外来語・日本語にしたようだと思った。論理を一周させ、転換して、最後にあらぬところに着地して笑わせて終わる。「なんなんだ、これは」と放り出したくなったら巻末の初出一覧参照、きっと納得する。 3,4章は若い人にはわからないだろう一昔まえのコンピュータ事情が題材。 残り六分の一、書籍エセイを読む前に三週寝かせた。書く感想の文案がぐるぐるして、素直に読めなくなっていたのだ。 こんなに面白いエセイを読んで、お手本にしたくならないわけがない。2013/10/17
-

- 電子書籍
- 生残賭博(全年齢版)【タテヨミ】 72…
-

- 電子書籍
- ニューズウィーク日本版 2014年 1…
-
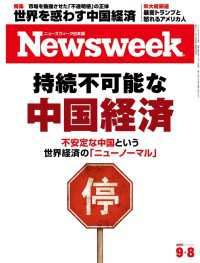
- 電子書籍
- ニューズウィーク日本版 2015年 9…
-

- 電子書籍
- シュガーアップル・フェアリーテイル 銀…
-
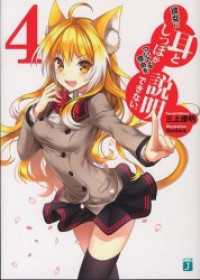
- 電子書籍
- 彼女に耳としっぽがついてる理由を説明で…




