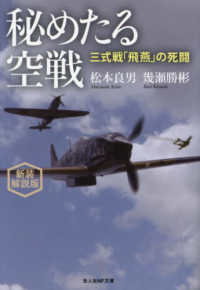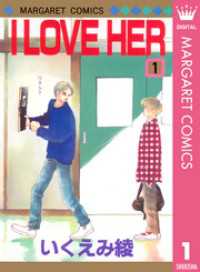内容説明
生命四〇億年の歴史を論じる進化論には、指針となる思想への鍵が潜んでいる――。倫理観、宗教観、優生思想、自然保護など、人類文明が辿ってきた領域を進化論的側面から位置付け直し、新たな思想を提示する。
※本作品は紙版の書籍から口絵または挿絵の一部が未収録となっています。あらかじめご了承ください。
※本文中に「*」が付されている箇所には注釈があります。その箇所を選択すると、該当する注釈が表示されます。
目次
第1章 進化と進化論の歴史
第2章 国家と社会の名のもとに―優生学と社会ダーウィニズム
第3章 社会行動の影に遺伝子あり
第4章 人はなぜ道徳的に振る舞うのか、また、なぜそうでなければならないのか?
第5章 ダーウィンとフェミニズム
第6章 ケーニヒスベルクの三〇〇年―進化論と認識論
第7章 人の心の歴史
第8章 さらばガイア、こんにちはバイオフィリア
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
A
3
著者は、進化論という事実から倫理という価値を導くことを試みる「強い進化倫理学」の立場に立つ。ただ人間の価値判断が複雑すぎて、現在の科学ではそれを扱うのが難しく、科学が価値の問題を扱える水準になるまでは、当面の間、事実から価値を導出するのには慎重であるべきだという留保つき。また進化によって獲得された倫理規範だけでは精度が粗いので、そこは脳による細やかな対応が必要だとのこと。果たして科学が将来価値の問題を扱えるまでに発展するかどうか楽しみではある。ただそれが人種差別などに繋がるのは防がねばならない。2016/04/24
AR読書記録
2
人間を科学するのは難しい。というか、「科学的な知識、さらにはそれを生産する科学活動を、社会なり国家なりの中でどのようにハンドリングするか」(p.209)が本当に難しい。性差別を肯定するような結果だって出る。「政治家や市民団体や、右翼団体や左翼団体や、その他もろもろは、自分たちの政策やイデオロギーに都合のいい「科学的」成果を、てぐすねひいて待ちこがれている」(同)。科学者自身もそのなかに含まれることも多々あろう。必要なのはただの科学じゃなく、思想・哲学のある科学、人間としての自負だろう、と思う。2016/01/04
Ryosuke Tanaka
1
ヒュームのテーゼと自然主義の誤謬ということはまだ注釈のいる概念であり続けているのだろうか(というか強い進化倫理学という形でその前提に疑義を挟みうるということが書いてあるがさすがにどうかと思う)。科学コミュニケーションの失敗例として社会生物学の来歴は大変参考になる。やや読者サービスがすぎるきらいがあると感じた。2015/11/16
A.Sakurai
1
社会生物学は進化論の中でも興味をひかれる題材で,関連する本をいくつか読んでいた.ただし,ウィルソンやドーキンス,トリヴァースあたりで止まっていたので,1990年代以降の展開には疎い.本書は1997年刊なので,ちょうどその続きを概観していて,流れを辿るにはちょうどよかった.筆者自身が「広く,広く」というようにあまり突っ込んだ検討はなく,おおよその流れを説明している.進化倫理学や都市行動生物学といった分野が社会生物学から派生して進んでいるので,次はこれらを読んでいこう.2013/10/27
うえ
0
元々95年に出た書物。他の進化論の書物と比べると,あまり進化論とは関係ない。進化心理学の立場だが著者のいう「倫理的人道的立場」なるもの考え方が、イスラーム、カトリック、マルキシズム、民俗宗教、ヒンドゥーあたりでも共通していないと意味ないんじゃないかと。その点ドーキンスが無神論を言い始めたのはよくわかる。「今でこそ自民族中心主義といえば極右保守派と相場は決まっているが当時の優生学の担い手はむしろ自由主義者や社会主義者だった」現代「マルクス主義科学者たちの組織が反社会生物学キャンペーンを大々的に展開した」2014/11/07