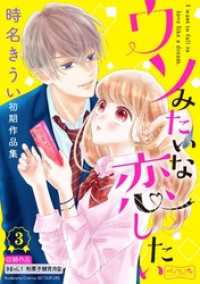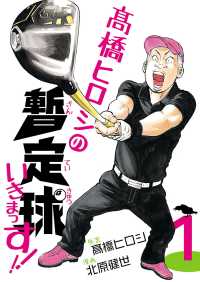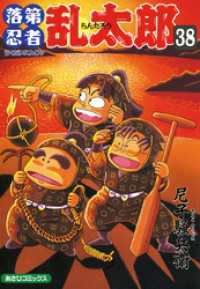内容説明
「青春は無限に明るく、また無限に暗い。」――岡本太郎にとって、青春とは何だったのか。パリでの旺盛な芸術活動、交遊、そしてロマンス……。母かの子・父一平との特異ではあるが、敬愛に満ちた生活。これらの体験が育んだ女性観。孤絶を恐れることなく、情熱を武器に疾走する、爆発前夜の岡本太郎の姿がここにある。
目次
1 青春回想(色気と喰気 はたち前後 独り旅 ほか)
2 父母を憶う(母、かの子の想い出 ヨーロッパのかの子 白い手 ほか)
3 女のモラル・性のモラル(処女無用論 日本女性は世界最良か? 服装直言 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Y2K☮
38
岡本太郎は絵を売らない人だった。ゆえに講演やこうした文章を書く事で収入を得ていた。フランス時代を舞台にした回がやはり最もイキイキしている。戦争さえなければ永住していたのではないか。でも彼に云わせれば、そうした不条理な運命と戦って己を開いてこそ人生なのだ。他人の目や道徳に囚われず、云うべき事は云う。且つ孤高を気取らず、窮屈な社会の中で生活を営む。この生き辛さや矛盾を引き裂く緊張感が次の芸術を生むと。今を全力。だから楽しめる。独身論や性の話もバランス感覚が素晴らしい。現代の男性女性共に読んで腑に落ちるのでは。2020/02/20
i-miya
27
2012.03.20(初読)岡本太郎著。 2012.03.20 (カバー) 「青春は無限に明るく、また無限に暗い」パリ、旺盛な芸術活動、交遊、そしてロマンス。母、かの子、父一平の特異ではあるが、敬愛に満ちた生活。その体験-女性観。情熱武器に爆発前夜祭!御覧下さい、青春太郎劇場、解説はみうらじゅん。2012/03/20
i-miya
23
2012.03.25(つづき)岡本太郎著。 2012.03.25 ◎はたち前後。 フランスに行ったのは、18.9歳の頃。芸術は手先の問題ではない。生活がその土台になければならないことは、私もわかっていた。おのれを堕落させるよう努めた。小モラルからの-日本的小モラルからの離脱。放縦であるためには、やはり手段と技術がいった。まず,異性が当面の問題である。ノエミというかわいい、魅力的なアルゼンチン娘にまいってしまった。2012/03/25
i-miya
20
2012.04.08(つづき)岡本太郎著。 2012.04.07 モンマントルはまさに不夜城である。キャバレー。楽屋にはなぜか、私だと気軽に入れてくれる、美女たち、一糸まとわぬ裸で化粧に、衣装替え、まるで肉体を誇るかのように。賭博は、女よりも、酒よりも、強い。一時は寝食も忘れて没頭したものである。パリの「昼の女」? ケッセルの小説、『昼顔』である。『娼婦、マヤ』など。 2012/04/08
roughfractus02
10
著名な両親のもとに生まれたことの重圧の中で否応なく「無限」に肥大する青春の「虚無」を、著者は芸術に集中することで対抗した。父一平が母かの子を信仰し、母かの子は芸術へと陶酔する家庭環境で、著者は、両親が疑わずにいた大正的芸術観を超克する姿勢を体得していく。青春の試行錯誤にから生まれる「虚無」は批判に変貌し、両親に留まらず近代日本社会が個人の内面に芸術を押し込め、歴史や社会に閉鎖的である点にその目を向ける。本書後半は、男性性や女性性も商業主義の個人への封じ込めだと批判し、開かれた社会に程遠い現状を暴いていく。2023/03/17