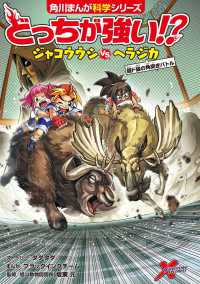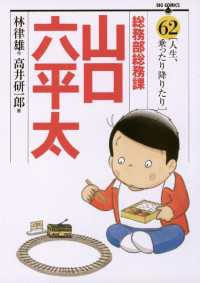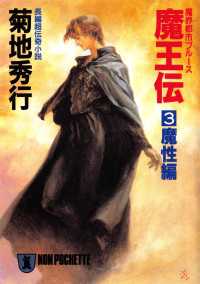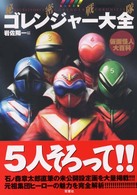- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
9・11テロは、文明の「外的」が引き起こした事件というだけではない。私たちの内にもテロに呼応する側面があるのではないか。テロリストは、私たちの内なる欲望を映しだす鏡ではないか? 現代世界の深層に横たわる葛藤の根源的要因を、資本のグローバル化との関連で鋭く読み解き、この葛藤を克服するための方策を探る、スリリングな 1 冊!
目次
序章 9・11テロ、そして社会哲学の失効
第1章 文明の内的かつ外的な衝突(資本主義への攻撃か?;テロリストへの憧憬 ほか)
第2章 イスラームと資本主義(「交換」の論理;ラシュディ事件再考 ほか)
第3章 原理主義的転回(国外における内戦;「生きよ!」と命令する権力 ほか)
第4章 弱くかつ強い他者たちへ(セキュリティの逆説;さまざまな「解決」 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mealla0v0
2
悪名高きサミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』――それを通俗的な批判とは真逆の方向性から批判し、つまり、文明vs.文明という構図の大きさではなく、それがむしろ隠蔽する決して一枚岩ではない文明の内側に存在する亀裂や対立という観点から批判し、新たに「文明の内なる衝突」というテーゼを提出する。▼しかし、この有意に思えるテーゼ、その立論に対して、考察が拡散し、論として不十分な印象は拭えない。それが内戦という今次を騒がすものに有効であるだけに、残念である。2016/12/31
davi
1
筆者の理論は相変わらず難解なんだけど、対象が具体的で情勢分析が鋭いこともあって内容が頭にスルスルと入ってくるのを感じた。で、テロ後の世界を考えるに当たって、現実はさらに困難になりつつあるんだけど、不可能な「普遍性」を(赦す)(赦される)行為により否定的な<普遍性>の到来を期待する思想は感動的ではある。2019/12/30
肉欲棒太郎
1
9.11後の国際社会が示すものは、敵たる「危険な他者」が外的であると同時に「内的」であること、それが高度の資本主義の今日的展開による帰結であること、その結果自由と民主主義を守るためのセキュリティの未曾有の高まりが逆に自由と民主主義を危機に陥れていることなど、なかなか示唆に富む論が展開される。ただ結論部分はやや心許なく、著者もまだ模索段階にある感じが伺える。2013/10/29
Ecriture
1
キリスト教とイスラム教の差異と類似点。この人の本の結論はいつも疑問が残る。2008/05/08
freebird
1
三幅対が困難に遭遇するのは、人々が共存し、共同体を構成するためには、最小限の規範が――つまり善や正義についての基本的な判断が――共有され、一致していなければならない、と考えているからである。このような前提を採用したとたんに、われわれは、他者との衝突――外的であるばかりではなく内的でもあるような他者との衝突――を回避することはできない」(231ページ)。2008/06/11