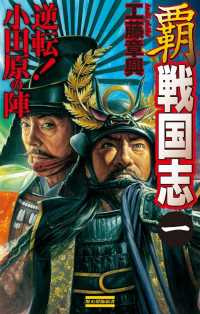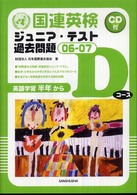- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
刑事事件の供述調書には様々な〈うそ〉が存在する。取調官に暗示・誘導された結果、被疑者が虚偽の自白をしたり、証人が無意識のうちに記憶を歪めてしまう。人はなぜ、このような〈うそ〉にだまされるのか? 人が過去と向きあう際に、陥りがちな錯誤を、多様な犯罪の供述を分析してきた著者が、明らかにする。
目次
序章 「供述の世界」に挑む心理学
第1章 人はなぜ、うその物語にだまされるのか―『藪の中』の供述分析
第2章 うその物語ができあがる過程―狭山事件の真相
第3章 うその物語を見抜く五つの指標
第4章 悲しいうそ―一家四人惨殺事件の供述調書から
終章 人は対話的空間を生きる―「供述の世界」から一般心理学に向けて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
加藤久和
3
俗流心理学のハウツー本を想起させるような書名だが内容はまったくそうではない。人はなぜ自分に不利な嘘をついて無実の罪を自白してしまうのか。冤罪事件をめぐる供述分析の一端を垣間見ることができる。少し疑問に思うのは強要も拷問も無い自発的な自白とは言うが、そもそも警察の取調室に単独で監禁されたらそれはもう拷問と言えるのではないか。とにかくマスコミによる「容疑者は容疑を認めています」という報道は一切信用してはならない。警察に逮捕されようが裁判で確定判決が出るまでは何人も無罪なのだということをそろそろ常識にすべきだ。2018/12/05
Hisashi Tokunaga
0
うそと真が不分明に日常生活に入り混じっている。=そうだと思います⇒うその部分の方が少ないけど。身体の臨場性こそ、世界の原基=諺通りです。虚偽の自白=自分はやっていないから裁判所でわかってくれる・・自分はやっていないという確信のゆえに自白への抵抗感は弱くなる。⇒今や取り調べの可視化問題に象徴されるように、意外と自白には慎重になってるんじゃないの。完全黙秘の有効性は?(2013・3記)ネッカーの立方体、ペンローズの三角形ほか
鈴と空
0
2006年以前