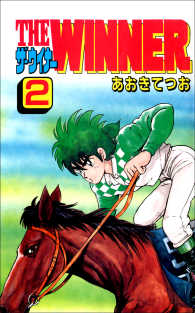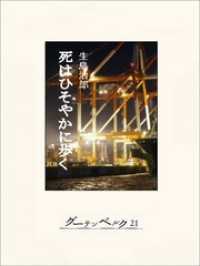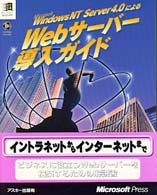- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
小学校低学年で急速に広がり出した学級崩壊、キレて凶悪事件を引き起こす十代の少年たち、いじめ、引きこもり、幼児虐待、援助交際、不登校…。
いま、子どもの世界では、何が起きているのか。
危機の実像とそれをもたらした背景を丹念に解明し、子育てと教育を再生させる考え方と実践例を提示。
従来の学校観や子育て観の転換を迫る。
学級崩壊,少年事件,キレる子現象,いじめ,幼児虐待,援助交際,不登校….いま,子どもの世界では,何が起きているのか.危機の実態とその背景を解明し,これからの教育と子育ての考え方を実践例とともに提示する.
目次
1 危機の実像(学級崩壊;新しい荒れ;いじめ;虐待)
2 危機の背景をさぐる(変化に取り残された学校;教師はなぜ力をなくしたのか;家庭の子育て力は低下したのか;大人と子どもの関係不全;子どもが問いかけていること)
3 危機からどう脱出するか(スクール・デモクラシーで学校再生を;「教え」から「学び」へ;子育てを社会化する;子どもと大人のパートナーシップ時代へ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
20
2000年刊。学級崩壊が社会問題化した時代に書かれている。学級崩壊は、セルフコントロール不全であり、かつ仲間に過剰に同調するといった子どもの態度傾向にその一因が求められるという。それは生活状況と学校の雰囲気との乖離から起こるとされる。衝動を抑える事ができない子どもの暴力化傾向という指摘はあるが、その背景要因に関する分析は曖昧であるように思う。それよりは、子どもの権利条約に即して、子供を権利行使の主体として教育の実践を変えていくべきだという後半の主張が面白かった。論点が割れている気もしたがいかに。2023/11/11
KASAO
17
学級崩壊、いじめ、キレる子ども、引きこもり、虐待、援助交際、不登校などの問題を取り上げ、それらの原因と改善を述べた一冊。学校体制の中で子どもをギチギチに管理するような教育の見直し、メディアから子どもへの配慮、学校、家庭、地域社会の3つで子どもを支えるべきなど、2000年に出た本なのに今読んでも共感したり、なるほどと思わされる箇所が多々ある。読んでいる途中で『窓ぎわのトットちゃん』やアドラーの思想を思い出した。2017/01/25
イリエ
3
暴力的な子どもの危機的状況の背景を探りながらも、脱出するヒントを具体的に示してあります。尾木ママの優しさが伝わります。ただし、これらは社会システム上の問題で、個別具体的な方法を示しているものではありません。学級崩壊を社会問題としていかに捉えるか、という意味では良書です。2015/04/23
だいすけ
2
「子どもと大人がパートナーシップで生きていくためには(中略)参加の概念を、実践的にも、イメージの上でも前面に押し出すことによって、子どもの自己決定権を尊重できますし、今度は、大人が子ども問題にとことん参加し子どもの最善の利益を擁護することによってケアが実現でき、両者は統一されていくのではないでしょうか。」2019/04/14
ぴー
1
まさに学級崩壊やいじめ、新しい荒れを体験したり間近で見てきた子供の私は、第二章の背景の分析が非常に的を得ていて納得した。確かに自尊感情が著しく低い子が多いし、同調圧力が高いことにも気がつかされた。尾木さんもおっしゃるように、せめて子供の意思表示や自己防衛を大人が尊重できたり、親が外に頼れる場所を持てたりする環境づくりがされて欲しいと思う。2014/01/13