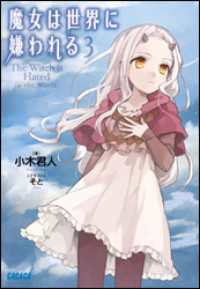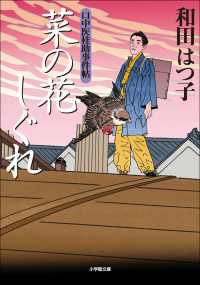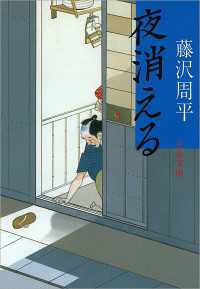- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
これからはどんな企業も「知識創造」をしていかなければ生き残れない。『エコノミスト』等世界の一流誌が絶賛した、世界に誇りうる日本人による初の「経営理論」。
【主な内容】
序文
謝辞
第一章 組織における知識――序論
第二章 知識と経営
第三章 組織的知識創造の理論
第四章 知識創造の実例
第五章 知識創造のためのマネジメント・プロセス
第六章 新しい組織構造
第七章 グローバルな組織的知識創造
第八章 実践的提言と理論的発見
日本語版へのあとがき
参考文献
目次
第1章 組織における知識―序論
第2章 知識と経営
第3章 組織的知識創造の理論
第4章 知識創造の実例
第5章 知識創造のためのマネジメント・プロセス
第6章 新しい組織構造
第7章 グローバルな組織的知識創造
第8章 実践的提言と理論的発見
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
127
これも最近話すことに関連があるので再読です。読み直して思うことはやはり昔はやった日本的経営ということを「暗黙知」という観点から説明しているのでしょう。野中先生の独自の考え方だと思いますが、人間知を形式知と暗黙知に分けて説明したというのは面白い考え方だと感じました。2016/07/07
molysk
51
組織において知識はどのように創造されるのか。まず、知識は暗黙知と形式知に区別され、両者は互いに変換する。この相互作用は個人ベースで行われるが、グループや組織レベルで増幅されることで、知識は組織的かつスパイラルに高度化する。スパイラルはトップと現場を巻き込むため、ミドルマネジャーが知識マネジメントの中心となる。知識創造の東洋的方法はグループと暗黙知の重視、西洋的方法は個人と形式知の重視にあるが、両者の長所の統合が求められる。事例がシャープなど古さは否めないが、時代を超えて読み継がれる日本発の経営理論の名著。2020/05/03
著者の生き様を学ぶ庵さん
35
日本発の経営理論が生まれたのは大いに称賛すべきこと。しかし経営理論の後に出てくる成功企業の事例の評価は難しい。それは、エクセレント・カンパニーでも類書でも同様に、「成功企業」が経営危機に瀕する例が多いため。また、後から見ると、一時的に調子の良い流行りの企業を都合良く取り上げて自説の説得力アップに使っているように見えるため。このようなとき、事例企業の良し悪しは無視し、経営理論としての評価に集中した方がよいと考える。2017/01/08
1.3manen
28
1995年初出。組織的知識創造とは、新しい知識を創り出し、組織全体に広め、製品やサービスあるいは業務システムに具体化する組織全体の能力(ⅱ頁)。知識には形式知と暗黙知がある(ⅲ頁)。暗黙知は経験知でもある。 ドラッカーは、知識社会では、知識労働者が最大の資産という(7頁)。個人知から組織知へ(17頁~)。日本的知の伝統は全人格の強調(41頁)。 バーナードは、行動的知識が重要であると強調(52頁)。組織化問題の本質は、バーナードによると、個人を合理的協働システムにまとめること(53頁)。 2014/09/01
KAZOO
27
野中先生が以前から言われている、暗黙知から形式知への転化をどのようにして具体的に行っていくのかが詳細に記されています。とくに第五章の知識創造のためのマネジメント・プロセスは非常に参考となりました。ただあくまで書かれていることは理想的な企業だと思うのでそれを実際の企業に適用していくのかはかなり高いハードルではないかと感じました。2014/09/09