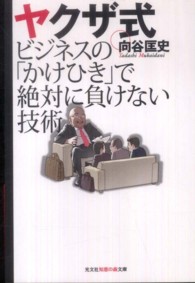- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
戦前・戦中、炭坑資源開発のためサハリン(樺太)に渡った労働者の中には強制的・半強制的に募集・連行された韓国・朝鮮人が数万人いた。終戦とともに始まった引き揚げ事業はサハリンにも及んだが、その中に帝国臣民として徴用された朝鮮人は含まれていなかった。彼らはソ連統治下のサハリンに残されたのである。冷戦・南北朝鮮対立という国際環境、そして日本の戦後責任への無自覚に抗し、故郷訪問に至るまでの四十五年の足跡を克明に辿る。
目次
第1章 サハリンに渡った人々
第2章 故郷に帰る日本人、残される朝鮮人
第3章 朴魯学たちの引き揚げ
第4章 朴魯学たちの運動
第5章 帰還運動の広がりと壁
第6章 サハリン裁判と裁判実行委員会
第7章 アジアにたいする戦後責任を考える会
第8章 サハリン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談会
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
76
1992年の初版本の積読をようやく解消。前半は1945年夏ソ連に占領されたサハリンで働いていた朝鮮半島南部出身者が、日本・ソ連・アメリカ(当時日本を占領していた主体)の不作為により取り残された事実についてかなり詳細に書かれている。その後当事国である韓国の動きも出てくるが、何しろ時代が東西冷戦(朝鮮戦争もあった)の真っ只中な上、日本と韓国の関係も厳しく(李承晩時代)、その上どの国にとっても「小さな問題」としてしか扱われていなかった様子が分かる。しかし当該者やその家族にとっては大問題。著者はそれを引き受ける。2024/06/21
BLACK無糖好き
15
終戦時サハリンには約4万人の朝鮮人がいたとされ、中には日本による強制的な動員も含まれる。戦後の引揚げにあたり、このサハリンの朝鮮人が置き去りとされ、祖国帰還まで半世紀近くを要した。本書は帰還運動に携わった日本の国際法学者による活動の記録。歴史の無慈悲な一面を痛感する。ソ連、北朝鮮、韓国それぞれの思惑が交錯し、様々な壁が立ちふさがり、国際政治の場では人権問題がいかに政治的に扱われるかという現実に直面。著者は日本政府の不作為を問題の根源としている。何とも言えない虚しさに包まれる。 2016/08/27
Mealla0v0
4
表題の「サハリン棄民」とは、主に戦中強制労働のために強制移動させられ、戦後置き去りにされた朝鮮人労務者――しかも多くは坑夫――のことであった。日本政府は日本人の引き揚げには熱心だったが、朝鮮人には冷淡だった。しかも悪いことに、GHQの無関心、ソ連の労働力確保の思惑、北朝鮮の「韓国への」帰還の嫌悪、韓国の帰還者を養えない自国の経済状況などといった複合的な要因から、在サハリン朝鮮人は棄民同然に追いやられて行った。著者はその運動に携わった経験から、この問題の要点を的確に指摘している。2018/02/01
印度 洋一郎
3
戦前は日本領だったサハリン南部に出稼ぎ及び、戦時中の動員で渡った朝鮮民族は、戦後独立した祖国に帰る事が出来ずに約半世紀を過ごすという境遇に置かれた。戦後、日本人では無くなった事で日本政府の引揚げの対象にならず、出身地である韓国は経済的負担に繋がると消極的、逆に北朝鮮は「朝鮮半島の正統政権」を標榜するために当事者の意思を無視する形で送還を主張、冷戦下で北との関係を重視するソ連がそれに同調、という四すくみの構造が絡み合い、帰還は進まなかった。このサハリン朝鮮人帰還問題に取り組んだ著者は数々の困難に直面する。2024/11/26
cochou
3
前半はサハリンに残された南朝鮮の人々の歴史を追うことで日本国民や政府の態度・心情や、ソ連、韓国、北朝鮮、日本の駆け引きとデッドロック状態が良く分かる。終戦前後でクリアに分けるという一般的な歴史観が大きく揺さぶられる。 後半は帰国運動の中心となった著者から見た運動の歴史と心情が綴られる。「(国連人権委通報の経験は)人権問題の政治性に対する理解の甘さを示す」反面教師だというのが痛切。最終的に議員連盟が解決の力になったことは政治の可能性を考える上で重要な示唆だと思う。2018/10/25