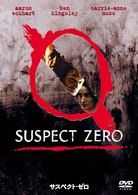基本説明
日本語学 冬号 「文章を書く教育」「日本語と試験」|
詳細説明
【特集】文章を書く教育
日本語の文章作成とその教育においては、学術分野、ジャンル、教科・科目、校種、学習者の属性などによって様々な文章像が掲げられ、それを目指してよりよく書けるようにと指導や学習が重ねられている。書く指導にあたる教師たちの努力によって、学習者は書く力を養い、書き手となって多くの文章を産出するようになる。そのことが、豊かな書き言葉を形成し、社会の活力の増進につながっていく。
ところで、学習者は、校種が上がったり複数の学術分野を学んだりすると、異なる文章像を目指した新たな文章指導を受けることもあるが、既に習得した文章作成法を、新たに学ぶ文章に応用できる場合もあるが、作成法や指導法の違いに戸惑ったり混乱したりすることもある。一方、指導者は、自身が属する領域とは別のところで、どのような文章指導が行われているのかをよく知らないことで、学習者の混乱に気付かなかったり、気付いてもそれにどう対処してよいか困惑する場合もある。
そこで、本特集では、日本語の文章を書く教育をめぐる近年の動きを広く取り上げ、文章の指導者や学習者のニーズに応えたい。あわせて、日本語で文章を書く教育について広く考える材料を提供したい。
【特集】日本語と試験
日本語に関する各種の力を測るために、さまざまな試験や検定が実施されている。どのような力をいかなる内容により、どのように測定しているのだろうか。またその結果からはどのような現状が現れてくるのだろうか。
ここでは、その中から主なものについて、それぞれの主催側の方々に紹介していただき、併せて過去の関連する試験の実態について紹介する。
目次
【特集】文章を書く教育
日本語の文章研究と文章作成(石黒圭)
国語科教育における「書くこと」の指導(田中宏幸)
DX時代の探究活動とアウトプット(品田健)
大学生の学術活動と文章作成指導(佐渡島紗織)
留学生に対する文章作成指導(大島弥生)
作文教育の国際比較(渡邉雅子)
児童・生徒作文の分析と文章指導(松崎史周)
わかりやすく書くこと(岩田一成)
文章のジャンル・スタイルと言葉の教育(安藤宏)
日本語の歴史から見る文章規範の転換(田中牧郎)
【特集】日本語と試験
日本語検定の方法と現状(中川秀太)
日本語能力試験の方法と現状(高野知子・市岡香代)