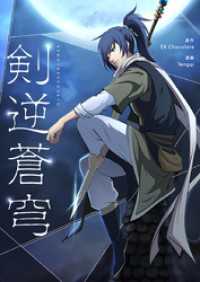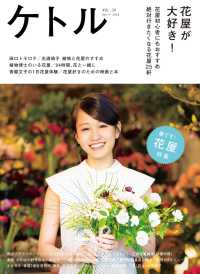出版社内容情報
■第一章 蕎麦学入門
蕎麦の文化史/特別対談 蕎麦と池波正太郎と「神田まつや」…野上龍雄(脚本家)×小高登志(神田まつや主人)/蕎麦の雑学ノート…1蕎麦の旨さとは何か 2旨い蕎麦ができる条件 3蕎麦屋ガイドについて
■第二章 蕎麦屋ガイド 東京・江戸蕎麦探訪記
千寿竹やぶ/玄庵/吟八亭やざ和/更里/神田まつや/九段一茶庵/小菅/山せみ/しながわ翁/箱根暁庵(広尾)/野中/法師人/進士/道心/典座/まん月/吉祥寺砂場/本陣房グループ・天祥庵/布恒更科/きびや/蕎楽亭/大川や/睦/京金/坐忘/一久/松翁
◆コラム
蕎麦の栄養学/夜蕎麦の誘惑/蕎麦屋の酒 など
◆資料編
蕎麦の重さと値段のグラフ/東京・江戸蕎麦おすすめ蕎麦店リスト88
江戸ソバリエへの道
私は青年期からかなりの「西洋かぶれ」だった。そんな私に、40代に入る前あたりから、「日本回帰」ともいえる変化が起きた。NPO法人神田雑学大学の主催する「江戸ソバリエ認定講座」を受け、江戸ソバリエとなったのもそのひとつだ。「江戸ソバリエ」とは、ワインのソムリエをもじった造語で、蕎麦のソムリエを目指すというもの。2003年5月、新聞の朝刊で「江戸ソバリエ認定講座」が開講されることを知りすぐさま申し込んだ。講座は、耳学(江戸蕎麦などに関する講義)、手学(蕎麦打ち体験)、舌学(蕎麦屋の食べ歩き)、脳学(まとめのレポート作成)とに分かれ、レポートを提出してめでたくソバリエの認定証も授与された。
「西洋かぶれ」だった私がなぜ「江戸ソバリエ」になったのか。古い話で恐縮だが、私は、中学3年で英語に目覚め、高校1年の時には、アメリカンスクールの女子高生と知り合い、その甲斐あって?高校2年では、O社の全国テストで英語は全国2番の成績となった。調子づいた私は大学1年で英検1級にチャレンジし、一発合格。その後も米軍基地のあった立川などに出かけ、英語に磨きをかけた。同時に、フォーク・ロックの音楽活動にも明け暮ってもらった帰りに、並木藪蕎麦などの老舗に立ち寄った記憶がある。DNAに刻まれた、いわば日本文化が、年齢とともに顕在化してきたのかも知れない。
本書では、ビジネスマン、そして日本を代表する素晴らしい先生方に教えていただいた「江戸ソバリエ」の一人として蕎麦屋巡りをする中で、感じたこと、学んだことをまとめさせていただいた。蕎麦はもともと庶民の食べ物である。手打ち蕎麦を食べに行き、量の少なさにがっかりした思い出もある。そういう不満や物足りなさを感じる読者も少なくないに違いない。そうした思いから、失礼ながら、「蕎麦屋ガイド 東京・江戸蕎麦探訪記」では各店の基本となる「もり蕎麦」の分量を量らせていただき、その結果を「蕎麦の重さと値段のグラフ」や「総合評価グラフ」に反映させるなどの試みを行った。さらに、蕎麦屋で酒を飲む、友人と語らう、接待に使うなど、さまざまな蕎麦店の活用に参考になるよう、できるだけ値段(2004年10月時点)も掲載した。また、巻末にはわが江戸ソバリエ仲間のご協力をいただき、私が取材した店に加え、採り上げられなかった他のおすすめ蕎麦店を各人のひと口コメントを付け「おすすめ蕎麦店リスト88」として掲載してい
◎ここがポイント
・本書は、NPO神田雑学大学が主催する「江戸ソバリエ認定講座」を修了した著者が、そば通、蕎麦の伝道師として、実際に食べ歩き、本当に旨いといえる蕎麦屋を厳選し、接待やデートに使える店を紹介する。
・本書には、大手旅行会社に勤めるサラリーマンの著者が、かねてより名店・有名店の蕎麦の量が少ないことに失望していたため、もっと旨くて分量のある蕎麦屋はないものかと探求した結果が示されている。
・本書では、蕎麦屋酒を愉しむため、各店の酒肴やおすすめ料理の写真と情報(値段など)を紹介するとともに、「もりそば」については計量を行いグラム数と単価も掲載し、各店のコストパフォーマンス比較なども掲載。
・本書は、蕎麦の歴史をはじめ、蕎麦の雑学ノートとして、原料のソバや、製粉方法、打ち方などの基礎的な知識をコンパクトにまとめてある。そば通への近道を行くガイドブックとして最適である。
・神田の老舗まつや店主・小高登志氏と、まつやと縁の深かった池波正太郎作品の脚色を数多く手がけた野上龍雄氏との特別対談を収録。池波正太郎の愛した蕎麦と蕎麦屋を語りつつ、旨い蕎麦の真髄をさぐってゆく。
◎こんな人にお薦め
・
内容説明
各店の基本となる「もり蕎麦」の分量を量らせていただき、その結果を「蕎麦の重さと値段のグラフ」や「総合評価グラフ」に反映させるなどの試みを行った。さらに、蕎麦屋で酒を飲む、友人と語らう、接待に使うなど、さまざまな蕎麦店の活用に参考になるよう、できるだけ値段(2004年10月時点)も掲載した。また、巻末にはわが江戸ソバリエ仲間のご協力をいただき、私が取材した店に加え、採り上げられなかった他のおすすめ蕎麦店を各人のひと口コメントを付け「おすすめ蕎麦店リスト88」として掲載している。
目次
第1章 蕎麦学入門(蕎麦の文化史;特別対談 蕎麦と池波正太郎と「神田まつや」(野上龍雄(脚本家)×小高登志(神田まつや主人))
蕎麦の雑学ノート)
第2章 蕎麦屋ガイド東京・江戸蕎麦探訪記(千寿竹やぶ(足立区・千住大橋)
玄庵(葛飾区・京成立石)
吟八亭やざ和(葛飾区・亀有)
更里(台東区・浅草橋)
神田まつや(千代田区・神田須田町) ほか)
著者等紹介
国松靖弘[クニマツヤスヒロ]
1955年(昭和30年)、東京・浅草に生まれる。1979年、大手旅行会社JTBに就職。旅行業という仕事柄、日本はもとより、世界各国に赴きフレンチやイタリアンなどをはじめ、各国・各地域の特産・名物料理を15年以上にわたり食べ歩く。その結果、10年程前から改めて、日本の江戸前料理に興味を持ち、究極の食べ物として、特に蕎麦にのめり込む。2003年、NPO法人・神田雑学大学主催の「江戸ソバリエ講座」を受講し、「江戸ソバリエ第1回生」として認定される。以後、ライフワークとして本格的に蕎麦研究に取り組んでいる。「ソバリエ・蕎麦通オフィシャルサイト」も主宰し、世界に冠たる日本の蕎麦文化の伝達に奔走している。一方で、学生時代から続けている作詞・作曲の音楽活動など、多彩な活動を展開している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。