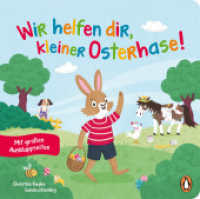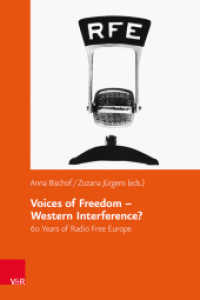出版社内容情報
〈象徴暴力〉とは何か?
『遺産相続者たち』('64)にはじまる教育社会学研究を理論的に総合する文化的再生産論の最重要文献。象徴暴力の諸作用とそれを蔽い隠す社会的条件についての一般理論を構築。「プラチック・」論の出発点であり、ブルデュー理論の主軸。
目次
第1部 象徴的暴力の理論の基礎(教育的働きかけの二重の恣意;教育的権威;教育的労働について;教育システムについて)
第2部 秩序の維持(文化資本と教育的コミュニケーション;教養人的伝統と社会の自己保存;排除と選別;独立による従属)
付論 高等教育進学機会の構造の変化―変形か、それとも転移か
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
香取奈保佐
41
「学校制度は、文化資本の収益性を確かなものにし、この資本の伝達を正統化する」。「文化資本」という独自の概念を用いて、社会における学歴と収入格差の再生産を暴き出した一冊。親が高学歴で教養のある人物であれば、家庭でも抽象度が高く複雑な会話が交わされやすい。そうした環境で育った子供は教養的知識と親和性が高く、学校教育の下でも有利な育ち方をしていく。教育や学問は社会階層や秩序と無関係であるかのような顔をしているが、そのじつ密接に結びついている。本自体は難解なので、時間がなければ教科書を読んだ方がよい。書評かきます2015/01/18
roughfractus02
8
5月革命以後、社会批判する学生たちのバイブルになったという本書(1970刊)は、学校教育が自らの文化資本を再生産する上流階級の恣意的な象徴的暴力の行使の場となっていると批判した。その際ハビトゥスは2つ、生まれ育つ環境としての第1のハビトゥス、さらに学校に適合するように仕向けられて身につく第2のハビトゥスに分けられる。第1から第2への移行が滑らかかどうかはシステムの問題ではなく、上流階級が恣意的に選んだ文化資本に適合するかしないかにある。また、適合せずに生じる反学校的文化も文化的再生産のうちにあるとされる。2024/06/06
山田
3
勉強。『Algeria60』を書いた人がこんな話も書くのか…まるで社会学者のようだあ…と思ったら社会学者だったわ。すっかり人類学者の気になってた。どうにもこうにも外国人には使いづらそうな話ばかりでそれなりに読み飛ばしてしまった。皆が「誤認」の部分しか使わないのも納得できる。2016/08/11
剛田剛
1
・そういや竹内洋先生が似たようなこと言っていたな、と思いながら読んだ。・それにしてもなんでこんな読みづらい文体を選択したのだ?・階級という係数を算入しない教育観は出発点においてすでに失敗していると言えるのではないか?・日本では「学問としての文学」は今後ますます「富裕層のお嬢ちゃんのための嗜み」になっていくのだろうな。・それにしてもなんでこんな読みづらい文体にしたのだ(2回目)・おそらく一般的なイメージとは逆に、サブカルチャーの世界でこそ「文化的資本」の格差は剥き出しになる2020/04/22
demoii
1
一回詰まると、何十分も止まってしまってなかなか進まない。とても難解だった。フランスの学校制度と日本の学校制度とでは歴史的経緯や立ち位置に違いがあるが、その点を留意しても現代日本社会を読み解くに大いなる助けになると思う。2013/06/30
-
![別冊フレンド 2021年3月号[2021年2月13日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0956691.jpg)
- 電子書籍
- 別冊フレンド 2021年3月号[202…