出版社内容情報
◎各種材料のぬれ、接触角、表面・界面張力、表面自由エネルギーなどデータを満載!!
編集(五十音順)
石井淑夫
鶴見大学教授
小石眞純
東京理科大学教授
角田光雄
文化女子大学教授
■ 総目次 ■
第1編 ぬれの基礎と評価法
第1章 ぬれ現象の基礎 【石井淑夫】
1. 接触角測定への期待
2. 接触角と表面張力の役割
3. 相性で決まる接触角
4. ぬれが問題になる現場
5. ぬれ、表面張力、接触角
6. 表面張力はぬれの基本
7. 液体の表面張力測定法
8. 静的表面張力と動的表面張力
9. 疎水面の水の状態 【上平恒】
9.1 疎水性水和の特性
9.2 疎水面の水の状態
第2章 ぬれの評価と測定技術 【石井淑夫】
1. ぬれの評価と測定技術
1.1 接触角は表面張力のバランスで決まる
1.2 接着仕事を求めるデュプレの式
1.3 浸漬仕事、湿潤ぬれ
1.4 拡張ぬれ仕事
1.5 ぬれの3タイプ
2. 接触角の測定
2.1 接触角の測定とその原理
2.2 静的な接触角の求め方
2.3 転落角
2.4 動的接触角の測定
第3章 接触角と及ぼす要因
1. 表面粗さ 【恩田智彦】
1.1 表面粗さとぬれの関係
1.2 ぬれの変化のメカニズム
1.3 表面粗さの構造
1.4 表面粗さの効果
2. 臨界表面張力 【石井淑夫】
3. 固体表面エネルギー
3.1 固体表面張力の分子間作用による展開
3.2 固体表面張力の解析
3.3 拡張フォーケスの式
3.5 その他の解析法
第4章 含浸 【榑松一彦】
1. 含浸
1.1 毛細管浸透
1.1.1 Poisuelleの式
1.1.2 Washburnの式
1.1.3 繊維層の毛細管上昇
1.1.4 Darcy則
1.1.5 Kozeny-Carmanの式
1.1.6 毛細管圧力差
1.1.7 Carman定数
1.2 気泡の生成と溶解
1.2.1 気泡の生成量
1.2.2 気泡の生成過程
1.2.3 気泡生成による未含浸部の気圧
1.2.4 気泡の消滅
2. 拡散吸着を伴う含浸
2.1 拡散吸着理論
2.1.1 拡散吸着速度式の導き方
2.1.2 拡散距離
2.1.3 拡散吸着確率
2.1.4 衝突結合エネルギー確率
2.2 拡散吸着を伴う含浸
2.2.1 反応確率エネルギー
2.2.2 電子親和力
2.2.3 界面張力の新定義
2.2.4 Youngの式の導出
2.2.5 毛細管径の標準偏差
2.2.6 拡散吸着を伴う含浸速度式
3. 界面張力と電子親和力
3.1 界面張力からの電子親和力
3.1.1 液体の界面張力と電子親和力
3.1.2 接触角と表面張力と電子親和力
3.2 含浸からの界面張力と電子親和力
3.2.1 液体の不織布への求心含浸における界面張力と電子親和力
3.2.2 減圧下での不織布への求心含浸における表面張力と電子親和力
3.2.3 γ-アミノプロピルトリエトキシシラン表面処理ポリエステル不織布の求心含
浸
3.3 粘度からの吸着確率と電子親和力
3.3.1 表面処理粒子からなる分散液の粘度の解析
第5章 ぬれの調節技術 【角田光雄】
1. 液の改質による親液化
1.1 液体の表面張力を固体の臨界表面張力以下にする
1.2 液体に界面活性剤などを添加することによる親液化と疎液化
1.2.1 白金、マイカ、シリカの界面活性剤水溶液によるぬれの例
1.2.2 ぬれの界面活性剤の吸着量との関係
1.2.3 ぬれと吸着膜の構造および濃度との関係
1.2.4 テフロンFEPの有機溶液によるぬれ
1.2.5 種なポリマーの液体および溶液によるぬれ
1.2.6 シリコンのコリンおよびアンモニア水溶液のぬれ
1.2.7 種々なアミンの水溶液による金属のぬれと水溶液のPHとの関係
1.2.8 セラミックスの溶融金属によるぬれ、溶融金属への添加剤の効果
2. 表面の改質による親液化と疎液化
2.1 高分子材料
2.1.1 基本的な考え方
(1)分散力相互作用を大きくする
(2)極性相互作用を大きくする
(3)表面粗さの調節
2.1.2 改質技術とぬれに対する効果
(1)化学的処理(薬品処理)とポリエチレン、テフロンFEPのぬれ
(2)グラフト化による親水化
?@ 処理の方式
?A グラフト化反応のエネルギーの種類
?B エネルギー付与の方式
1)液相光同時グラフト化処理
2)気相光照射グラフト化処理
(3)紫外線照射処理による親水化
1)ポリオレフィン
2)フッ素系
3)ポリエチレンテレフタレート(PET)
(4) プラズマ処理による親水化
1)プラズマによる表面処理の概念
?@ 高分子非生成プラズマ処理(プラズマ処理)
?A 高分子生成プラズマ処理(プラズマ重合)
?B プラズマジェット処理
2)グロー放電処理
(5) プラズマジェット処理による親水化
(6) プラズマ処理による疎水化
(7) 表面の塩素化によるゴムの親水化
(8) 高分子に添加剤を加えることによる親水化
(9) 添加剤による疎液化
2.1.3 その他の方法
(1) 表面エネルギーを大きくすることによる親水化
(2) 延伸処理による親液化
(3) 高分子の組成とぬれ
2.2 セラミックスと金属材料
2.2.1 セラミックスのぬれの基本
(1) 表面の静電気的な力とぬれ
?@ polarなvan der Waals力
?A non polarなvan der Waals力
?B 誘起効果による力
(2) 化学組成とぬれ
2.2.2 表面処理
2.2.3 金属のぬれ
第2編 水、有機溶媒、溶融固体による各種材料のぬれ
-評価法、測定条件、データとその意味およびぬれの調節-
第1章 無機材料(単体と化合物) 【角田光雄】
1. 炭素 C
1.1 固体炭素の基本構造
1.1.1 ダイヤモンド
1.1.2 黒鉛
1.1.3 カーボンブラック、活性炭
1.2 固体炭素の表面化学構造
1.3 ぬれの性質の表わし方
1.4 ぬれのデータ
1.4.1 黒鉛
1.4.2 石炭
1.4.3 PyrocarbonのK2ZrF6による処理とアルミニウムによるぬれ
1.4.4 Glassy Carbon(GC)
2. シリコン Si
2.1 シリコンの表面
2.2 ぬれのデータ
2.2.1 HF処理Si表面
2.2.2 B、Sb、PをドープしたSiとこれらをHF処理した表面のぬれ
2.2.3 オゾン水で処理したSiのぬれ
2.2.4 アモルファスシリコンa-Siの水によるぬれ
3. 硫黄 S
3.1 水に対するぬれ
3.2 臨界表面張力 γc
3.3 水中での炭化水素ヘプタンの接触角
第2章 溶融金属による固体金属(半導体も含む)のぬれ性 【野城清】
はじめに
1. 溶融金属/固体金属系のぬれ性の評価方法
2. 溶融金属による固体金属のぬれ性に影響する因子
3. 溶融金属による固体金属のぬれ性の報告例
3.1 溶融金属/Fe系
3.2 溶融金属/Cu系
3.3 溶融金属/耐熱金属(W、Re、Mo)系
3.4 溶融金属/半導体(Ge、Si)系
3.5 その他の系
3.6 溶融金属-固体金属間の接触角の計算
第3章 セラミックス材料のぬれ性 【野城清】
はじめに
1. 溶融金属によるセラミックスのぬれ性の報告例
1.1 反応のない系のぬれ性
1.2 反応のある系のぬれ性
2. 溶融金属によるセラミックスのぬれ性
2.1 溶融金属によるAl2O3のぬれ性
2.2 溶融金属による二酸化ケイ素(SiO2)のぬれ性
2.3 溶融金属によるジルコニア(ZrO2)のぬれ性
2.4 溶融金属による炭化ケイ素(SiC)のぬれ性
2.5 溶融金属による窒化ケイ素(Si3N4)のぬれ性
2.6 溶融金属による黒鉛、炭素、ダイヤモンドのぬれ性
2.7 溶融金属によるサイアロン(SIALON)のぬれ性
3. 溶融金属によるセラミックスのぬれ性の系統的取り扱いへのアプローチ
第4章 プラスチック材料 【石井淑夫】
1. 接触角
2. 臨界表面張力
3. 表面自由エネルギーの解析
3.1 Fowkesの式からの拡張
3.2 表面自由エネルギーのいろいろな解析法
3.3 酸-塩基相互作用による界面エネルギーの評価
3.4 高分子の表面エネルギーに関するそのほかのデータ
4. ジアルキルフタレートとステアリン酸
4.1 可塑剤、ジアルキルフタレートの表面張力
4.2 ステアリン酸の接触角
5. ポリアセチレン
5.1 ポリアセチレン
5.2 プラズマ重合アセチレン
6. ポリエチレン、ポリプロピレン、パラフィン
6.1 ポリエチレン上の水滴の接触角
6.2 水中における表面ポリエチレンに対するニトロベンゼンの接触角
6.3 極性液体で決められたプラスチックの臨界表面張力
6.4 エタノール水溶液を用いて決定した非分散力成分
6.5 固体表面のぬれに対する気水界面上の不溶性単分子膜の膜圧の効果
6.6 結合エネルギーに対する極性成分の測定
6.7 ある固体表面から他の表面への液体の移動
6.8 液体との相互作用に対するポリマーの表面の荷電の効果
6.9 クロム酸処理した低密度ポリエチレンから作られた膜の接触角
7. ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール
7.1 ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールおよびそのメチルエーテルの
同族体の表面張力-分子量依存性とメチル基効果
8. ポリエチレンテレフタレート
8.1 ポリエチレンテレフタレートに対する紫外線照射効果
9. ポリスチレン
9.1 ポリスチレンの炭化水素中における水の接触角
9.2 プラズマ処理により親水化されたポリスチレン表面の経時安定性
9.3 ポリマーの接触角に対する重合度等の依存性
10. ナイロン
10.1 ナイロン等の表面自由エネルギーの分散力成分と非分散力成分などの分析
10.2 固体/溶融液体界面の表面張力および接触角の決定
11. ポリメチルメタクリレートなど
11.1 溶媒を用いて作ったポリメチルメタクリレート膜の表面特性
12. ポリウレタン
12.1 ポリウレタンの表面の性質と血液適合性との関係
13. ゴム類
13.1 柔軟な材料上の接触角ヒステリシス
13.2 シンジオタクティック1,2-ポリブタジエン(PBD)の前進接触角
13.3 ブタジエン/酸素混合膜のプラズマ重合
13.4 シス-トランスブタジエンの表面酸化
13.5 シリル化したガラス表面上のポリイソブチレンの接触角
13.6 ポリイソブチレンの接触角
13.7 ポリブタジエンの空中におよび窒素雰囲気中での接触角の経時変化
14. ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ポリ塩酸ビニルなど
14.1 ポリビニルアルコールの臨界表面張力
14.2 親水性高分子の表面特性
15. 含フッ素高分子
15.1 含フッ素高分子の接触角
15.2 ポリテトラフルオロエチレンの表面張力、接触角、Girifalco-Goodの
相互作用パラメーターΦ
15.3 ポリテトラフルオロエチレン等の接触角など 15.4 ポリマーの表面張力の分析
15.5 温度依存性
15.6 ポリエチレン上のフッ化炭素のプラズマ重合
16. ポリジメチルシロキサンほか
16.1 ポリジメチルシロキサンの接触角
17. 生体高分子
17.1 接触角測定によって求められる生体高分子の表面化学的性質
18. 共重合体
18.1 エチレン-アクリル酸共重合体
18.2 エチレン-ビニル酸共重合体
18.3 ポリスチレンを一成分とするジブロック共重合体
18.4 スチレン-メチルメタクリレート共重合体
18.5 スチレン-2-ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体
18.6 4-ビニルピリジンをグラフトしたスチレン-ブタジエン-スチレン三ブロック共重合体
(SBS-g-VP)
18.7 テトラフルオロエチレン-クロロトリフルオロエチレン共重合体
18.8 ポリシロキサンをグラフトしたフッ素ポリマー
18.9 パーフルオロエーテルで修飾したシリコーン
18.10 ポリジメチルシロキサン-b-エチレンオキサイド多重ブロック共重合体
第5章 界面活性剤(湿潤剤) 【金子行裕】
1. 界面活性剤によるぬれ
1.1 表面張力の低下とぬれ
1.2 ぬれ評価法
1) 活性剤の効率
2) 活性剤の有効度
2. 動的表面張力によるぬれの評価
2.1 動的表面張力の測定法
2.2 活性剤水溶液の動的表面張力
2.3 動的表面張力とぬれ
3. 界面活性剤水溶液のぬれ性能
3.1 活性剤の分子構造および溶存状態とぬれ
1) 疎水基の影響
2) 親水基の影響
3) ポリエチレングリコール付加型非イオン活性剤 のエチレングリコール付加モル数の影響
4) 温度の影響
5) 塩濃度の影響
6) コサーファクタントの影響
7) pHの影響
3.2 代表的活性剤のぬれ性能
第6章 撥水撥油剤 【久保元伸・森田正道】
はじめに
1. 撥水撥油剤の材料
1.1 パーフルオロアルキル(Rf)基の製造方法
1.2 撥水撥油剤に用いられるフッ素材料の種類
1.2.1 Rf基含有アクリレート共重合体
1.2.2 Rf基含有リン酸エステル
1.2.3 Rf基含有ウレタン
1.3 製品の形態
1.4 処理方法
1.4.1 ディッピング
1.4.2 スプレー、泡加工
2. 理想系におけるぬれに関するデータと性能発現機構
2.1 接触角θ、臨界表面張力γc、表面自由エネルギーγS
2.2 各種撥水撥油剤のθ、γc、γS
2.3 Rf(メタ)アクリレートホモポリマーのγc、γS
3. 各種の実用的性能評価法とぬれに関するデータ
3.1 各種実用評価法
3.1.1 撥水性試験
3.1.2 撥油性試験
3.2 ぬれに関するデータ
3.2.1 モデル系
1) FAホモポリマーホの表面特性
2) FA/n-アルキルアクリレート共重合体の表面特性
3.2.2 商品としての撥水撥油剤
1)フッ素系撥水撥油剤の概要
2)フッ素系撥水撥油剤「ユニダイン」の性状と特徴
3)フッ素系撥水撥油剤「ユニダイン」の処方と性能
a) 新合繊用撥水撥油剤
b) 綿用超耐久型撥水撥油剤
c) SR剤
d) 防水スプレー「ノヴァテック」
e) 環境対応型撥水撥油剤
第3編 ぬれと応用技術
第1章 印刷
第2章 色材・塗装
第3章 接着・粘着
第4章 接合
第5章 トライボロジー
第6章 メカノケミストリー
第7章 めっき
第8章 エレクトロニクス
第9章 インクジェットプリンタと「ぬれ」
第10章 自動車用フッ素樹脂塗装と撥水ウィンドガラス
第11章 光励起反応によるぬれの制御
第12章 粉末冶金
第13章 食品
第14章 化粧品
第15章 医薬品
第16章 医用材料
第17章 防曇性
第18章 ワックス
第19章 着雪・着氷
第20章 繊維・不織布・紙
第21章 植物葉面のぬれ現象
第22章 セメント
第23章 ぬれの測定とその応用
■ 執筆者一覧 (執筆順)
石井 淑夫
鶴見大学 歯学部 化学研究室 教授
上平 恒
(前)北海道大学 理学部 高分子学科 教授
恩田 智彦
花王?? ヘルスケア第一研究所 第2研究室 主任研究員
榑松 一彦
(有)一数厚木 取締役社長
角田 光雄
文化女子大学 服装学部 教授
野城 清
大阪大学 接合科学研究所 教授
金子 行裕
ライオン?? 研究開発本部 物質科学センター 主任研究員
久保 元伸
ダイキン工業?? 化学事業部 副事業部長
森田 正道
ダイキン工業?? 化学事業部 第2研究開発部 主任研究員
高尾 道生
東京インキ?? 取締役 第一生産本部 インキ技術部長
小石 眞純
東京理科大学 総合研究所 界面科学研究部門 教授
柳原 榮一
神奈川県技術アドバイザー (元)?鞄?立製作所
武藤 睦治
長岡技術科学大学 機械系 教授
森 誠之
岩手大学 工学部 応用化学科 教授
神戸 徳蔵
東京都鍍金工業組合 高等職業訓練校 教頭
柳沢 寛
技術研究組合 超先端電子技術開発機構(ASET)
環境プロセス技術研究室 室長
三浦 和久
国立津山工業高等専門学校 一般科目 化学担当 教授
下村 明彦
キヤノン?? 記録技術研究所 第3研究部 第31研究室 室長
渡邉健太郎
日産自動車?? 材料技術部 車両材料技術グループ 上級技師
渡部 俊也
東京大学 先端科学技術研究センター 教授
橋本 和仁
東京大学 先端科学技術研究センター 教授
加藤 欽之
?潟Aトミックス 代表取締役
三浦 靖
岩手大学 農学部 農業生命科学科 食品健康科学講座 助教授
佐藤 孝俊
(前)日本大学 薬学部 薬品物理化学研究室 教授
筏 義人
鈴鹿医療科学大学 医用工学部 教授
福山 紅陽
協和界面科学?? 技術部
舩越 宣博
NTTアドバンステクノロジ?? 先端技術事業本部
機能材料技術部 超はっ水グループ 主幹部長
多賀谷久子
滋賀大学 教育学部 教授
渡部 忠一
アグロカネショウ?梶@研究部 部長
田中 勲
清水建設?? 技術研究所 エンジニアリング研究開発部
副主任研究員
佐々木信博
?潟激Xカ 取締相談役
-

- 電子書籍
- 週刊GIRLS-PEDIA022 ぷに…
-

- 電子書籍
- 異世界婿入り放浪記【タテヨミ】第34話…
-
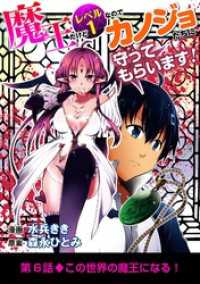
- 電子書籍
- 魔王だけどレベル1なのでカノジョたちに…
-
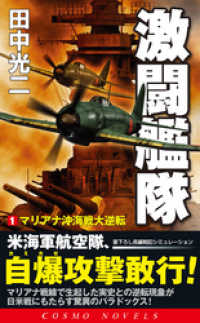
- 電子書籍
- 激闘艦隊(1)マリアナ沖海戦大逆転 コ…
-
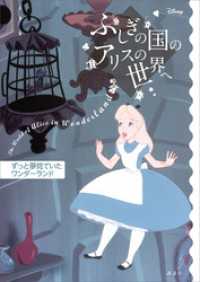
- 電子書籍
- ディズニー ふしぎの国のアリスの世界へ…



