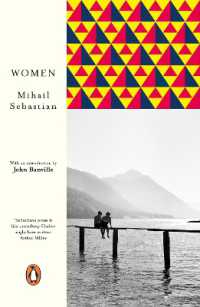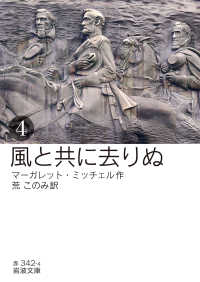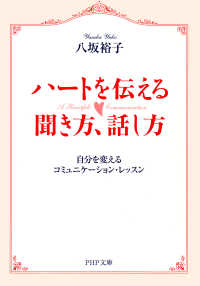内容説明
核の脅威、資源の枯渇、気候不順、経済格差の拡大は人間社会の存続を脅かす要因で、SDGsはこれらへの対応を指標化した。その達成には経済の成長から社会の成熟へと考え方の転換が必要。人口や物的生産の増加がなくても、人間社会の進化をめざす社会であり、物質文明の高度な段階にあり、平和で人間の特質にそった社会である。その特質は、第1に人は苦労しないで得たものは大事にしない、第2に人は逆境に強いが安楽の境地では弱い、そして第3に人は十人十色で多様である。多様な文化が共存せねばならない。質の高い生活を実現するには、富を幸福に変換する能力としての文化力を磨くこと。日本の伝統的文化を見直すことが文化力を高めるのに貢献する。家族やコミュニティは、従来のしきたりや制度にとらわれない多様な形態であること。評判のピケティ『21世紀の資本』を批判した、「反・ピケティ論」を収録!
目次
プロローグ 人類存亡の危機
第1章 デニス・ガボールの「成熟社会」
第2章 多様な生活文化と複数のユートピア
第3章 日本の文化と文化力
第4章 成熟社会における家族とコミュニティおよび女性
エピローグ 文化資本と文化力
著者等紹介
駄田井正[ダタイタダシ]
1944年、大阪府堺市生まれ。大阪府立大学(現大阪公立大学)卒業。1970年に久留米大学に赴任。商学部講師・助教授・教授を経て、1994年に新設の経済学部に移籍する。経済学部長(1998~2002年)、大学院比較文化学科長(2002~2004年)など歴任。2014年に退職、久留米大学名誉教授。経済学博士。もともとは理論経済学専攻であったが、オーソドックスな経済学に疑問を持ち、文化経済学に転向する。経済学部に文化経済学科の設置(2002年開設)に尽力する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。