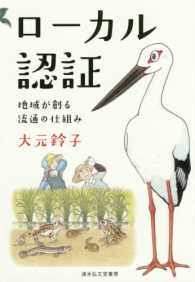出版社内容情報
消費者の嗜好変化に即応した次世代パッケージ仕様決定の実務指針
清涼飲料・中食・医療食をはじめ期待の市場・製品開発情報を満載
■ 主要構成
第1部 海外でいま何が起きているか
第2部 包装材料・包装システムの最先端と今後のパッケージ戦略
第3部 安全・おいしさ・機能を重視した包装食品の開発
--------------------------------------------------------------------------------
【発刊にあたって】
世界的な食中毒菌の蔓延、BSE(狂牛病)と鳥ウイルスの発生など、今こそ、消費者が「食品の安全・おいしさ・食品の機能性」を求めている時期はありません。一方で高齢化社会に向けて「安全でおいしい機能性食品」が求められています。
この本は、このような時代に対応できる「消費者志向の食品包装戦略と技術」というテーマでまとめられたものであり、食品製造会社や包装材料・包装システム、食品流通業界の実務者・開発者に役立つものと思われます。
ここにきて、清涼飲料水をはじめ食品のすべての分野で包装が大きく変化してきています。消費者の嗜好変化に即応した次世代パッケージの導入が進められており、包装設計が食品の機能実現と差別化の重要な要素になっています。一方、容器包装リサイクル法の施行に伴い、食品産業各社のリサイクル費用が確実に増大しており、そのコストを低減させる包材開発が急務となっております。
そこで、私たちは食品包装に携わっている専門家とともに、次の3つの視点から食品包装をめぐる世界の動きを分析し、今後の開発シナリオを提示したいと思います。
第1部「海外でいま何が起きているか」は、世界の食品包装ビジネスの最前線で活躍されている専門家の生々しい実態報告です。食品包装の新しい息吹とメガトレンド、様々なビジネスチャンスを感じとることが出来ます。
第2部「包装材料・包装システムの最先端と今後のパッケージ戦略」は、Kコート代替・生分解性・酸素吸収性・バリア性包材等、注目の包装材料と包装システム開発の詳細と開発技術の方向が示されています。
第3部「安全・おいしさ・機能を重視した包装食品の開発」では、成長著しい中食市場、医療食・介護食分野での食品開発の実状と包装設計、食品包装のユニバーサルデザインの実際等、豊富な事例を交えて簡潔に解説致しました。
私たちは永年に亘り「食品と衛生・包装システム」の見地から、食品包装の最先端技術に関わってきました。本書は必ずや食品産業業界の皆様に有益な戦略視点と最新の実務情報を提供出来ることを確信し、ご活用をお薦めする次第です。
編集委員 横山理雄・葛良忠彦・難波勝
--------------------------------------------------------------------------------
■ 内容目次
第1部 海外でいま何が起きているか
(1) 欧州の食品包装事情<井坂 勤>
プラスチックの基盤である石油化学工業のシェア変化
伝統的な硬包材の低迷
欧州における最近の動向―最近の飲食品包装のメガトレンド
3.1 包装の高機能化・多機能化の技術動向
3.2 シェルフライフの延長
3.2.1 MA包装
3.2.2 生鮮野菜包装
3.2.3 MicVac社の新方式
3.2.4 アクティブパッケージングの開発
スマートパッケージング
4.1 電子レンジ包装
4.1.1 ベント機能バルブ装着
4.1.2 フィルムスリット加工によるベントバルブ機能包装
4.1.3 ベント孔を設けた蓋材
徐放性バルブ機能包装
利便性包装
6.1 易開封包装
6.1.1 易カット包装
6.1.2 曲線開封包装
6.2 易開封/再封性兼備
6.2.1 ジッパー付包装
6.2.2 スライダー付包装
6.2.3 Pelaseal II
6.3 メンブランパウチ
特殊技術による新包装システム
7.1 シートからのFFSボトル
7.2 自己冷却包装
スナック食品包装
環境対応包装
9.1 シュリンクラベルの動向
9.2 生分解性フィルムの展開状況
9.3 非塩素系バリアフィルム
9.4 100%モノマテリアル
9.5 複合多層フィルムによる脱トレー包装
9.6 輸送包装の合理化
今後の展望
(2) 米国の食品包装事情<有田 俊雄>
食品包装を変化させる4つのドライビングフォース
変化する米国消費者のライフスタイル
消費者に支持される主力商品のリニューアル
3.1 欧米で成長期を迎えたジッパー袋
3.2 軟包装の牽引車の一つ、レトルトペットフード
3.3 パウチはPETボトルの次の競合相手
3.4 缶詰からレトルトパウチへ、大胆な製品リニューアル
3.5 片手で食べられるスティックヨーグルト
3.6 フルシュリンクラベルで世界をリードするフジシール
3.7 新しいカテゴリー、“ダッシュボード・ディナー”
(3) 中国・韓国の食品包装事情<西野 甫>
中国の食品包装事情
1.1 中国の経済状況(2003年ベース)
1.2 中国のプラスチック包装材料の動き
1.2.1 中国で生産されている主な食品包装材料
1.2.2 中国の食品包装材料関連企業の動き
1.2.3 日本の食品包装フィルム企業の進出
1.3 発展地域での包装食品市場の現況
1.4 発展地域での包装食品とその包装
1.4.1 菓子・パン、調味料、乾燥製品などの包装
1.4.2 乳・乳製品などの包装
1.4.3 生鮮野菜、果物などの包装食品
1.4.4 生鮮魚介類などの水産物包装
1.4.5 加熱・冷凍食品などの包装食品
1.4.6 トマトケチャップ、ソース、醤油、リンゴジャム、ジュースなどの酸度の高い包装食品
1.4.7 食肉の包装
1.4.8 食肉加工品の包装
1.4.9 レトルト食品
韓国の食品包装事情
2.1 韓国の食品産業
2.2 韓国のプラスチック包装材料の動き
2.3 韓国市場での包装食品の動き
2.4 韓国レトルト食品とその包装
(4) 開発途上国の食品包装事情<田中 好雄>
産業基盤の比較
1.1 世界の地域経済統合の位置付け
1.2 メルコスール、アセアンおよびアフリカ経済圏の比較
南米の包装事情
2.1 包装材料の加工技術
2.2 食品産業における包装の利用
2.3 食品包装の市場流通の例
2.3.1 輸送包装
2.3.2 消費者包装
2.4 南米の食品包装の特徴
2.5 その他のメルコスール加盟国の包装・物流の状況
2.5.1 パラグアイ
2.5.2 アルゼンチン
アセアンの包装事情
3.1 包装材料の加工技術
3.2 食品産業への利用
3.2.1 ミネラルウォーター
3.2.2 魚醤
3.2.3 冷凍エビ(ブラックタイガー)
3.2.4 ビール、炭酸飲料
3.3 食品包装の市場流通の例
3.3.1 魚醤、豆乳(ガラスびん、アルミ缶)
3.3.2 ジュース類(テトラブリック)
3.3.3 ミネラルウォーター(PETボトル)
3.3.4 クラッカー、フルーツキャンディー(アルミ蒸着複合パウチ・カートン)
3.4 タイの食品流通事情
アフリカ(タンザニア)の包装事情
4.1 包装材料の加工技術
4.2 食品産業における包装の利用
4.2.1 紅茶
4.2.2 コーヒー
4.2.3 ヨーグルト
4.3 食品包装の市場流通の例
第2部 包装材料・包装システムの最先端と今後のパッケージ戦略
(1) 塩素系代替包材の開発動向<村内 一夫>
塩素系包装材料に関するガイドライン
塩素系容器包装材料の種類とその代替材料の開発動向(概要)
塩素系代替家庭用ラップフィルムの開発動向
塩素系代替業務用ストレッチフィルムの開発動向
塩素系代替シュリンクラベル用フィルムの開発動向
塩素系代替PTP包装用フィルムの開発動向
(2) 生分解性包材の開発動向<葛良 忠彦>
生分解性プラスチックの行政・法規上の取扱いの現状
1.1 容器包装リサイクル法での取扱い
1.2 食品廃棄物リサイクル法での取扱い
1.3 グリーン購入法での取扱い
試験法標準化の動向
生分解性プラスチックの開発状況
3.1 微生物生産系脂肪族ポリエステル
3.2 ポリ乳酸(PLA)
3.3 ポリカプロラクトン(PCL)
3.4 ジオール・カルボン酸系脂肪族ポリエステル
3.5 芳香族・脂肪族系ポリエステル
3.6 ポリビニルアルコール
3.7 天然物系グリーンプラ
生分解性プラスチックの用途
食品容器包装への用途展開
(3) 酸素吸収包材料の開発動向<葛良 忠彦>
酸素吸収包装とは
脱酸素・酸素吸収包装の原理と技法
脱酸素剤・酸素吸収性包材開発の歴史
酸素吸収性材料の種類とその酸素吸収機構
4.1 還元鉄系酸素吸収剤
4.2 アスコルビン酸系酸素吸収剤
4.3 MXD6ナイロン・コバルト塩系酸素吸収剤
4.4 共役二重結合ポリマー系酸素吸収剤
4.5 シクロヘキセン基含有ポリマー系酸素吸収剤
各種酸素吸収材料の特許出願状況
5.1 還元鉄系酸素吸収剤
5.2 アスコルビン酸系酸素吸収剤
5.3 遷移金属系酸化触媒を含む酸素吸収剤
5.4 エチレン性不飽和炭化水素系酸素吸収剤
5.5 シクロヘキセン基含有酸素吸収剤
脱酸素剤封入包装の適用状況
6.1 生および半生菓子類
6.2 畜産製品
6.3 水産製品
6.4 米飯、切り餅、めん類
酸素吸収包材の適用状況
7.1 酸素吸収性トレーによる無菌米飯包装
7.2 湯殺菌・レトルト食品包装
7.3 パウチによる医薬品包装
7.4 酸素吸収性キャップ
7.5 飲料用酸素吸収性ボトル
7.5.1 海外における酸素吸収性PETボトルのビールへの展開
7.5.2 日本における酸素吸収性PETボトルのホット販売用飲料への展開
調理食品用酸素吸収性容器の将来展望
(4) バリア性包材の開発動向<葛良 忠彦>
ガスバリア包装の必要性
ガスバリア包装の技術動向
ガスバリア・フィルムの開発状況
3.1 EVOH系包材
3.2 PVA/ビニロン系包材
3.3 ナイロン系包材
3.4 アクリル酸系樹脂コートフィルム
3.5 シリカ・アルミナコートフィルム
3.6 ナノコンポジット材料
ガスバリア・ボトルの開発状況
4.1 ポリオレフィン系多層ボトル・チューブ
4.2 ポリエステル系ガスバリア・ボトル
4.2.1 ガスバリアコーティングPETボトル
4.2.2 ガスバリア多層PETボトル
4.2.3 PENボトル
4.2.4 ガスバリア耐圧PETボトル
(5) 包装用新規樹脂包材の開発動向<葛良 忠彦>
熱可塑性樹脂の包材としての位置
ポリオレフィン樹脂の製造技術動向
各種ポリエチレン樹脂とその用途展開
3.1 高級α―オレフィン系LLDPE
3.2 メタロセンHDPE
3.3 メタロセンLLDPE
3.4 プラストマー・エラストマー
3.5 メタロセンPEの包材への用途展開
3.5.1 シーラント
3.5.2 液体包装用、重袋用フィルム
3.5.3 ストレッチフィルム
3.5.4 共押出フィルム
3.5.5 ブロー成形品
メタロセン・ポリプロピレン
環状オレフィンコポリマー(COC)
(6) レトルト殺菌システムの開発動向<五領田 俊雄>
競争の制約要素
競争軸の変遷
2.1 温度制御と殺菌の完全性
2.2 圧力制御
2.2.1 容器の破損防止から変形防止へ
2.2.2 圧力制御競争は終了したか
2.3 加熱量と食品の品質
2.3.1 高温短時間殺菌の限界
2.3.2 レトルト・プロファイルの最適化と経験則
2.4 酸素量と食品の品質
2.5 便利さ
2.5.1 釜への出し入れ
2.5.2 連続式とバッチ式
2.6 殺菌された内容物の品質
2.7 コスト競争
将来の競争軸
競合技術
(7) 無菌充填包装システムの開発動向<横山 理雄>
食品の無菌充填包装機とその包装システム
1.1 紙容器詰め無菌充填包装機とその包装システム
1.2 ガラスびん容器詰め無菌充填包装とその包装システム
1.3 金属缶容器詰め無菌充填包装機とその包装システム
1.4 PETボトル容器詰め無菌充填包装機とその包装システム
1.5 プラスチック包装材料詰め無菌充填包装機とその包装システム
1.5.1 プラスチック軟包材詰め無菌充填包装機
1.5.2 プラスチックカップ詰め無菌充填包装機
業務用食品の無菌充填包装機とその包装システム
2.1 外食産業向け食品の無菌充填包装機とその包装システム
2.2 食品工場向け食品の無菌充填包装機とその包装システム
今後本格的に使われるようになる無菌充填包装システム
第3部 安全・おいしさ・機能を重視した包装食品の開発
(1) 安全・おいしさ・簡便性を重視した包装食品の開発<牧野 収孝/難波 勝>
安全性について
1.1 安全意識の高まり
1.2 安全を守るための法規
1.3 加工食品において安全を損なう事故原因
1.3.1 主として容器包装に起因する事故例
1.3.2 容器包装への表示で安全上問題となるケース
1.3.3 容器、材質について
1.3.4 賞味期限(品質保持期限、消費期限)の決め方について
おいしさについて
2.1 おいしさの保全
2.2 おいしさを保全する食品包装の実施例
2.2.1 パウチ
2.2.2 アセプティックカップ
2.2.3 アセプティック紙パック
2.2.4 缶
簡便性
3.1 手軽さ 3.2 ユニバーサルデザイン
3.3 ユニバーサルデザイン製品例
最新の包装材料
4.1 プラスチックボトル
4.2 TMC樹脂コート超軽量ビン(東洋ガラス)
4.3 機能性ダンボール(トーカンパッケージングシステム)
(2) 中食市場に向けた食品開発―限定品への挑戦<小林 憲一郎>
限定品・限定サービスとの出会い
限定品・限定サービスの背景
コンビニエンスストアと限定品
限定品の特徴・定義
限定品の種類
中食市場の食品に関する一般的情報
6.1 惣菜の購入基準
6.2 惣菜のRFM分析
6.3 惣菜の購入単価
(3) 中食市場に向けた包装容器開発<多治見 昭典>
中食市場の規模と容器の使用量
中食容器に必要な機能
2.1 ディスプレー効果
2.2 密閉性
2.3 防曇性
2.4 耐熱性・耐油性・透明性・深絞り性
中食容器に使用される代表的な樹脂
3.1 A-PET(非晶性ポリエチレンテレフタレート)
3.2 OPS(2軸延伸ポリスチレン)
3.3 PSP(ポリスチレンペーパー)
3.4 HiPS(耐衝撃性ポリスチレン)
3.5 PPフィラー(無機物充填ポリプロピレン)
3.6 C-PET(結晶性ポリエチレンテレフタレート)
3.7 パルプモールド
中食容器の成形方法
4.1 真空成形
4.2 間接加熱圧空成形
4.3 熱盤圧空成形
金型について
最近注目されている中食と容器
今後の中食容器開発の方向性
(4) 医療食・介護食向け食品開発
1.キユーピーの取組み<浜千代 善規>
介護用食品の商品設計
高齢者の摂食障害
2.1 摂食障害
2.2 咀嚼障害
2.3 嚥下障害
介護用食品に求められる形状、物性
介護用食品に求められる栄養機能
介護用食品の種類と特徴
摂食機能レベルに応じた介護用食品の区分
介護用食品に携わる食品企業の役割
2.明治乳業の取組み<有馬 裕史/村尾 周久>
医療・介護の場における栄養補給と食事
1.1 栄養補給の分類
1.2 経管栄養(流動食)
高齢者用食品の開発と商品展開
2.1 流動食の高齢者用食品への展開
2.2 流動食の包装形態
介護食品分野での取組み
3.1 介護食製品の分類と機能
3.2 「元気!」シリーズ製品の栄養設計と特長
3.2.1 栄養デザート(アイスで元気!)
3.2.2 栄養デザート(プリンで元気!、あずきムース)
3.2.3 栄養調整飲料(からだに元気!)
3.2.4 栄養調整スープ(スープで元気!)
3.3 “食感調整食品”の物性設計および特長
3.3.1 「やわらかカット食」
3.3.2 「カットフルーツゼリー」
3.3.3 「やわらかゼリー」
3.3.4 「トロメイク」(とろみ調整食品)
3.4 介護食のレオロジー評価
3.5 介護食の臨床評価例
(5) 医療食・介護食向け包装開発―流動食容器に対応したカートカン開発<島村 悦夫>
一般食品と医療食・介護食の包装について
1.1 医療食・介護食に使用される包装技法
1.2 レトルト殺菌方式と無菌充填方式について
流動食に対応したカートカン開発
2.1 カートカンとは
2.1.1 容器の基本構成
2.1.2 カートカンの特徴
2.1.3 カートカン成型システム
2.1.4 カートカン無菌充填システム
2.2 カートカン入り流動食
2.2.1 流動食の包装形態
2.2.2 タブ開封性の向上
2.2.3 流動食に合わせた容器サイズ
(6) 食品包装容器のユニバーサルデザインとは<高村 康正>
容器・包装には使いやすさ分かりやすさが求められている
容器・包装を使用する様々な人々
容器・包装設計におけるユニバーサルデザイン
3.1 ユニバーサルデザインのための3つの視点
3.2 容器・包装のプロダクトライフサイクルと3つの視点
3.3 消費者の使用場面を対象とした容器・包装の使用場面でのユニバーサルデザイン要件
容器・包装の構造面での具体的なユニバーサルデザインとは
4.1 購入場面
4.2 使用場面
4.3 保管場面(使用前保管と使用中保管)
4.4 廃棄場面
容器・包装の表示・デザイン面での具体的なユニバーサルデザインとは
5.1 購入場面
5.2 使用場面
容器・包装のユニバーサルデザイン設計の推進
(7) 電子レンジ対応包装食品の開発<牧野 収孝/難波 勝>
電子レンジの歴史
電子レンジの加熱原理
電子レンジ加熱の特徴
電子レンジ対応包装食品の容器に必要とされる特性
電子レンジ対応包装食品の実際例
今後の展望