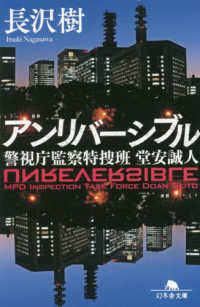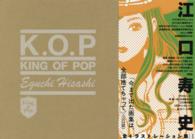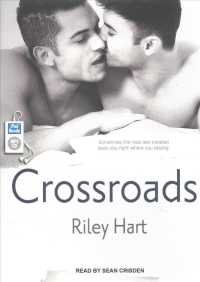出版社内容情報
現場必携:微生物検査における簡便迅速測定法導入の最適入門書
食品細菌分野における簡便迅速法の開発は、食品産業界から強い要望があったにも拘わら
ず、臨床細菌分野よりも大きく後れを取った。昭和60年に国内で初めて「食品微生物検査の簡
易化、自動化、迅速化」 (春田三佐夫ほか編集)がサイエンスフォーラムから出版され、この
分野の先駆けとなった。その時代に開発され、その当時に記載されたスパイラルプレーティン
グ法、ストマッカー、 メンブレンフィルター法などは、その後の改良により現在は日常の検査法
として広く導入されている。同書序文には「食品微生物検査の機械化、自動化、 迅速化の進
展にいささかでも資するところがあれば幸いである。」と結ばれているが、その後の15年間に
おいて食品微生物検査の簡便迅速化は目覚ましい進展を遂げてきた。 特に寒天培地の準備
が必要ないペトリフィルム、シート状培地、コンパクトドライが開発・市販化され小規模な検査
室でも食品細菌検査が容易となってきた。 寒天培地上の集落の観察は基質の分解に伴う培
地のpHの変化で判定されてきたが、菌属や菌種に特異な酵素を簡易に検出する合成基質培
地が開発され、 従来の鑑別培地より一層性能が高まり細菌の鑑別が可能となってきた。 さら
に、免疫学的方法や遺伝子診断法が活用され、これまでの常識では達成できなかった技術レ
ベルまで到達している。
今回の出版では、前回よりは食品微生物分野における簡便迅速な検査法が飛躍的に進展し、より充実した内容となっている。また、現場での活用が重要であることから、 新たな試みとして食品製造検査室での活用法も解説した。現時点ではまだ満点でない技術も含まれているが、近い将来には完成した検査技術になることを切望し、 あえて紹介している。また、本書に収録できなかった検査法もすでに数多く報告されているが、今後の書いて番で逐次細くしていき、食品微生物分野の簡便迅速検査法を集大成し、現場の技術者に受け入れられる資料としていきたい。
検査指針に拘泥せず、食品微生物検査技術として容認でき、食品の微生物学的安全性の評価に導入できる簡便迅速検査法は、自主衛生管理として勝つようしていくべきである。 その際に本書が少しでもお役に立てることを切望する。
(本書 「序」より抜粋)
■執筆者(執筆順・敬称略、役職等は発刊当時のものです)
伊藤 武
財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター所長
佐藤 順
日本コカ・コーラ株式会社クオリティマネジメント品質規格担当マネジャー
山本 茂貴
国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部部長
蓜島 義隆
守山乳業株式会社品質管理課課長
廣田 春子
守山乳業株式会社品質管理課
高橋 寿洋
サッポロビール株式会社ビール事業本部製造部課長代理
坂根 香
伊藤ハム株式会社生産事業本部技術部部長
大橋 英治
日本水産株式会社食品分析センター所長
丸山 純一
株式会社ニチレイ品質保証部検査センター所長
中川 弘
財団法人東京顕微鏡院研究開発室技術部長
守山 隆敏
スリーエム ヘルスケア株式会社メディカル製品事業部一般市場製品販売部産業機能材室長
牛山 正志
チッソ株式会社横浜研究所主幹
水落 慎吾
日水製薬株式会社診断薬研究部テクニカルマネージャー
仲西 寿男
財団法人日本食品分析センター大阪支所学術顧問
木股 裕子
神戸市環境保健研究所細菌部
山縣 尚
日本ビオメリュー株式会社産業事業本部
田代 義和
松下精工株式会社バイオセンシング事業プロジェクト開発Ⅰチームチーフマネージャー
島北 寛仁
松下精工株式会社バイオセンシング事業プロジェクト開発Ⅰチーム
畑山 勝浩
日本ミリポア株式会社バイオファーマシューティカル事業本部
五十嵐 俊教
キッコーマン株式会社研究本部第3研究部研究員
長谷川 敦子
フォス・ジャパン株式会社営業部
小川 廣幸
マイクロバイオ株式会社代表取締役
高橋 克忠
けいはんな文化学術協会微生物計測システム研究所理事長
向井 博之
タカラバイオ株式会社DNA機能解析センターリサーチフェロー
三宅 一恵
タカラバイオ株式会社DNA機能解析センター研究員
藤井 聖士
タカラバイオ株式会社DNA機能解析センター研究員
中筋 愛
タカラバイオ株式会社DNA機能解析センター研究員
野上 尊子
オルガノ株式会社機能商品事業本部食品事業部技術開発室課長代理
金子 精一
神奈川県立栄養短期大学食品衛生研究室教授
後藤 慶一
三井農林株式会社食品総合研究所微生物・分析研究グループリーダー
吉田 信一郎
財団法人日本食品分析センター多摩研究所微生物研究課課長
間處 博子
株式会社フードサプライジャスコ兵庫事業所品質管理室課長
■ 主要構成
第1章 簡便迅速測定法の導入ガイダンス
第1節 ここまできた微生物の簡便迅速測定法
第2節 簡便迅速測定法の現場での活用法
第2章 食品別にみる簡便迅速測定法の現場活用のポイント
第3章 微生物検査の簡便化技術
第4章 微生物技術の迅速化技術
第5章 微生物同定の簡便迅速化技術
付属資料
1 簡便迅速測定法で使用する統計的手法
2 工場における簡便迅速法導入プロセスの具体例-食品原材料の場合
■ 内容目次
序<伊藤 武>
編集にあたって<佐藤 順>
第1章 簡便迅速測定法の導入ガイダンス
第1節 ここまできた微生物の簡便迅速測定法<山本茂貴>
1.細菌検査の簡便化技術
2.細菌検査の迅速化技術
第2節 簡便迅速測定法の現場での活用法<伊藤 武>
1.食品の細菌検査の意義
2.安全性と品質確保のための検査法
3.検査対象となる微生物
4.汚染指標菌の迅速検査法
5.簡便迅速法による病原菌の検査
6.清浄度と迅速細菌検査法
第2章 食品別にみる簡便迅速測定法の現場活用のポイント
第1節 清涼飲料水<佐藤 順>
1.清涼飲料水の製造現場における微生物検査の現状
2.清涼飲料水の微生物検査における簡便迅速測定法導入の現状
3.今後望まれる簡便迅速測定法とは
第2節 牛乳・乳製品<蓜島義隆/廣田春子>
1.乳製品における微生物検査法(従来法)の現状
2.ATP法の導入
2.1 ATP法の選定
2.2 ATP法の検出限界
2.3 ATP法基準値の設定
2.4 ATP測定方法
3.乳業における簡便迅速法の今後について
第3節 アルコール飲料<高橋寿洋>
1.工場における微生物検査(従来法)の現状
2.どのような簡便法・迅速法が工場で採用されているか
2.1 MicroStar-RMDS-SPSの開発
2.2 RMDS-SPSの検出感度
2.3 RMDS-SPSの実用化の現状
2.4 実用化後の安定的運用のための施策
3.今後どのような測定法が望まれるか
第4節 食肉製品<坂根 香>
1.食肉および食肉加工品の微生物検査方法の現状
2.食肉および食肉加工品の迅速微生物検査法
2.1 検査用試料の調製
2.2 食肉の迅速微生物検査
2.3 食肉加工品の迅速微生物検査
第5節 水産練り製品<大橋英治>
1.現状の検査法
2.合成酵素基質培地を用いた大腸菌群測定検討
2.1 練り製品での検査法
2.2 結果
2.3 考察
第6節 冷凍食品<丸山純一>
1.自主検査に求められる要素
1.1 冷凍食品の成分規格
1.2 公定法と自主衛生検査の目的
2.一般生菌数検査の簡便迅速化
3.大腸菌検査の簡便迅速化
4.サルモネラ検査の簡便迅速化
5.腸炎ビブリオ検査の簡便迅速化
6.今後の課題
第3章 微生物検査の簡便化技術
第1節 スパイラルプレーティング法<中川 弘>
1.原理
2.測定方法
2.1 寒天平板培地の準備
2.2 試料の調製
2.3 測定手順
2.4 細菌数の測定
3.応用例
4.使用に際しての注意点
第2節 乾燥培地法
1)ペトリフィルム法<守山隆敏>
1.種類と構造・原理
2.使用手順
2.1 ペトリフィルムACプレート操作手順
2.2 ペトリフィルムCC/EC/EB/RCCプレート操作手順
2.3 判定方法と培養条件
3.使用用途と応用例
3.1 乳酸菌測定への応用
3.2 空中落下菌および直接スタンプ法
4.使用に際しての注意点
5.特徴
5.1 ペトリフィルムの有用性
5.2 承認関係
2)シート状培地法:サニ太くん<牛山正志>
1.測定原理
2.測定方法
3.応用例
3.1 一般生菌用
3.2 大腸菌群用
3.3 真菌用
3.4 落下菌
3.5 食品加工工場における検査例
3.6 手指検査
4.使用に際しての注意点
3)コンパクトドライ法<水落慎吾>
1.測定原理および特徴
1.1 測定原理
1.2 特徴
2.測定方法
2.1 操作方法
2.2 種類
3.応用例
4.使用に際しての注意点
第3節 合成酵素基質培地法<仲西寿男/木股裕子>
1.歴史
2.細菌検査の簡便化
2.1 合成酵素基質培地法の反応原理
2.2 主な発色(発光)物質誘導体とその特徴
3.汚染指標菌検査への応用
3.1 食品衛生検査に用いられる酵素基質培地法
3.2 上水試験方法で採用された酵素基質培地法
4.病原菌検査への応用
4.1 E.coliO157:H7
4.2 Salmonella
4.3 Shigella
4.4 Listeria
4.5 酵母様真菌
4.6 その他
5.酵素基質培地法の制約と特殊性
第4章 微生物検査の迅速化技術
自動生菌数測定
第1節 インピーダンス法<山縣 尚>
1.インピーダンステクノロジーの原理
2.バクトメーターシステムの構成
3.バクトメーターの特徴
4.バクトメーターの測定条件の設定
5.検出時間
6.応用例
6.1 食品検査における一般的使用例
6.2 生菌数の測定
6.3 品質保持期限の設定
第2節 濾過法
1)蛍光染色法:バイオプローラ<田代義和/島北寛仁>
1.測定原理
2.検査キットおよび測定方法
2.1 検査キット
2.2 測定方法
3.応用例
4.使用に際しての注意点
2)MicroStar-RMDS法<畑山勝浩>
1.測定原理
2.測定方法
3.応用例
4.使用に際しての注意点
3)MicroStain法<畑山勝浩>
1.測定原理
2.測定方法
3.牛乳での応用例
4.使用に際しての注意点
第3節 ATP法<五十嵐俊教>
1.菌数の推定
2.無菌製品の検査
3.測定原理
4.測定方法
4.1 基本的な測定方法
4.2 前処理を行う測定方法
5.応用例
5.1 果汁飲料での無菌性確認試験方法
5.2 遠心分離による菌の濃縮
6.使用に際しての注意点
第4節 Micro-Foss法<長谷川敦子>
1.測定原理
2.測定方法
3.応用例
3.1 汚染モデルの作成
3.2 測定
3.3 検量線の登録
3.4 検量線の評価
4.使用に際しての注意点
第5節 センシメディア法<小川廣幸>
1.測定原理
1.1 検出要素とセンサー
1.2 採用している概念
2.測定方法
3.応用例
4.使用に際しての注意点
第6節 ディジタル顕微鏡法<小川廣幸>
1.測定原理
1.1 システム構成
1.2 ディジタル顕微鏡の検出機構
1.3 培養機構
1.4 コロニー計測ソフトウェア
2.測定方法
3.応用例
4.使用に際しての注意点
第7節 ミクロカロリメトリー<高橋克忠>
1.測定原理と測定方法 1.1 装置と計測シグナル 1.2 抗微生物作用の解析
2.応用例-食品腐敗の計測と腐敗速度の評価
2.1 煮豆の腐敗計測とその再現性
2.2 各種の食品が示す腐敗サーモグラム
2.3 煮豆の防腐実験
3.予測食品微生物学への応用
4.使用に際しての注意点
病原菌および特定菌の迅速検出法
第8節 免疫学的検出法<伊藤 武>
1.免疫学的な方法
2.サルモネラ検出法
3.腸管出血性大腸菌O157検出法
4.その他の病原菌
5.黄色ブドウ球菌エンテロトキシン
第9節 遺伝子検出法
1)DNAプローブ法<牛山正志>
1.測定原理
2.測定方法
2.1 前培養
2.2 キット操作手順
3.応用例
3.1 サルモネラ
3.2 リステリア
3.3 その他
4.使用に際しての注意点
2)PCR法<向井博之/藤井聖士/三宅一恵/中筋 愛>
1.PCRの基本原理
2.食品微生物検査へのPCRの応用
3.増幅DNAの検出
4.応用例
4.1 アガロースゲル電気泳動による検出
4.2 リアルタイムPCRによる検出
5.PCR法の注意点
第10節 バクテリオファージ法<野上尊子>
1.ファージの初期感染過程と検出の原理
2.T4の蛍光標識の実際
2.1 4',6-ジアミジノ-2-フェニルインドール(DAPI)によるT4DNAの標識
2.2 蛍光標識T4による大腸菌の特異染色の実際
2.3 細胞エネルギー状態とT4による染色性
2.4 自動測定系構築の試み
3.大腸菌以外の細菌とファージによる特異検出
第5章 微生物同定の迅速化技術と現場活用法
第1節 微生物の簡便同定の意義と課題<金子精一>
第2節 簡便同定法<金子精一>
1.分離菌株の菌属同定
1.1 分離細菌の性状試験
1.2 試験結果に基づく菌属の決定(同定)
2.選択培地を併用した特定菌属群同定
2.1 使用培地
2.2 平板培地表面への試料接種と培地の乾燥法
2.3 培養温度および時間
2.4 集落カウント法
第3節 シークエンス法<後藤慶一>
1.同定原理
2.同定方法
2.1 DNAの調製
2.2 標的領域の増幅
2.3 電気泳動による確認
2.4 増幅DNAの精製
2.5 シークエンシング
2.6 波形データ解析
2.7 データベース検索
3.使用に際しての注意点
4.PCRサービスライセンス
5.遺伝子解析による微生物同定の受託業務
第4節 リボプリンター[tm]法<吉田信一郎>
1.原理
2.分析方法
3.応用例
3.1 菌株間の比較
3.2 細菌の同定
3.3 類縁関係の推定
4.使用に際しての注意点
4.1 菌株比較における注意点
4.2 同定結果に関する注意点
4.3 デンドログラム作成時の注意点
付属資料
1)簡便迅速測定法で使用する統計的手法<金子精一>
1.相関・回帰分析
2.対応あるデータについての2つの平均値の差の検定
2)工場における簡便迅速測定法導入プロセスの具体例-食品原材料の場合<間處博子>
1.ATP法導入の背景
1.1 洗浄効果判定の役割
1.2 従来法(微生物検査)の問題点
1.3 ATP法の特徴
2.導入プロセス
2.1 導入プロセスⅠ-衛生標準作業手順(SSOP)の作成
2.2 導入プロセスⅡ-SSOPの定着