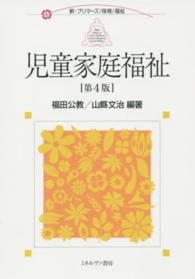出版社内容情報
21世紀の食品市場を創造する、「食感」に着目した新製品開発・調理加工技術・マーケティング戦略のエンサイクロペディア!
執筆者一覧
【編集委員】
西成 勝好 大阪市立大学生活科学部食品栄養科学科教授
中沢 文子 共立女子大学家政学部物理学研究室教授
勝田 啓子 奈良女子大学生活環境学部生活環境学科助教授
戸田 準 食評価コンサルタント
【執筆者一覧】
勝田 啓子 奈良女子大学生活環境学部生活環境学科助教授
西成 勝好 大阪市立大学生活科学部食品栄養科学科教授
窪田金次郎 東京医科歯科大学名誉教授
高橋 淳子 聖セシリア女子短期大学幼児教育学科講師
新井 映子 静岡大学教育学部助教授
中沢 文子 共立女子大学家政学部物理学研究室教授
柳澤 幸江 和洋女子大学家政学部健康栄養学科助教授
和仁 皓明 東亜大学工学部食品工学科教授
黄 竜 大阪市立大学大学院生活科学研究科
Stefan Kasapis Department of Food Science &Neutrition,College of Agricalture,Sultan Qaboos University
Dimitrios Boskou Laboratory of Food Chemistry and Technology,Faculty of Chemistry,Aristotle University of
Thessaloniki
Autio,K.and VTT Biotechnology and Food Reserch
Lahteenmaki,L.
Alina Surmacka
Szczesniak
Andrew Halmos
大坪 研一 農林水産省食品総合研究所素材利用部穀類特性研究室室長
諸橋 敬子 新潟県農業総合研究所食品研究センター穀類食品課主任研究員
渡辺 紀之 亀田製菓(株)R&Dセンター研究室室長兼ヘルスケア事業部長
川畑 育治 (株)三輪そうめん山本技術研究所所長
赤松 伸行 日清食品(株)中央研究所食品開発部部長
門岡 克行 マ・マーマカロニ(株)宇都宮工場研究開発部課長
長尾 精一 製粉協会理事/製粉研究所長
早川 幸男 (社)菓子総合技術センター専務理事/研究所長
長野 隆男 愛媛大学教育学部助教授
神山かおる 農林水産省食品総合研究所食品理化学部食品物性研究室主任研究官
長谷川裕正 茨城県工業技術センター発酵食品部主任研究員
前梶 健治 山陽女子短期大学食物栄養学科教授
干野 隆義 アヲハタ(株)R&Dセンター開発センター次長
枳穀 豊 アヲハタ(株)R&Dセンター研究分析室長
稲熊 隆博 カゴメ(株)総合研究所基礎研究部部長
福島 正義 東京農業大学生物産業学部食品科学科教授
井筒 雅 雪印乳業(株)研究企画部部長
折居 直樹 明治乳業(株)中央研究所市乳開発研究部課長
高野 耕次 明治乳業(株)中央研究所市乳開発研究部
小久保貞之 森永乳業(株)食品総合研究所第2開発室室長
岡崎恵美子 中央水産研究所加工流通部品質管理研究室長
島根 正則 日本ハム(株)中央研究所
重久 保 日本ハム(株)中央研究所
小林 幸芳 キユーピー(株)研究所研究1部技術開発
鈴木 英司 クノール食品(株)商品開発研究所
平野 和彦 太陽化学(株)研究所EP事業部研究開発主任研究員
宇野 喜貴 三栄源エフ・エフ・アイ(株)ハイドロコロイド研究室
大本 俊郎 三栄源エフ・エフ・アイ(株)ハイドロコロイド研究室マネージャー
藤田 哲 藤田技術士事務所所長
森高 初惠 昭和女子大学生活科学科助教授
本木 正雄 味の素(株)食品研究所原料・素材基盤研究所所長
大塚とも子 味の素(株)食品研究所原料・素材基盤研究所
柳沼 義仁 旭化成工業(株)添加剤技術第1部主幹研究員
藤原 和彦 日本リーバ(株)リージョナル・イノベーションセンターテクニカルマネージャー
位田 毅彦 太陽化学(株)NF事業部研究開発副主席研究員
余川 丈夫 太陽化学(株)NF事業部研究開発
山崎 彬 越後製菓(株)代表取締役社長
笹川 秋彦 越後製菓(株)総合研究所食品研究室室長
早川 功 九州大学大学院教授
戸田 準 食評価コンサルタント
内容目次
第1部 食感研究の最新潮流とマーケティング戦略
第1章 食感とおいしさのニューサイエンス
第1節 おいしさとその構成要素<勝田啓子>
1.おいしさとは何か?
2.おいしさの評価にかかわる要素―食物に対する人間の認識の流れ―
3.心理的要因
4.観念的要因
5.嗜好
6.食物の特性に由来する要因
6.1 化学的な要因と物理的要因
6.2 フレーバ・リリース(flavor release)
6.3 味と香り(匂い)―風味―
7.生理的要因
第2節 食感とは何か<西成勝好>
第3節 食感の表現法<勝田啓子>
1.食感(=テクスチャー)定義の困難さ
2.食感の言語表現における問題点
3.食感表現用語の国際化・標準化
4.代表的食品の食感表現用語
第2章 食感・口腔内感覚と生理機能
第1節 食感と咀嚼、嚥下<窪田金次郎>
1.噛んだときの硬さの感知、口蓋と舌で押しつぶすときの感知
2.唾液、刺激による唾液の分泌
3.食塊の移動、嚥下の機構
3.1 嚥下のメカニズム
4.咀嚼による生理機能の活性
第2節 口腔内感覚のダイナミックス
A 咀嚼中に歯に生じる咀嚼圧、口蓋圧<高橋淳子>
1.咀嚼力について
1.1 食品の厚さが異なる場合の咀嚼力
1.2 加熱後の食品の咀嚼力
1.3 咀嚼力と機器測定から得られる値との関連
2.半固体食品の口蓋圧
2.1 ゼリーを咀嚼したときの口蓋圧
2.2 形状の違うゼリーを咀嚼したときの口蓋圧
3.液体食品の口蓋圧
3.1 粘度の異なる液体食品の口蓋圧
3.2 ニュートン流体と非ニュートン流体の口蓋圧
3.3 液体食品の一度に飲み込める量
B 咀嚼音<高橋淳子>
1.食品の咀嚼音を特徴づける性質
2.咀嚼音の測定と周波数解析
3.咀嚼音と擬声語
4.食品の咀嚼音を表す擬声語
C 口腔内食物の移動<新井映子>
D 咀嚼中の歯の動き<中沢文子>
1.噛む動作
2.歯の動きを測定する装置
3.第1大臼歯の咀嚼における動き
第3節 咀嚼筋筋電図<柳澤幸江>
1.筋肉収縮の原理
1.1 活動電位
1.2 骨格筋の収縮
2.筋電図による咀嚼筋・舌筋の筋活動の計測
2.1 筋電図
2.2 歯科領域における筋電図の利用
2.3 咀嚼運動と咀嚼筋・舌筋
2.3.1 咬筋 masseter muscle
2.3.2 側頭筋 temporal muscle
2.3.3 外側翼突筋 lateral(external)pterygoid muscle
2.3.4 内側翼突筋 medial(internal)pterygoid muscle
2.3.5 舌骨上筋群
2.4 表面筋電図の測定
2.5 表面筋電図の記録方法と分析方法
2.6 分析区間
3.食品の食感を分析する手段としての筋電図
3.1 咀嚼中の食感と咀嚼筋筋活動
3.2 舌運動の筋電図誘導
3.3 嚥下の筋電図誘導
第3章 消費者の行動変化と食感マーケティングへの視点<和仁皓明>
1.食感マーケティングの切り口
1.1 食品企業の二極性
1.2 食品品質の差別化視点とは
2.テクスチャーの機能性
2.1テクスチャーの機能分解
2.1.1 第一次機能(食べやすさ機能)
2.1.2 第二次機能(食感の快適さ機能)
2.1.3 第三次機能(食品の生理活性促進構造)
2.2 テクスチャーのおいしさ機能
2.3 感性とテクスチャー特性
3.再びテクスチャーの第一次機能へ
3.1 テクスチャーの現代的視点
3.2 高齢者介護における給食の問題
第4章 新食感食品の海外動向
第1節 アジアの動向
A 中国<黄 竜>
1.中国料理の概念イメージ
2.調理過程のテクスチャーに及ぼす影響
3.いくつかの中国特色食品のテクスチャー
3.1 雲南省の「糸引き納豆」
3.2 チベットのバター茶
3.3 浙江省の「金華火腿」
3.4 福建省ウーロン茶
4.テクスチャーの人間の健康に対する影響
5.中国語のテクスチャー評価用語
B 韓国(予定)
C タイ(予定)
第2節 欧米の動向
A フランス(予定)
B ギリシア<Stefan Kasapis and Dimitrios Boskou>
C ブラジル(予定)
D フィンランド<Autio,K.and Lahteenmaki,L.>
E 米国<Alina Surmacka Szczesniak>
F オーストラリア<Andrew Halmos>
第2部 生活に息づく食感の創成技術
第5章 各種食品に見る食感開発の実際
第1節 米および米加工品
A 米・粥<大坪研一>
1.わが国における米食史
2.白飯のおいしさ
3.白飯の一般的な炊飯・調理
4.白飯の食感の評価
4.1 テクスチュロメータによる測定
4.2 動的粘弾性の測定
4.3 テンシプレッサーによる多面的物性測定
5.業務用炊飯
6.粥
6.1 白飯
6.2 茶粥
6.3 粥の物性測定
B 餅類<諸橋敬子>
1.餅の物理性と官能評価
2.調理特性
2.1 つき方式と物性
2.2 つき方式と調理性
C 米菓<渡辺紀之>
1.米菓の分類と特徴
2.米菓の市場・製品動向と食感の変遷
3.製造工程と食感
4.食感の評価方法
4.1 レオメトリー
4.1.1 進入度試験
4.1.2 折れ試験
4.1.3 圧縮試験
4.2 アミログラフィー
4.2.1 当社製品(おかき)の硬度の経時変化の把握
4.2.2 原料米が異なるおかきの差異の把握
4.2.3 微妙な食感の差異がある当社粳製品の把握
5.食感をめぐる課題と展望
第2節 小麦粉加工品
A うどん・そうめん<川畑育治>
1.手延べそうめんの製造方法
2.うどんの製造方法
3.手打ちと手延べの違いと最近の傾向
4.食感
B 中華めん<赤松伸行>
1.中華めんの市場、製品動向と食感の変遷
2.テクスチャーに関わる製品開発の実際
3.食感をめぐる課題と展望
C マカロニ・スパゲッティ<門岡克行>
1.当該食品の市場・製品動向と食感の変遷
2.テクスチャーに関わる製品開発の実際
3.食感をめぐる課題と展望
D パン類<長尾清一>
1.市場と製品の動向
2.パン類の食感
3.新製品開発の動向
4.食感をめぐる課題と展望
第3節 菓子類<早川幸男>
第4節 大豆加工品など
A 豆腐
【1】大豆タンパクの機能と製品応用<長野隆男>
1.大豆タンパク質
2.原料大豆
3.豆腐
4.豆腐食感の利用
【2】豆腐のテクスチャー測定<神山かおる>
1.豆腐の食感の特色
2.豆腐の食感に影響する諸因子
2.1 原料大豆による因子
2.2 製造方法による因子
3.官能評価
4.機器による方法
4.1 貫入試験
4.2 試料全体を圧縮する試験
4.3 テクスチャープロフィール法(TPA)
4.4 圧縮-回復試験
4.5 多重バイト法
4.6 応力緩和およびクリープ
4.7 粘性測定
4.8 動的粘弾性
5.新手法と新製品のテクスチャー
5.1 テクスチャーマッピング法
5.2 咀嚼の生体計測
5.3 新規開発製品のテクスチャー評価
B 納豆<長谷川裕正>
1.納豆の製品動向と食感
2.納豆の物性測定の実際
2.1 粘物質の粘弾性とその測定法
2.1.1 粘物質の採取
2.2.2 粘度の測定
2.2.3 ワイセンベルグ効果の観察
2.2 納豆の硬さ
2.2.1 納豆の豆の硬さ測定法
2.2.2 測定法と官能評価
C こんにゃく<前梶健治>
1.こんにゃくの生産と消費
1.1 生産・流通・消費
1.2 消費減退の背景
2.こんにゃく製品のテクスチャーの変遷
3.新製品開発の現状
3.1 巻き(結び)こんにゃく
3.2 繊維状こんにゃく
3.3 粒状こんにゃく
3.4 刺身こんにゃく
3.5 凍結こんにゃく
4.こんにゃく製品の今後の動向
第5節 野菜・果実加工品
A ジャム・マーマレード<干野隆義・枳穀 豊>
1.ジャム・マーマレードの歴史と現在の流れ
2.国内・海外の市場規模
3.ジャム類の製造方法とペクチン
4.市販ブルーベリージャムの食感と方向性
5.ジャム類の展望
B ケチャップ<稲熊隆博>
第6節 乳・乳加工品
A バター・マーガリン<福島正義>
1.バター・マーガリンの市場・製品動向と食感の変遷
1.1 バター:脂肪源の保存形態
1.2 マーガリン:世紀のソフト製品
2.テクスチャーに関わる製品開発の実際
2.1 バター:小型の成形品で活路
2.2 マーガリン:捏和機で緻密な組織
3.食感をめぐる課題と展望
B チーズ<井筒 雅>
1.チーズの歴史と種類
2.生産・消費動向
3.テクスチャーに関わる研究開発
4.チーズのテクスチャーをめぐる課題と展望
C ヨーグルト<高野耕次・折居直樹>
1.ヨーグルトの種類と規格、市場動向
2.ヨーグルトのテクスチャーに影響する要因
2.1 プレーンヨーグルトおよびヨーグルト全般
2.2 ハードヨーグルト
2.3 ソフトヨーグルト
2.4 ドリンクヨーグルト
D アイスクリーム<小久保貞之>
1.アイスクリームの味覚
2.アイスクリームの微細構造
3.アイスクリームミックスと解乳化
4.アイスクリームのレオロジー
5.ボディーとテクスチャー
第7節 魚肉加工品<岡崎恵美子>
第8節 食肉加工品<島根正則・重久 保>
1.食肉製品の生産数量と製品構成の変化
2.食肉製品関連法規の改正と新テクスチャー食肉製品の登場
3.新テクスチャー食肉製品の開発例
4.食肉製品の物性評価
5.食肉加工品のテクスチャーに求められる課題と展望
第9節 調味料類
A ソース<稲熊隆博>
B マヨネーズ・ドレッシング<小林幸芳>
1.マヨネーズ類
1.1 マヨネーズ
1.2 マヨネーズタイプ調味料
2.液状ドレッシング
第10節 調味加工食品類
A スープ<鈴木英司>
B ハンバーグ<井筒 雅>
C 卵豆腐・茶碗蒸し<平野和彦>
第6章 新食感を実現するテクスチャーモディファイヤーと応用
第1節 1.テクスチャーモディファイヤーとその食感<西成勝好>
2.テクスチャーコントロールの実際<位田毅彦・余川丈夫>
第2節 増粘・安定剤<大本俊郎・宇野喜貴>
1.増粘安定剤とは
2.主に増粘剤として利用される多糖類
2.1 キサンタンガム
2.2 ローカストビーンガム
2.3 グアーガム
2.4 タマリンド種子多糖類
3.安定剤として利用される多糖類
3.1 カラギーナン
3.2 ハイメトキシルペクチン
3.3 大豆多糖類
3.4 ジェランガム
4.使用基準について
4.1 指定添加物
4.1.1 カルボキシメチルセルロースカルシウム
4.1.2 カルボキシメチルセルロースナトリウム
4.1.3 デンプングリコール酸ナトリウム
4.1.4 デンプンリン酸エステルナトリウム
4.1.5 ポリアクリル酸ナトリウム
4.2 既存添加物
5.食品への添加物の表示について
5.1 表示方法
5.2 食品への添加物表示を省略できる製剤中の食品添加物の範囲
5.2.1 製剤の形態を形成させるために必要不可欠であり、かつ必要量以内で配合される添加物
5.2.2 主剤の機能を安定化させるための添加物
第3節 ゲル化剤<西成勝好>
第4節 乳化剤と食品テクスチャー<藤田 哲>
1.食品用乳化剤
2.乳化剤とタンパク質、デンプンとの相互作用
3.食品エマルションの安定性に影響する因子、油脂とタンパク質
3.1 タンパク質の乳化作用
3.2 エマルション安定化とタンパク質の役割
4.油水界面に吸着するタンパク質と乳化剤間の競合
5.食品における膜乳化と乳化剤
第5節 新素材
A 大豆多糖類<森初惠>
1.大豆多糖、CRC多糖
2.CRCガム
B トランスグルタミナーゼ<本木正雄・大塚とも子>
1.微生物起源TGの発見とその特性
2.その他の工業用TGの大量製法の試み
2.1 血液からの抽出
2.2 微生物からの分離
2.3 遺伝子組み換え製法
3.原料内在性TGと食品加工での役割
4.GLの分布と消化性
4.1 GL検出と定量法
4.2 食品中の分布
4.3 GLの消化法
5.食肉加工への応用
6.新しい応用の可能性
6.1 栄養生理分野
6.2 ハイブリッド素材
6.3 シート状素材
C 微粒子セルロース<柳沼義仁>
1.結晶セルロースのグレードと特性
2.「アビセル」RC、「セオラス」SCの機能
2.1 懸濁安定化機能
2.2 乳化安定化機能
2.3 耐熱安定化機能
2.4 チキソトロピー性
2.5 保水性、保形性
2.6 脂肪代替適性
3.「アビセル」「セオラス」の食品への応用
3.1 固体粒子懸濁系の飲料
3.2 クリーム類
3.3 ビスケット
D 流動ゲル(Fluid Gel)<藤原和彦>
第6節ダイエタリーファイバーとしてのテクスチャーモディファイヤー<位田毅彦・余川丈夫>
1.食物繊維とは
2.食物繊維の分類と種類
3.食物繊維の生理効果
4.食物繊維の脂肪、糖質(砂糖)代替物としての応用
4.1 脂肪代替物への応用
4.2 糖質(砂糖)代替物への応用
第7章 新食感を目指す調理・加工技術
第1節 加熱・冷却・冷凍<中沢文子>
1.水の役割
2.常温における加工・調理
2.1 乾燥・吸水
2.2 あらい・さらし
3.加熱による加工・調理
3.1 煮る・蒸す
3.2 揚げる・炒める
3.3 焼く
3.4 電子レンジ加熱
4.冷蔵・冷凍
4.1 冷蔵
4.2 氷温冷蔵
4.3 パーシャルフリージング
4.4 凍結
5.冷却・冷凍の過程
6.解凍
6.1 冷蔵庫内の解凍
6.2 空気解凍
6.3 電子レンジ解凍
6.4 水中解凍
6.5 加圧解凍
6.6 解凍法の選択
7.食べるときの適温
第2節 加圧<山崎 彬・笹川秋彦>
1.高圧処理の食品への利用
2.タンパク質食品への利用
2.1 魚肉すり身のゲル化
2.2 牛肉(死後硬直後)の軟化
2.3 新しい加圧豚肉と加圧ハムの製造
2.4 鶏卵の卵白および卵黄の物性変化
3.デンプン食品への利用
3.1 米飯の食感改良
3.2 新しい物性の餅の開発
3.3 新しい米菓の製造方法
4.漬物への利用
4.1 梅漬けの物性改善処理
4.2 ミョウガおよびカブの調味加工
4.3 各種漬物の加圧と加熱との物性比較
5.果実加工品への利用
6.牛乳および豆乳のゲル化への利用
7.新しい食品の創出
第3節 低温滅菌法<早川 功>
1.耐熱性胞子の破壊殺菌
2.栄養細胞の破壊殺菌
第8章 食感の評価・測定技術
第1節 物性測定<西成勝好>
1.基礎的測定
2.実用的測定
3.熱物性
第2節 官能評価<戸田 準>
1.官能評価実験
2.官能評価の型
3.官能評価の手法
3.1 二項型試験法
3.2 順位法
3.3 評定尺度法
3.4 マグニチュード推定法
3.5 記述試験法
4.官能評価データの解析法
4.1 二項検定
4.2 順位検定
4.3 評定尺度データ
4.4 マグニチュード推定値
4.5 記述試験データ
4.6 一対比較法
5.官能評価から見た食品のテクスチャー
第3節 データ解析<戸田 準>
1.多次元データの基本統計量
2.回帰分析法:感覚特性と物理特性の関係
2.1 単回帰分析
2.2 重回帰分析
3.主成分分析法:テクスチャーの基本特性
4.親近性データの解析法:テクスチャーによる固形食品の分類
-

- 電子書籍
- おたまじゃくしな彼女たち~女もみんな溜…