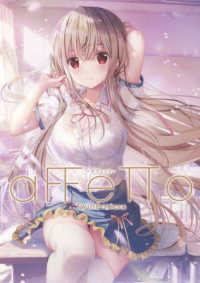出版社内容情報
食品・生活素材・クラスターの破壊メカニズムの解明を通して、画期的な新機能製品開発の実際を集大成した初の実務指針書!
目次
■第1篇 マテリアル破壊メカニズムと技術展開
序 章 諸々の破壊メカニズムの現状
第1章 咀嚼による食品破壊とそのメカニズム
第2章 クラスターの破壊とそのメカニズム
第1節 水の構造プロセス
第2節 金属の構造プロセス
第3章 プラスチックの破壊現象とそのメカニズム
第4章 粉砕操作と生成粉粒体のフラクタル性
第5章 粉体の流動現象とそのメカニズム
第1節 気中粉体の流動現象とそのメカニズム
第2節 液中微粒子分散系と成形体,燒結体特性制御
第3節 粉体流動現象シミュレーション
第6章 風合いのメカニズム
第7章 トライボロジーのメカニズム
第8章 破壊による限界粒度への挑戦
■第2篇 破壊コントロールと高付加価値製品開発
第1章 咀嚼とデザイナーズフーズ
第1節 澱粉質食品
第2節 魚肉製品
第3節 大豆製品
第4節 増粘安定剤によるテクスチャーモディファイアー
第5節 小児食・老人食・介護食
第2章 香りの破壊コントロールと製品応用
第1節 日常生活と香り
第2節 フレグランスと製品開発
第3節 フレーバーと製品開発
第4節 粉末香料の概況
第3章 機能性フィルムの破壊現象と製品応用
第4章 ファインセラミックスの破壊コントロールと製品応用
第1節 信頼性の高いセラミックスの製造プロセス
第2節 セラミックスを破壊から守る技術開発
第3節 セラミックス加工の技術と原理
第5章 メカニカルアロイングによる機能性金属材料
第6章 医用バイオマテリアルの新展開
執筆者一覧
■編集委員長
種谷 真一 (株)ダルトン理事・東京農業大学客員教授
■編集委員
高橋 淳子 聖セシリア女子短期大学幼児教育学科講師
内藤 牧男 (財)ファインセラミックスセンター標準化プロジェクト研究室室長代理
近藤 浩司 食品産業戦略研究所主任研究員
■執筆者
種谷 真一 (株)ダルトン理事・東京農業大学客員教授
高橋 淳子 聖セシリア女子短期大学幼児教育学科講師
中沢 文子 共立女子大学家政学部物理学研究室教授
近藤 浩司 食品産業戦略研究所主任研究員
中平 敦 京都工芸繊維大学工芸学部物質工学科助教授
鈴木 徹 東京水産大学水産学部食品生産学科助教授
富田 侑嗣 九州工業大学工学部設計生産工学科教授
植松 敬三 長岡技術科学大学化学系教授
田中 敏嗣 大阪大学大学院工学研究科機械物理工学専攻助教授
辻 裕 大阪大学大学院工学研究科機械物理工学専攻教授
川端 季雄 滋賀県立大学工学部材料科学科学科長教授
岩渕 明 岩手大学工学部機械工学科教授
池田 正明 セイシン企業(株)取締役統括部長
高橋 禮治 松谷化学工業(株)研究所所長
木村 郁夫 日本水産(株)中央研究所研究推進課課長
広塚 元彦 不二製油(株)阪南研究開発センター蛋白事業部蛋白第一開発室室長
飯田 博樹 三栄源エフ・エフ・アイ(株)学術部係長
大本 俊郎 三栄源エフ・エフ・アイ(株)第1研究部ハイドロコロイド研究室
柳沢 幸江 和洋女子大学家政学部調理学研究室専任講師
藤森 幹三 長谷川香料(株)広報室副室長
浅越 亨 長谷川香料(株)フレグランス事業本部フレグランス研究第3部長
石川 雅司 長谷川香料(株)常務取締役フレーバー事業本部本部長
井坂 勤 東洋紡績(株)フィルム開発第1部長
篠原 伸広 旭硝子(株)中央研究所ガラス・セラミックス領域研究所主席研究員
小笠原俊夫 日産自動車(株)宇宙航空事業部基盤技術部
和田 重孝 (株)豊田中央研究所材料2部主監
野城 清 大阪大学溶接工学研究所教授
岡崎 義光 通産省工業技術院機械技術研究所基礎技術部材料設計研究室主任研究官
(敬称略・執筆順)
[この頁の先頭へ]
内容目次
発刊にあたって
第1篇 マテリアル破壊メカニズムと技術展開
序 章 諸々の破壊メカニズムの現状〔種谷真一〕
1. 破壊の種類とエネルギー
2. 破壊時間とWLFの式
3. 内部摩擦と外部摩擦
4. 咀嚼破壊
第1章 咀嚼による食品破壊とそのメカニズム〔高橋淳子/中沢文子〕
1. 食品破壊に関与する咀嚼組織
1.1 咀嚼による食品破壊に関与する口腔内器官
1.2 咀嚼に関与する筋肉
1.3 咀嚼に関与する下顎の動き
2. 液体食品の咀嚼による破壊とそのメカニズム
2.1 ニュートン液体と非ニュートン液体
2.2 粘度が異なる液体食品の咀嚼
2.3 液体食品の一度に飲む量の違いが咀嚼におよぼす影響
2.4 下顎の動きと咀嚼筋からみた液体食品の破壊
3. 半固体状食品の咀嚼による破壊とそのメカニズム
3.1 半固体状食品の力学的特性
3.2 半固体状食品の硬さや大きさが異なる場合の咀嚼
3.3 下顎の動きと咀嚼筋からみた半固体状食品の破壊
4. 固体食品の咀嚼による破壊とそのメカニズム
4.1 固体食品の種類の違いが咀嚼による破壊におよぼす影響
4.2 固体食品の大きさの違いが咀嚼による破壊におよぼす影響
4.3 固体食品の硬さの違いが咀嚼による破壊におよぼす影響
4.4 固体食品の咀嚼による破壊と口腔外の機器による破壊
4.5 下顎の歯の動きと咀嚼筋からみた固体食品の破壊
第2章 クラスターの破壊とそのメカニズム
第1節 水の構造プロセス〔近藤浩司〕
1. クラスター(cluster)
2. 水の状態図
2.1 三重点と臨界点
2.2 超臨界流体とクラスター
3. 量子論
3.1 陽子,中性子,電子
3.2 粒子と波動の二面性
3.3 シュレディンガーの波動方程式
3.4 主量子数,方位量子数,磁気量子数
3.5 電子軌道と電子配置
4. 水分子
4.1 水素原子と酸素原子
4.2 水の分子軌道
4.3 水分子のサイズ
4.4 水分子の分極
5. クラスターを形成する分子間力
5.1 イオン結合
5.2 共有結合
5.3 金属結合
5.4 分子間力(ファンデルワールスの力)
5.5 最密充填構造
5.6 水素結合
6. 水の構造とモデル
6.1 氷と水の分子構造
6.2 水の構造モデル
6.3 クラスターの構造
6.4 水の構造モデルのシミュレーション
6.5 水の温度とクラスター破壊
6.6 動径分布関数
6.7 速度自己相関関数
7. 水和クラスター
7.1 イオン性結晶の溶解サイクル
7.2 電気伝導度(イオンの動きやすさ)
7.3 正水和と負水和(ライトサルト)
8. 疎水性結合
8.1 アルコール水溶液(水和エタノールクラスター)
第2節 金属の構造プロセス〔中平 敦〕
1. 熱処理による金属のクラスター組織制御
2. アモルファス金属
3. ガラスの組織制御
4. セラミックスのナノ複合化
第3章 プラスチックの破壊現象とそのメカニズム〔近藤浩司〕
1. 破壊現象
1.1 破壊の種類
1.2 破壊に影響する高分子材料サイドの因子
2. 高分子材料の力学的挙動
2.1 応力とひずみ挙動
2.2 引張ひずみとヤング率E(実用弾性率1)
2.3 せん断ひずみと剛性率G(実用弾性率2)
2.4 体積弾性率Kと圧縮率β(実用弾性率3)
2.5 ポアソン比(実用弾性率4)
3. 理論強度
3.1 配向高分子材料の強度
3.2 無配向高分子材料の強度
4. クラックの生成,グリフィスの破壊理論
4.1 2通りの破壊理論
4.2 き裂の種類
4.3 表面エネルギーと表面張力
4.4 グリフィスの理論
5. 破壊靭性
5.1 応力集中と応力拡大係数
5.2 エネルギー解放率
5.3 破壊靭性値
6. クレイズ
7. 線形破壊
7.1 高分子材料のクレイズ発生メカニズム
7.2 脆性破壊のメカニズム
7.3 Griffith理論の修正
7.4 脆性破壊の前に起こる延性破壊のメカニズム
8. 非線形破壊,延性破壊のメカニズム
8.1 延性破壊
8.2 高圧下での脆性―延性転移
8.3 エラストマーの破壊
9. 衝撃破壊
9.1 衝撃破壊試験法とその特徴
9.2 衝撃強度に影響する因子
9.3 弾性波および塑性波による破壊メカニズム
10. 疲労破壊
10.1 繰返し数と疲労破壊
10.2 疲労破壊のメカニズム
11. クリープ破壊のメカニズム
11.1 クリープ挙動
12. 環境応力き裂(ESC)破壊
12.1 環境物質の流入吸収
12.2 分子量の効果
13. 絶縁破壊
13.1 絶縁抵抗,表面抵抗,体積抵抗
13.2 高分子材料の絶縁破壊のメカニズム
13.3 電子的破壊
13.4 熱的破壊
13.5 放電劣化(部分放電劣化,トリーイング劣化)
14. 極限環境条件下における破壊 107
14.1 低温物性と破壊のメカニズム
14.2 圧力と破壊のメカニズム
15. 破壊のプロセス
第4章 粉砕操作と生成粉粒体のフラクタル性〔鈴木 徹〕
1. 粉体のフラクタル形態評価法
1.1 フラクタル
1.2 単一粉体の形態評価
1.3 粉体集合の粒径,表面積,体積
1.4 BET比表面積と粒子径
1.5 粒径分布のフラクタル性
2. 粉砕エネルギー
2.1 古典的粉砕エネルギー則
2.2 フラクタルを考慮した粉砕エネルギー則
2.3 粒径分布フラクタルと表面フラクタル
2.4 シャルピー試験とフラクタル次元
第5章 粉体の流動現象とそのメカニズム
第1節 気中粉体の流動現象とそのメカニズム〔富田侑嗣〕
1. 粉体の物性
1.1 粒度と粒度分布
1.2 空隙率
2. 粉体の静力学
2.1 クーロン物質
2.2 隙間流体の影響
3. 気流との相互作用
3.1 粒子間の流れ
3.2 気流中の単粒子に作用する力と自由落下速度
4. 流動層
4.1 流動化開始速度
4.2 流動化の状態
4.3 気 泡
5. フラッシング現象
6. ゲルダート線図
7. 空気輸送
8. 孔からの粉体の排出
第2節 液中微粒子分散系と成形体,燒結体特性制御〔植松敬三〕
1. 加圧成形プロセスと欠陥の発生
2. 成形体中の傷の新しい評価法
3. 原料粉体の特質と分散処理
3.1 原料粉体の性状
3.2 粉体粒子間の相互作用
3.3 分散と粘性
3.4 分散に及ぼす温度の影響
4. スプレードライ顆粒の構造および特性の制御
4.1 分散・凝集の影響
4.2 顆粒表面への添加物の偏析現象
5. 成形体構造
5.1 バインダー偏析による顆粒間の不均質
5.2 中空顆粒による不均質
5.3 粒子の配向構造
6. 燒結プロセス
6.1 緻密化
6.2 大形気孔の形成
6.3 巨大粒子の形成
7. 燒結体構造と特性
第3節 粉体流動現象シミュレーション〔田中敏嗣/辻 裕〕
1. 粉粒体の運動モデルの分類
2. 連続体モデル
3. 柔軟粒子モデルと離散要素法
3.1 基礎式
3.2 接触力モデル
3.3 接触力モデル中の要素の特性について
3.4 離散要素法の応用
4. 剛体粒子モデル
4.1 基礎式
4.2 衝突モデル
4.3 衝突の判定
4.4 剛体粒子モデルの応用
第6章 風合いのメカニズム〔川端季雄〕
1. 人間の感性と交絡する材料
2. 感性性能の重要さ
3. 感性性能としての布の風合い
4. 風合いの客観評価に向けて
5. 風合いの数値化
6. 風合いの客観評価法の開発
7. 力学量の測定システム
8. 今後の方向
第7章 トライボロジーのメカニズム〔岩渕 明〕
1. トライボロジーの定義
2. 固体の表面
3. 接触のメカニズム
3.1 真実接触面積
3.2 ヘルツの弾性接触と塑性接触
3.3 粗さを持つ表面の接触
3.4 摩擦力が作用したときの接触
4. 摩擦のメカニズム
4.1 乾燥摩擦
4.2 潤滑下の摩擦
4.3 固体潤滑剤の作用
4.4 転がり摩擦
4.5 摩擦によるシステムの破壊現象
5. 摩耗のメカニズム
5.1 摩耗のパターン
5.2 摩耗の基本的メカニズム
5.3 摩耗形態の遷移メカニズム
5.4 摩耗によるシステムの破壊
第8章 破壊による限界粒度への挑戦〔池田正明〕
1. 破壊強度について
1.1 理想的破壊強度
2. 粉砕における粉砕限界
2.1 Rosin,Anselm,中条らの研究
2.2 田中の研究
2.3 松居らの研究
2.4 神保らの振動ミル,遊星ミルによる研究
2.5 川嶋らの粉砕限界に関する材料の弾性論ならびに材料強度学的立場からの検討
3. 粉砕現場における微粉砕への挑戦
3.1 微粉砕機の分類と最近の動向
3.2 砕料への添加物による粉砕性の向上
3.3 液体窒素等の冷媒を使用することによる粉砕
3.4 同体摩擦による摩擦粉砕法
3.5 減圧下での高速衝撃粉砕
3.6 加熱,加圧による粉砕性の改善
4. 粉砕の難しい,いくつかの物質の粉砕技術例
4.1 最近注目されている食品素材の微粉化
4.2 繊維質天然素材の粉砕
4.3 プラスチックス粉砕に使用される粉砕機および粉砕方法
5. 微粉砕技術の今後の動向について(砕料の品目別の微粉砕について)
5.1 プラスチックス
5.2 プラスチックス関連
5.3 一般無機物
5.4 セラミックス
5.5 化学薬品,医薬品,化粧品,農薬
5.6 食品,食品添加物,飼料
5.7 金属関係
第2篇 破壊コントロールと高付加価値製品開発
第1章 咀嚼とデザイナーズフーズ
第1節 澱粉質食品〔高橋禮治〕
1. 硬い多孔質食品
2. 軟らかい多孔質食品
3. 硬いゲル状食品
4. 軟らかいゲル・ゾル状食品
5. エマルジョン
第2節 魚肉製品〔木村郁夫〕
1. カマボコゲル形成のメカニズム
1.1 カマボコゲル形成(破壊と再形成)
1.2 坐りカマボコゲル物性の分析
1.3 坐りカマボコゲルのタンパク質化学分析
2. 新規練り製品製造法
第3節 大豆製品〔広塚元彦〕
1. 大豆製品の種類と分類
2. 大豆製品の製造工程とその意義
2.1 大豆を全粒のまま利用するもの
2.2 豆乳/豆腐
2.3 脱脂大豆/組織状大豆蛋白質
2.4 濃縮大豆蛋白質/分離大豆蛋白質
2.5 食品原料とした場合の機能特性
3. 分離大豆蛋白質の応用例
3.1 大豆蛋白質の性質
3.2 分離大豆蛋白質の応用例
4. 食感(テクスチャー)からみた大豆蛋白製品
5. 食感改良のためのいくつかの手法
5.1 加 熱
5.2 凍 結
5.3 均質化
5.4 pH
5.5 2価金属
5.6 油 脂
5.7 乳化剤
5.8 酵 素
5.9 塩 類
6. 蛋白質以外の成分
第4節 増粘安定剤によるテクスチャーモディファイアー〔飯田博樹/大本俊郎〕
1. 増粘安定剤の種類
2. カラギナン
3. ジェランガム
4. 相乗作用
5. 今後の展望
第5節 小児食・老人食・介護食〔柳沢幸江〕
1. 離乳食を中心とした小児食
2. 老人食と介護食
2.1 老人食とは
2.2 介護食
第2章 香りの破壊コントロールと製品応用
第1節 日常生活と香り〔藤森幹三〕
1. 身の回りの香り
2. 香り物質について
3. 人間の嗅覚器官
4. 匂い(香り)発生のメカニズム
4.1 「緑の香り」発生の仕組み―植物組織の破壊(分解)により香りを発生―
4.2 バニラビーンズの香り
4.3 ミートフレーバー
4.4 お茶類の香り
第2節 フレグランスと製品開発〔浅越 亨〕
1. フレグランスと生活
2. 香 水
2.1 香水の仲間とその特徴
2.2 その香り
2.3 香りの流れ
2.4 残念なことに
3. 芳香剤
3.1 その市場規模
3.2 芳香剤の基剤
3.3 芳香剤の香り
4. アロマコロジー
第3節.侫譟璽弌爾叛宿奮?発〔藤森幹三〕
1. 食べ物の風味と匂い
2. フレーバーの役割
3. フレーバーの種類
3.1 総合的な分類
3.2 構成要素による分類
3.3 香調分類
3.4 フレーバーの用途による分類
3.5 形態による分類
4. フレーバー開発のこれから
第4節 粉末香料の概況〔石川雅司〕
1. フレーバーの粉末化・カプセル化の目的
2. 粉末化,カプセル化の方法
2.1 スプレードライ法(噴霧乾燥法:Spray Drying)
2.2 バキュームドライ法(真空乾燥法:Vacuum Drying)
2.3 エクストルージョン法(押し出し法:Extrusion)
2.4 コアセルベーション法(液中硬化被膜法)
2.5 脂肪・油脂・コーティング法(Fat or Wax Coating)
2.6 包接化法(Molecular inclusion in Cyclodextrin)
2.7 ソフト・ハード・マイクロカプセル化法(Microcapsulation)
第3章 機能性フィルムの破壊現象と製品応用〔井坂 勤〕
1. 組織敏感性と組織鈍感性
2. 引張破壊現象
2.1 一般的現象
2.2 組織構造欠陥を有する場合の引張破壊現象
3. 屈曲破壊現象
3.1 屈曲破壊メカニズム
3.2 耐屈曲ピンホールPET
3.3 耐屈曲ピンホール性ONy
4. 内圧破袋現象
4.1 袋の変形状態
4.2 内圧を受ける包装袋破袋メカニズム
4.3 最内面シール層の面間剥離破壊
4.4 シール層の層間剥離による破壊
4.5 ラミネート界面破壊
4.6 基材破壊
5. 衝撃破壊
5.1 液体充填包装の落袋破袋の実例
5.2 真空包装袋の落下破袋
6. 破裂破壊
6.1 破裂強度
7. 突刺破壊
7.1 フィルムの突刺強度
7.2 突刺破壊現象の実例
8. 擦過破壊現象
9. 引裂破壊
9.1 未延伸フィルム
9.2 縦方向一軸配向フィルム
9.3 横方向一軸配向フィルム
9.4 二軸配向フィルム
第4章 ファインセラミックスの破壊コントロールと製品応用
第1節 信頼性の高いセラミックスの製造プロセス〔篠原伸広〕
1. リファセラム(アルミナ)製造プロセスの開発
2. 原料の選択
3. 原料の分散
4. 造 粒
5. 焼結体の特性
第2節 セラミックスを破壊から守る技術開発〔小笠原俊夫〕
1. セラミックスにおける破壊現象の特徴
1.1 破壊靭性と脆性
1.2 強度のばらつき
1.3 寸法効果
1.4 仕上げ加工の影響
1.5 静疲労の影響
1.6 繰り返し疲労
1.7 非破壊検査と保証試験
2. セラミックスを破壊から守るための設計(セラミックターボチャージャーローターを例として)
2.1 即時破壊保証
2.2 寿命保証
第3節 セラミックス加工の技術と原理〔和田重孝〕
1. セラミックス加工の原理
2. セラミックスの物性と加工能率
3. セラミックス加工の技術
3.1 研削加工
3.2 ホーニング加工
3.3 サンドブラスト加工
3.4 水ジェット加工
3.5 超音波加工
3.6 ラッピング加工
3.7 ポリシング加工
3.8 切削加工
3.9 放電加工
3.10 レーザー加工
第5章 メカニカルアロイングによる機能性金属材料〔野城 清〕
1. 金属の破壊
2. 破壊による材料の高付加価値化
3. 粉末の特性を維持した成形加工プロセス
3.1 繰り返し鍛造法
3.2 放電プラズマ焼結(SPS)法
第6章 医用バイオマテリアルの新展開〔岡崎義光〕
1. 金属の毒性
2. 生体用金属材料
2.1 ステンレス鋼
2.2 Co-Cr合金
2.3 純TiおよびTi合金
3. 生体適合性に優れた新Ti合金の開発
3.1 各種金属イオンの細胞適合性
3.2 合金設計の指針
3.3 生体内での耐食性
3.4 力学特性
3.5 腐食疲労特性
-
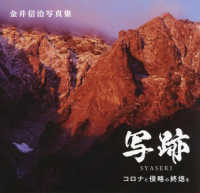
- 和書
- 写跡

![カードすごろく レキシトリップ from DVD付 学研まんが NEW日本の歴史 [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40575/4057509216.jpg)