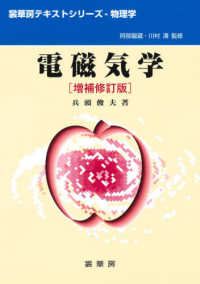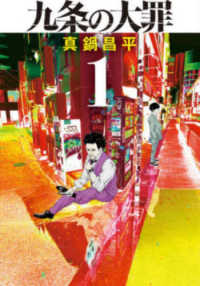内容説明
子どもたちの「心の空腹感」を埋めたい。競争と評価にさらされる「まなびの時間」だけで子どもは育つのか。家族に会話と「くらしの時間」を生み出し、子どもたちに生きる力を目覚めさせた、自分でつくる「弁当の日」の実践は、教師、親、地域を動かし、全国へ伝播中。
目次
プロローグ 「弁当の日」のある中学校―ルポ・二〇〇五年一〇月一一日(渡辺智子)
「弁当の日」と三つの時間(「弁当の日」の三つのきまり;「評価しない」がキーポイント ほか)
中学校にやってきた「弁当の日」(中学校で「弁当の日」がむずかしい理由;実践開始のために工夫したこと ほか)
「弁当の日」を支える教職員たち(家庭科教員としての手応えを感じて(眞邉国子(家庭科))
感謝の連鎖(吉田崇(国語科)) ほか)
子どもを台所に立たせよう―子育てと食育(私の考える食育;働く親を見て育つ子ども ほか)
著者等紹介
竹下和男[タケシタカズオ]
1949年、香川県生まれ。香川大学教育学部卒。県内の小・中学校・教育行政職を経て、平成12年度から綾南町立(現綾川町立)滝宮小学校、平成15年度から国分寺町立(現高松市立)国分寺中学校の校長。「子育て」や「食育」について積極的に全国で講演中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
本読みじいさん
5
先日の「弁当の日」シンポジウムがきっかけで読みました、竹下先生の話は聞いても泣けましたが読んでもなけてきました。しかし泣いてばかりではいられません、我が家で出来ることを考え中。2011/04/29
どっち
2
前半は竹下和男校長の考える教育理論。(1)暮らしの時間(衣食住の手伝い)(2)遊びの時間(子ども同士の付き合い)(3)学びの時間 の3本立ての子どもの生活の中で、学校・塾・習い事・スポーツといった学びの時間ばかりが増え、他の時間が減少している。学びの時間は評価・勝敗といった他人を蹴落とすことを身に付ける。衣食住、例えば洗濯物をたたむ・ご飯を作る・家の掃除などを手伝うことにより、他人に喜んでもらえることのすばらしさを覚える。その最初から最後までを自分で考えて行わせることができるのが"弁当作り"。2011/06/03
ひっしー
1
大阪で弁当の日の実践みたことある!栄養士さんとの出会い、「ごちそうさん」の影響で食について考えたいと思った。家庭の役割が崩壊してるからこそ、家庭と協力して子どもたちに力つけてあげたい。2013/12/14