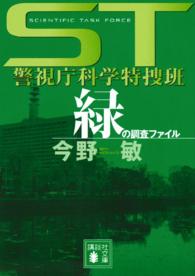内容説明
『源氏物語』の享受が生み出した雅俗の表象は、それ自体がひとつの文化装置として日本文化の形成に関与してきた。江戸時代の文化・文芸を中心に、さまざまなイメージやテクストにおける受容と再生の軌跡から、現代にいたる「源氏文化」の意味を問う。
目次
1 『源氏物語』の図像資料(幻の「源氏物語絵巻」をもとめて―新紹介バーク本・ベルギー本から;バーク財団蔵「源氏物語絵巻」賢木巻断簡について;『源氏物語』の絵入り写本)
2 “みやび”とパロディ―文学史の想像力にみる(お伽草子と説話世界の『源氏物語』;『源氏物語』享受における和歌と絵画―若紫巻をめぐって;近世和歌と『源氏物語』―源氏物語名和歌の方法;交錯する雅俗―江戸初期の連歌に見る『源氏物語』;西鶴・長嘯子・芭蕉の『源氏物語』享受―『好色一代男』『挙白集』『奥の細道』を中心として;『源氏物語』と『色道大鏡』―遊女「八千代」を中心に)
3 視覚化される雅俗―宗教・芸能・美術から(源氏供養と普賢十羅刹女像;『扇の草子』に見る十七世紀前後の『源氏物語』享受;源氏文化から葦手のポエティックネスへ;元禄歌舞伎と『源氏物語』―近松門左衛門作『今源氏六十帖』における受容;江戸の見立て絵と女三宮)
4 源氏文化と近代日本のイメージ形成―現代への射程(図像・ジェンダー・源氏文化―立教大学日本文学科創設五〇周年記念国際シンポジウムから;『源氏物語』享受史の射程;『源氏物語』と文化共同体;『源氏物語』の文化イメージとヴィジュアリティ;アカデミズムと大衆文化―『源氏物語』江戸から近現代へ;『源氏物語』と女訓書:物語は亡霊たちをDeleteしたか―戦時下版「谷崎源氏:の削除問題について)
著者等紹介
小嶋菜温子[コジマナオコ]
立教大学文学部教授。古代文学
小峯和明[コミネカズアキ]
立教大学文学部教授。中世文学
渡辺憲司[ワタナベケンジ]
立教大学文学部教授。近世文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。