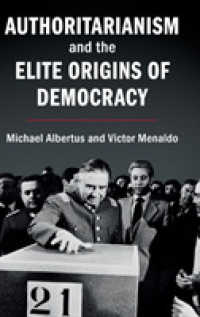内容説明
この本から、始まる新しい世界史=「生きるための世界史」。あらゆる人が戦争と自分を結びつけ、歴史に出会い直すために。アラブ、ポーランド、ドイツを専門とする三人の対話からはじめて浮かび上がる「パレスチナ問題」。
目次
1 私たちの問題としてのパレスチナ問題(岡真理「ヨーロッパ問題としてのパレスチナ問題―ガザのジェノサイドと近代五百年の植民地主義」;「ユダヤ人のパレスチナ追放による離散」は史実にない;ジェノサイドが終わるだけでは不十分 ほか)
2 小さなひとりの歴史から考える(小山哲「ある書店店主の話―ウクライナとパレスチナの歴史をつなぐもの」;ふたつの戦争のつながり;長い尺度で問題を捉える ほか)
3 鼎談「本当の意味での世界史」を学ぶために(今の世界史は地域史の寄せ集め;「西」とはなんなのか?;ナチズムは近代西洋的価値観の結晶 ほか)
著者等紹介
岡真理[オカマリ]
1960年生まれ。早稲田大学文学学術院教授。専門は現代アラブ文学、パレスチナ問題
小山哲[コヤマサトシ]
1961年生まれ。京都大学大学院文学研究科教授。専門は西洋史、特にポーランド史
藤原辰史[フジハラタツシ]
1976年生まれ。京都大学人文科学研究所准教授。専門は現代史、特に食と農の歴史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
がらくたどん
60
同じ読書会に参加している司書の先輩のお勧めYA。「中学生から」と表題にあり内容も平易な語り口の講演録中心なのだが、その分一章ワンテーマではないので「要するに」を求めると決して容易ではない。だが、今ガザで起きている事を見る時の光の当て方を改めて見直すのにはとても役に立つし面白い。まず最初の岡真理氏の講演ではガザで起きている事を長い世界史の中に繰り返し点在する入植植民地主義と先住民の脱植民地化を求める抵抗の歴史の延長線上にある出来事として見てみようという提案が目を引く。その中で単なる宗教文化の違いが「人種」→2025/09/05
やいっち
58
楽しみで読む本もあれば、世界の実状を知るため読むべき本もある。本書は明らかに後者。入門編かな。でも、無知な我輩にはカルチャーショックだった。感想は(書けたら)後日。2024/11/16
mikarin
38
今のイスラエルを見ていると本気なんだと分かる。あの地を物理的にも歴史的にもまっさらの更地にしてイスラエルを作るつもりなんだ。まるで二千年前からそこにあったように。狂ってると思った。でも本当にそうだろうか。本当は人類がずっと行ってきたことなのでは?著者の3人が自分たちの学び方に疑問を感じ反省してこれからの歴史学の在り方について考えてるのがよかった。それはそれとしてとにかく今はイスラエルを一刻も早く止めたい。2024/09/07
kameyomi
33
イスラエルがパレスチナにしていることは、余りにも酷い事だが、それをダイレクトに批判していいのかという躊躇いが、本書を読むまではあった気がする。そして、「食」が権力と深く関わってきて今も続くという恐ろしさを学んだ。「飢えてもいい人びと」を選ぶような優生思想が我々の日常にも深く根づいていると。かつてナチスは「生きるに値しない」とみなした人々を飢餓状態に放置することで殺害した。現在イスラエルがガザ地区にしていることも同じ事なのは何故なのか。2025/08/16
やいっち
20
楽しみで読む本もあれば、世界の実状を知るため読むべき本もある。本書は明らかに後者。入門編かな。でも、無知な我輩にはカルチャーショックだった。感想は(書けたら)後日。2024/11/16
-

- 洋書電子書籍
- Theory and Applicat…