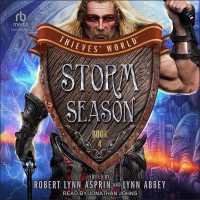出版社内容情報
坂本龍一の傍にはいつも本があった。
「いつか古書店の店主になるのが夢だった」と語り、東京の仮住まいでも特製の本棚を設け新旧の本を蔵していくほど、無類の本好きで愛書家だった。
本書は、2018年から2022年にわたり、婦人画報に掲載していた連載『坂本図書』全36回分と、2023年3月8日に実施された、坂本龍一と旧知の仲である編集者・鈴木正文氏との対談「2023年の坂本図書」を収録しています。
本から始まり、本に気づかされ、本で確信する。
本を媒介に浮かび上がる、坂本龍一の記憶と想像の人物録です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
112
ロベール・ブレッソンやアンドレイ・タルコフスキーなどの映画を、かつて六本木のWAVEの地下のシネ・ヴィヴァンというミニシアターで観たのを思い出す。映画のパンフレットで武満徹と蓮實重彦の対談が理解出来ないながらも楽しみだった。ひとり暮らしの大学生の頃、NHK-FMから流れる坂本龍一の声を昨日の事のように思い出す。お父様が出版社に勤めていたので、学生時代から本に親しんでいたことを知った。歳を取るほど親父と同じく古書に惹かれ、自分で作れるなら箱入りの綺麗な本を作りたいと。日本が誇る文化人を失ったことを実感する。2023/11/29
kaoru
77
著名な編集者を父に持ち自らも無類の本好きだった坂本龍一氏が影響を受けた数々の本を紹介。武満徹などの作曲家、大島渚やタルコフスキーといった映画監督にまつわる本は当然という感じだが、読書を通じて彼が人類史や時間に関する考察を深めていった様子が伺える。幅広い分野に関心を抱いた彼は、新型コロナウィルス以来、地球の在り方に危機感を強めた。今西錦司『生物の世界』、藤原辰史『分解の哲学 腐敗と発酵をめぐる思考』…どこを開いても坂本氏の思索と洞察に触れることが出来るのが嬉しい。2023年には鈴木正文氏との対話で漱石や→2024/06/02
里愛乍
72
year of the Dragonの一冊めは坂本龍一氏の本書と決めていた。ありがちな選書の紹介だけではないだろうとは思っていたが、ここまで綺麗でお洒落でまた深く考えさせられる本であるとは読むまでは思わなかった。これはもう氏による哲学といってもいいのでは?そう思わせる言葉の数々、これは自分が歳を重ねるに連れ、何度も読みたくなる本だ。埴谷雄高氏の本は以前より興味あったけど絶対に欲しい、手に入れようと真面目に思った。理解出来なくても読めなくても持っていたい。教授のそういう本ってありますよね?に激しく同意。2024/01/02
優希
45
教授の感性が伝わってくるようでした。多岐にわたる読書論ですが、単なる本の紹介に終わらず、お洒落で、写真などセンスが感じられました。教授の感性は読書にも通じているのですね。2024/01/08
踊る猫
39
いったい教授とは誰だったのか。この本は実に親しみやすく、間口の広い1冊だが読めば読むほど教授という人がわからなくなる。時間や生命、音楽や文学に関して該博な知識と旺盛な好奇心を持ちその内的必然に実に素直に従って動き続け、最後の最後まで衰えを見せなかったそんな教授の「深さ」が見えてくる。ぼく自身、この本を通して教授を学び直したいと思ったクチなのだけれど結局「よくわからない」で終わってしまった。ただ単に短絡的に「ブックガイド」や「本好きの本」とレッテルを貼ることを拒ませる何かがこの本には魔力としてあるように思う2023/10/23
-

- 洋書
- Siku & Pete