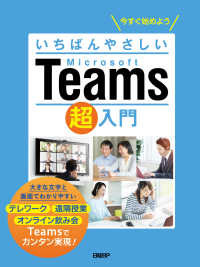出版社内容情報
今もっとも注目される
歴史学者の新機軸
人間は何より高等な生命だと私たちは思いがちだ。だが、それは真実だろうか?歴史、文学、哲学、芸術を横断し、ありうべき人間の未来をさぐるエッセイ。
内容説明
はたして人間は植物より高等なのか?植物のふるまいに目をとめ、歴史学、文学、哲学、芸術を横断しながら人間観を一新する、スリリングな思考の探検。
目次
第1章 植物性
第2章 植物的な組織
第3章 大気のクリエーター
第4章 植物の舞踏―ブロースフェルトの『芸術の原形』に寄せて
第5章 根について
第6章 花について
第7章 葉について
著者等紹介
藤原辰史[フジハラタツシ]
1976年生まれ。京都大学人文科学研究所准教授。専門は農業史、食の思想史。2006年、『ナチス・ドイツの有機農業』(柏書房)で日本ドイツ学会奨励賞、2013年、『ナチスのキッチン』(水声社/決定版:共和国)で河合隼雄学芸賞、2019年、日本学術振興会賞、『給食の歴史』(岩波新書)で辻静雄食文化賞、『分解の哲学』(青土社)でサントリー学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
124
人間は植物を自分より劣った生物と考えているのではないか?人間は植物がないと生きていけないが、植物は人間がいなくても生きていける。約30億年前に共通の祖先から分かれた同志。植物と動物の視覚機能はどちらもクリプトクロムという青色光受容体を有する共通点がある。植物は動く。そして地球の大気を作り、様々な生物と共同作業を行う。世界最古の植物の化石には葉も根もない。葉が増え出すのは4000万年後である。植物は人間がただ老いていくだけなのと異なり、花を咲かせたり、咲かせなかったり、大人と子どもの間を行ったり来たりする。2023/02/03
たまきら
43
「ナチス・ドイツの有機農業」を読んだとき、「意識高い系」が生んだ分断の歴史が新しいものではないのだと、ゾッとしたのを覚えている。「美味しんぼ」で行き過ぎた菜食主義者に「動物はダメで植物はOKというのは傲慢ではないか」という趣旨の回があったときも、「賢い動物は食べてはいけない、苦しめてはいけない」という主張にも、どこか居心地の悪さを感じた。食材への奇妙なランク付けや忌避観念(背後に西洋文化の押し付けがありません…?)に違和感を感じている人には一読の価値がある一冊だと思う。2023/11/05
鯖
18
「ナチスのキッチン」の藤原先生の植物考。欧米で消費される熱帯植物と欧米で生産される動物産品である毛織物等の工業製品を交換し、その不足を補う対価として新大陸から流入した金銀が再流出するのが重商主義政策というのはアーってなった。植物は大地から離れられないけれど、環境が同じであれば地球上の遠く離れた地でも育つ。南米原産のゴムが東南アジアのプランテーションで育つように。…先生、バジルの芽のふつくしさに触れておられるのですが、私、今年もバジル栽培失敗したんすよね。シソと空芯菜はプランテーションみたくなってるのに。2024/09/05
さとちゃん
10
一年も購入するかどうか迷っていたところ、本屋さんのお薦めで購入、読了。「はたして人間は植物より高等なのか?」はスリリングな問いだ。その問いに対する答えは、本書を読んでのお楽しみ。モンステラの葉が光をいかにうまく捉えるように育つかの描写は、思わず私もモンステラの鉢を買いに行きたくなったほど。カバーの、石内都氏の写真がまたしびれるくらい素敵! 2023/10/11
YT
9
人間は植物の上位種なのか?という問いから、植物性・根・花・葉・種などに付いての考察をおこなう。 植物・アート・歴史・チャペックにいとうせいこうのエッセイなど文理またぎながら植物とはなにかを共に考えていく一冊。本書に明確な答えがあるわけではない。 植物世界の考察が人間の役に立つか、という植物を劣位に置く思考を捨て植物の人間性、あるいは人間の植物性などを考えるのはとてもスリリングで面白い。 学生時代、生物が大好きだったが、文系が得意だった私にはとてもおもしろい読書体験だった。2024/01/03
-

- 洋書電子書籍
- Computational Scien…