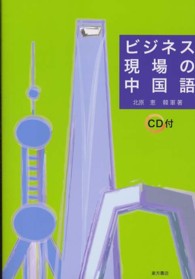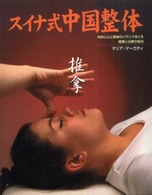内容説明
走ることについての古今東西の哲学やヨガや様々なスポーツの体験談、トレーニングや食事法、エッセーや散文がまとめられた稀有な一冊
目次
第1章 わが道を走る
第2章 戦うランナーのためのトレーニング
第3章 総合芸術としてのトレーニングプログラム
第4章 未来のアスリート
第5章 ランニングの精神性について
著者等紹介
スピーノ,マイク[スピーノ,マイク] [Spino,Mike]
ランニング・コーチ、「スピーノ・ランニング&ザ・マインドフル・ランナーズ(spinorunning.com)」ファウンダー、CEO。シラキュース大学卒業、リール2大学でメンタル・トレーニングと管理についての研究で博士号を取得。ジョージア州立大学教育・人間開発学カレッジの大学院プログラムで教壇に立つ。1970年代から90年代にかけてエサレン・スポーツ・センターのディレクター、ジョージア工科大学及びライフ大学でのコーチ、国際連合の「The International Year of Sport and Physical Education 2005」における米国でのスポーツ・開発・平和に関するプログラムのディレクターを歴任
近藤隆文[コンドウタカフミ]
翻訳家。一橋大学社会学部卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Take@磨穿鉄靴
32
ちょっとターゲットが分からない本だった。訳の問題かタイトルが「ほんとうのランニング」となっているけどランの定義はそんなに明確ではないしそもそも簡単に定義しきれるものでもない。トレーニング目線だとダニエルズやリディアーノの方が圧倒的な説得力がある。瞑想というかマインドフルネスの目線からそれを期待して読んだがその答えは見付からなかった。タイトルが大袈裟過ぎて肩透かし。「ぼくの考えたほんとうのランニング」にした方が期待値的にちょうどいい。もう読まない。★★☆☆☆2023/02/20
鈴木拓
18
ランニング、あるいはスポーツの究極的な目的とは、自分と向き合うことなのだという哲学。タイムなどの数字は本当の目的ではなく、自分の限界の向こう側にある世界を求める中で、ある瞬間に見える世界があるのだという。よくある問いで、何のために走るのか、というものがあるが、それを他人に伝える意味もそれほどないのかもしれない。答えは自分が理解していればよいのだから。2022/06/18
チェアー
6
具体的なランニングの技術を学びたい人向けではなくて、トレーニングに臨む心構えや、メンタルが走ることにおいて大きな要素を占めていることを示した本。 巻末のオカルトチックな話はちょっと…。(関係者はこれこそ必要なんだ、と言うのだろうけど) 2022/01/29
もも
5
書き方?訳し方?なのか小難しくなかなかすんなり入ってこなかった。2025/04/13
bibliotecario
4
ニューエイジ系ランニング読本?なにをいってるのかわからない箇所が多数。2022/02/26