内容説明
明治憲法から新憲法への交代になぜ高い価値があるのかを経験的に知る世代が、民主主義国日本の出発に際して示した要点。天皇を象徴として存置することで過去との切断を回避した民主主義国家、そして交戦権を放棄した独立国家。―それを支えるものは何か。現憲法制定同時代の代表的法哲学者が、法哲学的/政治哲学的視点から平易に語る。現憲法を貫く統一的理念/基本思想としての哲学。
目次
新憲法と民主主義(天皇の象徴的地位について;改正憲法の革命的性格;民主政治の実現;法の革新と道徳の進展;交戦権の放棄;基本的人権について;改正憲法と経済生活;新憲法と経済的基本権)
国民主権と基本的人権(主権者たる国民;基本的人権の主体としての国民;全体としての国民と国家及びその機関;基本的人権の特性;基本的人権の体系)
憲法(日本国憲法;国民主権;基本的人権;国会中心主義;違憲立法の審査)
著者等紹介
恒藤恭[ツネトウキョウ]
1888‐1967。法哲学者。京都帝国大学法科大学卒業。同志社大学教授、京都帝国大学助教授を経て、同教授。1933年滝川事件に際して辞職。その後、大阪商科大学講師、教授、学長、大阪市立大学学長、京大教授兼任
和田小次郎[ワダコジロウ]
1902‐1954。法哲学者。早稲田大学法学部独法科卒業。早稲田大学講師、助教授を経て、同教授。戦後、日本学術会議学問思想の自由委員会委員
尾高朝雄[オタカトモオ]
1899‐1956。法哲学者。東京帝国大学法学部卒業後、京都帝国大学文学部哲学科卒業。京城帝国大学教授を経て、東京帝国大学法学部教授。欧米留学時代(1928年から1932年)にはウィーンでケルゼンに、フライブルクでフッサールに師事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
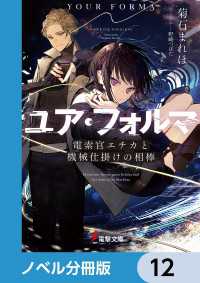
- 電子書籍
- ユア・フォルマ【ノベル分冊版】 12 …







